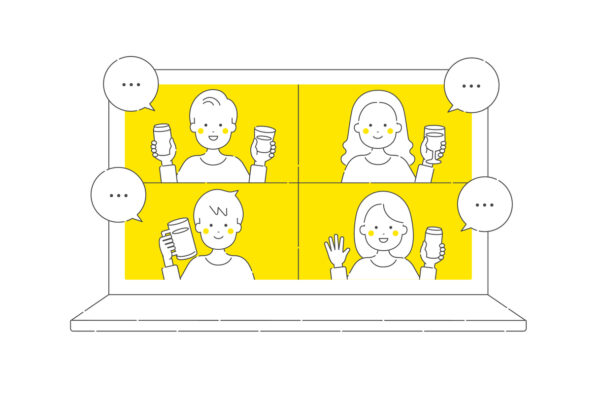updated: 2025
利き茶とは?実施する際の進め方やポイントを紹介

利き茶は、5~6種類程度の紅茶や緑茶を用意し、目隠しをした状態で最初に飲んだお茶がどれなのかを当てるゲームです。全体で共通体験ができるため一体感の醸成につながり、コミュニケーション促進が期待できます。
本記事では、利き茶の概要、目的・効果、ルール、進め方、実施する際のポイントを紹介します。
利き茶とは

利き茶は、銘柄が異なる緑茶や紅茶を用意し、目隠しをした状態で飲んだお茶を当てるクイズゲームです。
目隠しをして1種類のお茶を飲み、目隠しを外してからすべてのお茶を試飲して、最初に飲んだお茶がどれなのかを考えます。目隠しをすることでお茶を飲んで得られる情報量が少なくなり、次に飲むお茶の味や香りが更新されるため、正解を言い当てることが難しいことが利き茶の特徴です。
利き茶をおこなうことで、全員が同じ体験をすることができるため、一体感が醸成されます。また、共通目標の達成に向かうため、帰属意識の状態やチームビルディングにつながる効果も期待できます。
利き茶の他に、同様のやり方で利き酒も実施可能ですが、飲酒することが前提となるため、基本的には利き茶がおすすめです。
利き茶を実施する目的・効果

以下では、利き茶を実施する目的や、期待できる効果について紹介します。
共通体験による一体感が醸成される
利き茶を実施する際には、オンライン通販などでお茶を簡単に揃えられます。また、全員が同じ飲料を飲むことができるため、共通体験となり、一体感が醸成されます。そのため、新入社員や若手社員などの関係性の構築が不十分な方々を対象とした社内レクリエーションや研修に適しています。
体験を通じてコミュニケーションが促進される
利き茶で飲んだお茶の味や香り、ゲームとしての難しさなどの共通の体験を通じて、懇親会などでのコミュニケーションのきっかけ作りになります。利き茶体験により会話が促され、振り返りを通じてコミュニケーション活性化につながります。
利き茶のルール

- 目隠しをした状態でお題となるお茶を飲む
- 目隠しを外してからすべてのお茶を飲んでどれが正解かを予想する
- 試飲回数や量には制限がない
- 回し飲みはせず、自身の紙コップを使う
- それぞれのお茶をアルファベットで区別する
- 最初に飲んだお茶を当てることができれば成功となる
ルールはシンプルで、お題となる最初に飲むお茶を見てはいけないことがポイントとなります。試飲回数やの無料には基本的に制限がなく、確認のために複数回試飲しても問題ありません。ただし、お茶の量が少ない場合など、試飲できる量や回数に制限を設けることが適切な場合は、そのようにするとよいでしょう。
利き茶の進め方

- 5~6種類程度の銘柄が異なるお茶を用意する
- 挑戦者は目隠しをした状態でお題となるお茶を飲む
- 目隠しを外し、すべての銘柄のお茶を試飲する
- 最初に飲んだお茶を選ぶ
- 当てることができれば成功となる
利き茶をおこなう際は、上記の流れで進めることが基本となります。5~6種類のお茶と記載していますが、少なくても問題ありません。また、緑茶、ほうじ茶、玄米茶のように種類が異なるお茶や、ダージリン、アールグレイ、アッサムのように茶葉が異なる紅茶を用意する形での実施も可能です。
利き茶を効率よく実施するには、5~6人程度のグループを作り、まとめて実施する方法がおすすめです。全員が同じお題のお茶を飲みます。試飲しながらコミュニケーションを取って他者の意見を参考にできる形と、解答を出すまで会話をしない形があります。実施する目的に応じて、適した方法で実施しましょう。
利き茶を実施する際のポイント・注意点

以下では、利き茶を実施する際に押さえておきたいポイントや注意点について紹介します。
参加者の年齢や目的に応じて難易度を調整する
参加者の年齢に応じて、利き茶の難易度を調整することがポイントとなります。たとえば、複数の銘柄の緑茶を用意すると、味が似通っていて、難易度が高くなります。一方、緑茶、ほうじ茶、玄米茶のように、茶葉や抽出方法などが異なるお茶にすると、味や香りの違いが増し、難易度が下がります。また、レモンティー、アップルティー、ピーチティーのように味も香りも大きく異なる紅茶にすると難易度が低くなります。
簡単すぎると没入して楽しみにくくなるため、参加者の年齢などを考慮し、適正な難易度にすることが重要です。一度、企画者側で実験的に試してみて、やや高い程度の難易度に設定するのがおすすめです。また、ほぼ同じ味・香りのお茶があると混乱しやすくなるため、違いがあるお茶で選択肢を作るようにすることも大切です。
コミュニケーションを促す工夫をする
利き茶は、グループで一緒におこなうこともできます。目隠しをして飲んでから、目隠しを外してから試飲して検討し、解答するまでの流れをグループで一緒におこなうことで、実施しながら参加者同士のコミュニケーションを促進させることができます。
基本的には、試飲しながら会話ができるようにしたほうが、コミュニケーションが促進されるためおすすめです。また、懇親会などを実施し、利き茶体験を振り返りながらコミュニケーションを取る形にするのもよいでしょう。
十分な量のお茶を用意する
利き茶を実施する際に、途中でお茶がなくなってしまうと、体験できない参加者が出てしまう可能性があります。1人あたりの試飲する量を100~200ml程度で計算したうえで、余分にある状態にするのがおすすめです。また、確実に途中でなくならないようにするために、1人あたりの試飲可能な量に制限を設け、あらかじめ紙コップなどに注いでおくとよいでしょう。
参加者の苦手な食品を避けるようにする
場合によっては、参加者のなかにお茶や紅茶が苦手な人や、意図的にカフェインレスでないと飲まないようにしている人などがいる可能性があります。事前にアンケートを取り、苦手な食品がないか、カフェインを含む食品に問題がないかなどを確認しておきましょう。
利き茶を実施するなら、「格付けバトル」がおすすめです。

格付けバトルは、見る・嗅ぐ・食べるなど五感を使い、一流品を当てる体験型クイズゲームです。
お題はカスタマイズが可能なため、「一流のお茶はどれ?」というテーマで利き茶を実施することが可能です。そのほか、絵画や俳句、牛肉など、さまざまなテーマを選択できます。
個人戦・チーム戦どちらでも開催可能で、懇親会や周年イベントに最適です。
まとめ

利き茶をおこなうことで、一体感の醸成やコミュニケーション促進につながります。実施する際のポイントを押さえ、利き茶を通じて参加者同士のコミュニケーションを活性化させましょう。


 IKUSA.jp編集部
IKUSA.jp編集部