updated: 2025
OODAループ(ウーダループ)とは|PDCAとの違いや事例を学び個人・組織の生産性を高める

目次
OODAループは、PDCAサイクルよりも汎用性が高く、個人や企業の決断力を高めて生産性を上げるフレームワークです。株式会社IKUSAの新サービスとしてリリースした「サバ研(サバイバルゲーム研修)」で、より楽しく効率的にOODAループを学べます。
今回は、OODAループとは何か、PDCAとの違い、学ぶメリット、海外事例、学び方・実践方法について網羅的に紹介します。
受け身では終わらせない、行動につながる研修へ。
Z世代の関心を引き出す、テーマごとのゲーム型研修プログラムをまとめた資料をご用意しています。
初めてのご相談でも安心。研修プランナーが最適なプログラムをご提案します。
OODAループ(ウーダループ)とは
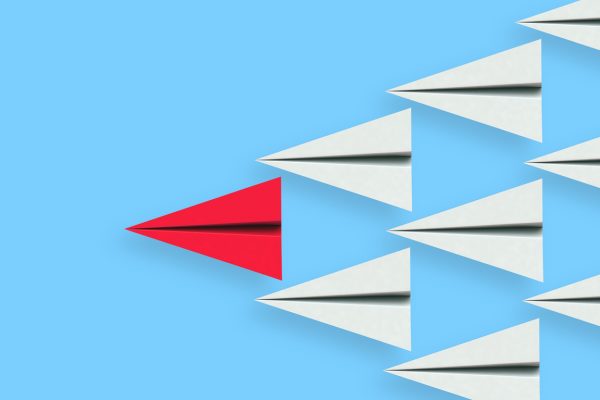
近年、企業や個人の間でOODAループというフレームワークが注目を浴びています。海外で誕生したOODAループは、PDCAサイクルよりも汎用性が高く、生産性を上げるために有効な手段とされています。
OODAループが生まれた背景やそれぞれの意味を学び、OODAループのフレームワークを効率よく習得しましょう。
OODAループの歴史
OODAループとはもともとアメリカ空軍の戦闘機パイロットが考案した理論で、瞬時の判断が必要とされる戦場で利用されていた方法です。意思決定の速さが勝ちにつながるOODAループのプロセスはロシア・中国軍のほか、テロ組織でも注目されるようになりました。
のちにビジネスやスポーツ、政治や教育の現場などにも応用され、「迅速な対応が求められる、現場に応じた行動をするための仕組み」として広まりました。
OODAループの「OODA」とは?
OODAループの4つの頭文字はそれぞれObserve(観察)Orient(状況判断)Decide(意思決定)Act(行動)を指しています。よくPDCAサイクルと同じような認識をされがちですが、それぞれ役割は異なります。
Observe(観察)
周囲の状況をよく観察(見るのではなく「観る」)しながら、できるだけ多くの情報を的確に収集して把握する。ただ見るだけでなく、意識して気づきを得ることが重要。
Orient(分かる)
集めた情報をもとに状況を判断し、将来像を予測する。自分が持っている過去の経験や知識などを掛け合わせて目指すべき方向性や世界観(ビジョン)を作る。正確さよりも方向性や世界観に意味があることを優先させる。
Decide(決める)
直感ではなく「直観」で判断する。目指す方向や世界観を実現するために最適な手段や方法、順番などを多様な選択肢の中から選び決定する。
Act(行動)
決定した方法をもとに実際に行動に移す。意志の強さが重要。
ActのあとはObserveに戻り、上記の「OODA」を「ループ(繰り返す)」します。失敗した場合や環境が変わったときは今までの方向性や考え方に捕らわれず、世界観を更新し迅速に切り替えます。それを何度も繰り返すことで物事を瞬時に判断し、すぐに行動に結び付けられるため想定外の事態にも対応できるようになります。
OODAループとPDCAサイクルとの違い

OODAループとよく比べられるフレームワークが、PDCAサイクルです。OODAループとPDCAサイクルは似ているようで内容は大きく異なります。それぞれの特徴をよく理解して使い分けることが重要です。
PDCAサイクルと比較すると?
PDCAサイクルはもともと日本で生産管理や品質管理に活用されてきた、業務管理や改善のためのフレームワークです。計画(Plan)ありきで計画通りに動くことが重視されるため、計画や目標を作成し、結果に対して改善するまでの一周にある程度の期間を要します。
それに比べてOODAループは環境の変化に対応しやすく、短期間で何度も回すことが可能です。そのため、PDCAサイクルは事業部全体での経営方針や計画を立てるときなどの長期的な目標付けに役立ち、OODAループはその場で柔軟な判断と行動が必要なスピード感のある現場向きの行動指針と言われています。
実は、PDCAサイクルというものは日本にしかありません。それに比べ、アメリカで生まれたOODAループは世界中で活用されている汎用性の高いフレームワークなのです。
PDCAサイクルとOODAループ、どちらを使うべき?
PDCAサイクルとOODAループは、状況に応じて使い分けることが重要です。もともと品質改善のために作られたPDCAでは計画の作成に時間がかかる反面、OODAループは計画に時間をかけられない場面でも臨機応変な対応に役立ちます。また、初めての行動で過去の経験が活かせず、PDCAのようなしっかりした目標設定が立てにくいときにもOODAループを使うことでひとまず行動に移すことが可能です。
PDCAサイクルの「Do」部分を実践用にかみ砕いたものがOODAループ、というイメージをすると分かりやすいでしょう。
OODAループをサッカーの試合に例えると?
OODAループをサッカーの試合に例えてみましょう。「試合までに相手チームの傾向を研究し攻め方を考え(Plan)、試合後(Do)は結果に対して対策を練り(Check)次の試合に活かす(Action)」というのがPDCAだとすると、「相手選手の動きや攻め方をしっかり見極め(Observe)、監督が状況を判断し(Orient)、選手に戦略を伝えて(Decide)行動にうつし(Act)」、それを試合中に何度も繰り返しおこなうのがOODAループです。
参考:PDCAサイクルとOODAループとは?2つの違い、メリット・デメリットを解説|あそぶ社員研修
OODAループのメリットは?

企業や個人の行動指針にOODAループを取り入れるメリットはいくつかあります。ここではその4つのメリットを見てみましょう。
メリット①すぐに行動に移せ、物事に対する対応が早くなる
OODAループはあらかじめ目標や指針がなくとも回すことが可能なため、短い期間でもすぐに行動に移せることが一番のメリットです。短いサイクルで繰り返し回すことで、タイムロスがなく環境の変化にもすぐに対応することができます。
メリット②イレギュラーに対応しやすい
先ほど述べたとおり、OODAループはすぐに行動に移せるため、とっさの判断が必要な場合は特に効果を発揮します。例えば大地震などの天災が起こった際でも、その場の状況をすばやく理解して適切な行動に移すことが可能です。普段から準備や予測がしがたい想定外の事でも、OODAループを実行することで被害を最小限に抑えることも可能です。
メリット③個々に責任感を与えることができる
OODAループは企業などのグループ全体ではなく現場や個人などの小規模単位で回すことが多いため、それぞれが行動に責任感を持つようになります。また、無意識に行動するよりもOODAループを用いて意識的に行動に移すことで、突然のトラブルが発生しても冷静に対処することができます。
メリット④新しい事業の行動指針に活用できる
OODAループはあらかじめ目標を設定する必要がないため、新規事業などの先の見通しが立てにくいプロジェクトの場合はPDCAサイクルよりも活用しやすいという特徴があります。
OODAループの海外企業の事例

海外では決断や行動が早いOODAループのフレームワークを取り入れることで、事業に成功した企業が多く存在します。
たとえばアメリカでは、このような企業がOODAループを使って成功しています。
Dell
OODAループの戦略を活用することで、ソリューション・プロバイダーにおける競争優位を獲得。
モンデリーズ・インターナショナル
ナビスコやオレオ、リッツなど日本でも有名なモンデリーズも菓子業界で上位になることにOODAループの戦略が役立った。
GRHノースアメリカ
OODAループをビジネスに取り入れることで、無名の企業からNAFTA地域の市場で最大手のサプライヤーへと成長。当時の最高責任者(CEO)がOODAループを活用していることを公表した。
リーンカンバン大学
授業の他人に必要な戦略フレームワークの中にOODAループが含まれている。
また、「長時間労働のわりに生産性が低い」と言われてきた日本企業も、近年ではPDCAサイクルの代わりにOODAループを取り入れる傾向にあります。リーンスタートアップやデザイン思考、タイムベース競争などの名前で広まっているものは、すべてOODAループの考え方を用いたフレームワークとされています。
今後も経済に関わらずOODAループの考え方が日本で広まることで、あらゆる分野で国内の生産性が伸びていくと言えるでしょう。
生産性の高い組織をつくるOODAループマネジメント

日本は品質管理のためのPDCAサイクルを使い経済発展に成功してきましたが、それから数十年たち、環境や状況が変化した現在でも同じフレームワークを使い続けています。そのため今では生産性が悪いまま、経済が停滞してしまっている状況です。
プレジデント誌が「PDCAは日本企業を停滞させた元凶」と発表したこともあり、日本企業は現状を打破するため、今までのやり方を変える選択を迫られています。そこで、海外の経営戦略で採用されている、OODAループの手法が注目されるようになったのです。
シリコンバレー企業など急成長している企業の経営モデルは、OODAループマネジメントとされています。これは今までのピラミッド型組織とは異なり、企業内に自律分散型の組織をつくることを意味します。想定外な事態がおこっても各組織が指示待ちすることなく自律的な行動に移すことで、状況に応じた素早い対応ができるようになります。結果として、事業転換や新規事業の立ち上げが一気にスピードアップします。
実は2019年に日本がベスト8に輝いたラグビーワールドカップでも、OODAループのフレームワークを採用したことが勝利に結びついたとされています。ラグビー日本代表のジェイミージョセフヘッドコーチが掲げた「One Team」の考え方は、各人が一体となり攻撃の役割の判断をおこなうという、まさにOODAループの思考をもとに生まれた行動方針でした。
キックやオフロードパス(とっさの判断で片手でもパス)を取り入れるなど臨機応変の訓練を重視し、試合中は一人一人が瞬時に的確な判断でプレイすることでチームの得点へと結びついたとされています。
個人の生産性を高めるOODAループ思考

OODAループの考え方は組織だけでなく、個人の生産性を高めることも可能です。OODAループを身につけることで計画や目標を立てることに時間をかけず、状況に合わせてその場で考えられるようになります。また、意識して早く決断し、そのたびに行動を見直して改善していくことで物事が何倍も早く進むようになります。
個人の生産性を高めることで指示待ちや保守的な考え方の人間が減り、グループや企業単位の生産性も上がるようになります。
OODAループを学ぶ方法

個人でOODAループの知識を身につけるには書籍などもありますが、企業やグループの場合は専門の業者や講師が開催しているセミナー、ワークショップ、アクティビティ、ビジネスゲームなど集団で学ぶ方が効率的です。たとえば新入社員の研修なら20代が楽しめそうなアクティビティを選ぶなど、OODAループの学びを浸透させたいグループの特徴や規模、予算に合わせて選びましょう。
OODAループを学べるワークショップ・ビジネスゲーム

OODAループのフレームワークを習得するには、ワークショップやゲームを通じて覚えることが近道です。たとえば室内でできるゲームとして下記のようなものがあります。
マシュマロ・チャレンジ
PDCAサイクルを学ぶ際にも使われるマシュマロ・チャレンジは、OODAループを学ぶビジネスゲームとしても採用されています。OODAループ研修としてのマシュマロ・チャレンジでは、Observe(観察)の部分に重点を置きます。相手チームの行動をよく観察したうえで、自分のチームのマシュマロ・チャレンジをどう成功させるか短時間で試行錯誤することがポイントです。
ジェスチャーゲーム
気軽な遊びとして盛り上がるジェスチャーゲームも、OODAループを学ぶゲームに向いています。表現する人は最初にジェスチャーで表現したあと、解答者の発言や考え方をふまえて瞬時に体の動きを変える必要があります。また、解答者は表現者のジェスチャーから予測できる単語を次々に発言する必要があります。いずれも制限時間があり、「相手をよく見て」「最適なジェスチャーや単語を探し」「動くor発言し」「繰り返す」ことでOODAループを実践することができます。
OODAループを学べるアクティビティ

OODAループはアクティビティを取り入れた研修で、さらに楽しみながらフレームワークを体で覚えることが可能です。ここではオススメのアクティビティを紹介します。
OODAチャンバラ合戦
OODAチャンバラ合戦は、IKUSAの人気プログラム「チャンバラ合戦」に、OODA LOOPを取り入れたアクティビティです。
チャンバラ合戦とは
チャンバラ合戦は、スポンジ製の刀を手に持ち、「命」と呼ばれるカラーボールを腕につけ、相手チームの「命」を落とし合うアクティビティです。
一度参加すれば誰でも夢中になってしまう魅力のあるアクティビティですが、ただ楽しいというだけではなく、スポンジの刀を用いるため安全で、チームビルディングにも高い効果があります。レクリエーションや社内研修におすすめです。
このチャンバラ合戦に、勝つためのフレームワークとしてOODAループを取り入れることで、体を動かし、楽しみながらOODAループを学ぶことができます。
サバゲー(サバイバルゲーム)研修

効率的にOODAループを学ぶ新しい研修方法として、現在注目を集めているのが「サバゲー(サバイバルゲーム)研修」です。OODAループはもともと軍隊から生まれたフレームワークのため、戦争の疑似体験ができるサバゲー研修は他の研修よりもリアルに近い状況でOODAループを回すことが可能です。
迅速な意思決定や臨機応変な対応といった、目まぐるしく変化する戦況に応じた行動を戦いながら学べるところが魅力です。
OODA LOOPについて知り、それが生まれた状況に近いアクティビティの中で実践すれば、話を聞くだけではわからないような深い学びを得ることができるでしょう。
OODAループ(ウーダループ)研修の効果・メリットとは?提供会社も紹介 | IKUSA.JP
まとめ

個人や企業の決断力を早め、生産性を高めるOODAループ。そのOODAループを学ぶには、企業などのグループ単位で研修を受けることが近道です。中でも株式会社IKUSAが提供する「サバ研」は、勝つための方程式である「OODAループ」を取り込んだチームビルディング型のサバイバルゲーム研修です。
OODA LOOPを学び、実践して習得していく研修をして、フレームワークを身につけていきましょう!
Z世代が“つい本気になる”仕掛けが詰まった研修を。
IKUSAでは、PDCA・OODA・ロジカルシンキング・合意形成などをテーマに、楽しみながら学べる参加型の研修プログラムをご用意しています。
企画の段階でも構いません。まずは、どんなプログラムがあるのかのぞいてみてください。
参考:




 IKUSA.jp編集部
IKUSA.jp編集部




