updated: 2026
内定者研修におすすめのゲーム17選!メリットや実施する際のポイントも紹介

目次
内定者研修は、新入社員へ会社の方針や社会人としてのマナーを知ってもらうための、企業にとって大切なイベント。しかし、受講する側にとっては不安と緊張・ストレスにもなりうる存在です。
退屈なイメージのある内定者研修ですが、ただ講義を実施するだけでなく、遊びながら仕事につながるゲームを取り入れれば楽しく学習することができます。
今回は内定者研修で役立つおすすめのゲームをご紹介。内定者研修にゲームを取り入れるメリットや、実施のポイントも解説しているので、ぜひ参考にしてくださいね。
内定辞退を防ぎ、入社に向けて連帯が強まる!
コミュニケーションイベントの成功事例を無料で配布中。
⇒他社の事例を覗いてみる
内定者研修にゲームを取り入れるメリット

「たかがゲームに、研修の時間を割くのはもったいない」と思っていませんか?
内定者研修にゲームを取り入れるメリットはたくさんあります。受講者がただ楽しむだけではなく、企業にとってもプラスに働く部分があるため、時間があれば積極的に取り入れることをおすすめします。
その①:内定者同士のコミュニケーションが円滑になる
入社したばかりの新入社員にとって、まだ研修の段階では周りの社員と会話が生まれにくく、お互いに話かけにくい部分があるでしょう。そこで研修中にゲームを取り入れることにより、会話のきっかけをが増え、コミュニケーションが円滑になります。実際に仕事が始まっても「あのゲームで目立っていた○○さんだ」というように、参加者同士の名前を覚えやすいというメリットもあります。
その②:楽しみながら仕事に役立つ考え方を理解できる
研修でおこなうのは、ただのゲームではありません。PDCAを回すことやアウトプットの練習につながるなど、研修のために考えられたゲームを取り入れることで、実際の仕事に役立つ考え方を楽しみ、体験しながら理解することができます。
その③:研修の息抜きになる
新入社員にとって、内定者研修は入社して間もない不安と緊張感があります。また、座学が多いと疲れやすく、集中力が続かなくなってきます。しかし、研修の途中にゲームがあれば受講者もリラックスでき、研修自体が楽しくなって息抜きにつながります。途中でゲームをはさむことで、研修にメリハリがつけられるのです。
その④:研修に取り入れやすい
研修に取り入れるゲームの多くはルールがあらかじめ決まっているため、想定外のハプニングなども起こりにくいように考えられています。教育側が研修自体に慣れていなくても、短時間で準備がしやすく取り入れやすいというメリットがあります。
内定者同士や先輩社員との繋がりを深め、内定辞退を防ぐ一日型企画、あります。
⇒【無料ダウンロード】内定者向け研修の資料を見てみる
ゲームを取り入れる時のポイントは?

研修内でただゲームをやるだけでは意味がありません。ここでは、内定者研修にゲームを取り入れるときのポイントを紹介します。
その①:ゲームの目的をはっきりさせる
ただゲームを行うだけでは意味がありません。「このゲームはPDCAの練習になる」といったように、ゲームを始める前に目的を理解させたうえで実施することで、より研修中にゲームを行う効果が出ます。
その②:説明と振り返りの時間をたっぷりとる
実施するゲームは初めての場合の人もいるので、ルール説明はしっかりとしましょう。ゲームの終了後も「楽しかった」「勝った・負けた」の感想だけではなく、参加者にしっかりと実施した効果を気づかせるようにすることが大切です。
その③:時間配分に気を付ける
ゲームはやっている側は夢中になり、時間を忘れてしまいがちです。ゲームに割く時間をオーバーしてしまい、振り返りの時間が短くなるといった失敗のないようにしっかりと時間調整を行うことがポイントです。
その④:参加者の感想を聞く
実施側もゲームをやりっぱなしで満足してはいけません。参加者のフィードバックをしっかりと得て、ゲームが実習として効果があったか検証し、次回開催時に役立てましょう。
内定者研修におすすめのゲーム17選

内定者研修におすすめのゲームはたくさんあります。ここでは、「卓上系」「発表系」「体を動かす系」「リアルでもオンラインでも楽しめる系」と4つのグループに分けて紹介しますので、参加者の人数やスペース、取り入れたい内容に合わせてゲームを探してみてくださいね。
<卓上系ゲーム>

謎解き脱出ゲーム
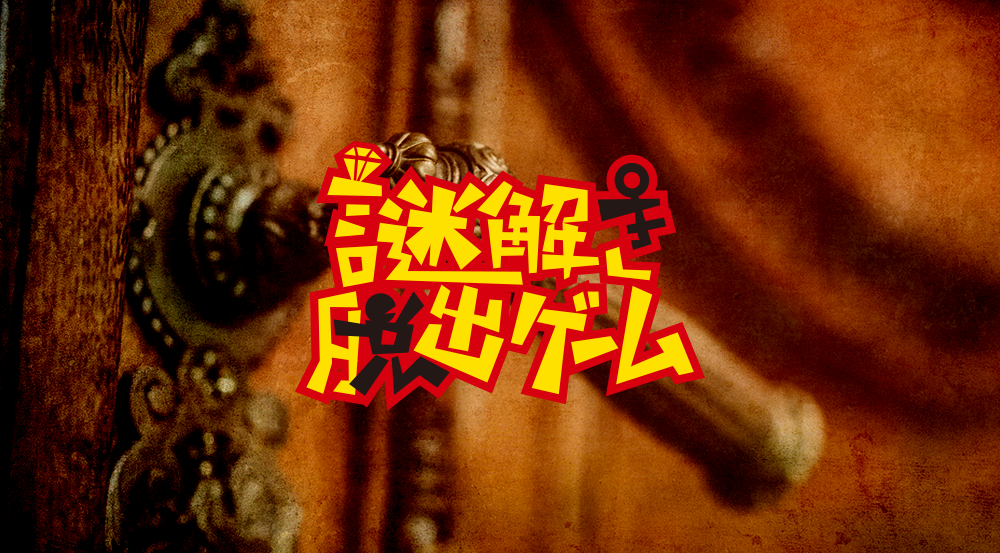
株式会社IKUSAの提供する「謎解き脱出ゲーム」は、謎解き型脱出ゲームです。
参加者は様々な場所を舞台に、チームで協力して謎解きを行い、そこから「脱出」することを目指します。
問題をカスタマイズできることから、会社の理念や行動指針を内定者に伝えることができます。
また、チームでの協力が必須なことから、コミュニケーション能力はもとより、役割分担も重要であり、リーダーシップやフォローシップを学ぶ機会にもなります。
クイズいいセン行きまSHOW! (市販のゲーム)
プレイ人数:3~10人
プレイ時間:約10~30分
すべての質問を数字で答えるクイズゲーム。問題には「『贅沢な食事』と呼べる外食は、何円以上から?」など、誰も正解を知らないようなものばかり。その場で出た解答のちょうど真ん中にあたる、“いいセンいってる”数字を出した人が「正解」というルールです。
このゲームでは常識だけでは通用しない答えを探すことと、他の参加者の回答を予想するという2つの「想像力」が必要です。さらに、自分の生活圏外のことを仮定して数値を想像するという、マーケティングなどの仕事に活かせる考え方を養うことができます。慣れれば自分たちで問題を考えることもできますよ。
遊び方
(1):最初の親を決めて全員に紙とペンを渡す。
(2):親が問題カードを引いて、好きな問題を読み上げる。
(3):問題の答えと思われる数字を、親も含めて全員がホワイトボードに書く。
(4):全員の答えを大きい順に並べて、真ん中になった数字を書いた人がポイント獲得。一番大きな数字と小さな数字を書いた人はマイナスポイントを獲得。
想像と言葉 NEW(市販のゲーム)
プレイ人数:3~12人
プレイ時間:約30分
40枚の言葉のカードから3枚を選び、「恋」「おお!」「毛」など、ランダムに出た3つの言葉から連想される単語を想像する連想ゲーム。それぞれ考えた単語を発表する際に他の参加者と同じ言葉だった場合は1ポイントが入り、一番点数が高い人が優勝です。また、面白い回答をした人には“想像王”という称号が与えられます。
共感力を高めるもよし、想像王を目指すもよし「斉藤さんと一緒の答えなら5ポイント」などとルールを自由に決めて楽しむこともできます。サービスを人に提案するときに必要な共感力や、語彙力が養われるゲームです。
遊び方
(1):裏返したチップからランダムに3枚を選ぶ
(2):3つのチップに書かれた単語から連想される言葉を想像して紙に書く。
(3):全員がそれぞれ考えた言葉を発表する。
(4):他の参加者と同じ言葉を考えた人が1ポイント獲得。また、面白い回答をした人は想像王の称号が贈られる。
カイジ×チームビルディング ~悪魔的社内研修を生き延びろ!~

⼈気漫画・アニメシリーズ『賭博黙⽰録カイジ』の世界に入り込み、カイジのゲームを通してチームビルディングができる、新体験型イベントです。
常に極限の状態に置かれる『カイジ』のスリリングな緊張感の中で、心理戦や戦略立ての過程でチーム内の活発なコミュニケーションや信頼関係の構築を促進します。『カイジ』が好きな方はもちろん、そのストーリーを知らない方も楽しめる内容となっています。
実施ゲームは以下の通りです。詳細はリンクよりご確認ください。
- 限定じゃんけん
- 地下労働
- 鉄骨渡り
- スリー・ポーカー
- Eカード
マシュマロ・チャレンジ
プレイ人数:4〜6人
プレイ時間:30分〜2時間
乾燥パスタとマシュマロを使ってチームで協力して自立するタワーを作り、一番高いタワーを作ったチームが勝つというゲーム。何度かゲームを繰り返すうちにPDCAサイクルを回す練習ができます。
さらに「私がパスタを支えるから鈴木さんはタイムキーパーをお願い」というように、全員で役割分担を行い、協力することでチームビルディングにも役立ちます。
遊び方
(1):チームで作戦を考える。
(2):パスタ、マスキングテープ、ひも、はさみを使って自立できるタワーを組み立てる(テープで足場を固定するのはNG)。
(3):タワーの上にマシュマロを置く(パスタに刺してもOK)。
(4):各チームの高さを測定し、一番高いチームが優勝。
おばけキャッチ(市販のゲーム)
プレイ人数:2~8人
プレイ時間:20~30分
「青い本」「緑のビン」「白いおばけ」など、カードに描かれた絵に対応するコマを素早く取った人がカードを獲得できる、反射神経が養われるゲーム。
なかには「緑のおばけ」「赤い本」など、コマと合わないカードもあり、瞬発力だけでなく頭の切り替えが必要です。研修でパンパンになった頭をリフレッシュするための中だるみ対策になります。
遊び方
(1):テーブルの真ん中に山札とコマを置く。
(2):山札の一番上のカードを1枚表にする。
(3):カードに描かれた「青い本」「緑のビン」などの絵に対応するコマを素早くとる。カードと同じものがない場合は、「赤いイス」などカードの絵と全く合わないものを取る。
(4):コマをゲットした人が札をもらえ、札の数が一番多い人が優勝。
十人十色
プレイ人数:3~7人
プレイ時間:約60分
チームの中にいる一人を対象者とし、「対象者なら、目玉焼きにはソース、ケチャップ、醤油の何をかけるか?」という問題を出して、チームが予想する答えと対象者の回答が一致したら得点できるというゲーム。“自分の好みと他人の好みは違う”ということを再認識できるため、第三者の好みや趣向を意識するというマーケティングの考え方を学べます。
遊び方
(1):チームの対象者を選び、対象者は部屋の外で待機する。
(2):進行役が対象者に問題シートを渡し、対象者は問題に対する選択肢の中から自分の「好み」を決定する。
(3):進行役が各チームに問題シートを渡し、チームは自分たちの好みを発表したのち、その結果を参考にしつつ教室の外にいる対象者の「好み」を考える。
(4):1チームずつ答え合わせをし、正解チームが1点を獲得。チームのメンバー全員が対象者の役割につくまで繰り返し、最後に得点が高かったチームが優勝。
SDGsビジネスゲーム ワールドリーダーズ

ワールドリーダーズは、企業経営を擬似体験できるビジネスゲームです。一チームが一企業となり、企業の利益をどれだけ上げられるかを競い合います。
利益は、労働力や資本を使って上げることができます。
しかし、このゲームは闇雲に利益を追求するだけでは勝利できず、勝利のためには、社会や環境など、様々なことを考える必要があります。
本ゲームでは SDGsにおける企業の役割だけでなく、戦略の立て方や情報共有、駆け引き、チームビルディングといった、お仕事の中で重要なことも学ぶことができます。
これから必要になるような知識を身につけることができるアクティビティですので、内定者研修にはまさにぴったりのゲームかもしれません。
プレイ人数:10~100人
プレイ時間:150~180分
SDGs カードゲーム「2030SDGs 」
カードゲーム「2030SDGs(ニーゼロサンゼロ エスディージーズ)」は、SDGs17の目標を達成するための“道のり”を体験できるカードゲームです。プレイ人数は最低5人から、最大で200人規模まで対応可能です。
このゲームは、SDGsの目的やゴールについて学ぶゲームではなく、「SDGsの本質」について体感的に学べる内容になっており、SDGsについての理解や興味がない人でも、プレイすることで「SDGsとはこういうものなんだ」と理解できます。
最近は誰もがSDGsについて取り組むことを強く求められる時代です。カードゲームから取り入れてみてはいかがでしょうか。
プレイ人数:5~60人
プレイ時間:90~180分
<発表系ゲーム>
ルールライティングワーク
プレイ人数:3~8人
プレイ時間:約20分
例えば「じゃんけん」のように、みんなが知っているルールを用紙に書きだし、一人ずつ発表するゲームです。当たり前の事でも知らない人に伝える難しさを知り、仕事をする上で欠かせない「人に分かりやすく説明すること」の大切さを学べます。
遊び方
(1):ルールを書きだすテーマを設定する。
(2):テーマをもとにルールを書きだしていく。
(3):各人が書いたルールを発表して、正解・間違いを指摘しあう。
(4):正しいルールを一番多く書いた人が優勝。
ビブリオバトル
プレイ人数:3~8人(聴講のみなら何人でもOK)
プレイ時間:約20~60分
1人5分程度の時間で、自分の好きな本を紹介する書評会。ただし、全ての参加者のプレゼンが終わったあと、読みたくなった本(=チャンプ本)を投票して決定するため、スポーツのような勝ち負けを味わえます。
プレゼンの内容には本の流れをまとめた単なる書評だけではなく、自分の感想やおすすめポイントを入れるようにします。プレゼン力を養えるほか、普段から本を読む時にアウトプットすることを意識して読む練習にもつながります。
遊び方
(1):発表者が順番に1人5分で本を紹介する。
(2):それぞれの発表のあとに、その発表に対するディスカッションを2~3分おこなう。
(3):すべての発表が終わったあとに「一番読みたくなった本」を基準に投票し、一番投票数が多かった本を「チャンプ本」とする。
他己紹介ゲーム
プレイ人数:6~10人(聴講のみなら何人でもOK)
プレイ時間:約30~60分
2人組になってお互いに質問を繰り返し、パートナーのことをチーム全員に発表するアイスブレイク。相手のことをよく知らないと発表できないので情報収集力が問われるほか、自分のことを伝えるコミュニケーション能力が養われます。また、ヒアリングを通して他者を発表することで、短時間でのインプット&アウトプットの練習にもなります。
遊び方
(1):制限時間を決め、2人組になってお互いの情報をインタビュー形式で聞き出す。
(2):聞きだした情報をまとめる。
(3):チーム全体に向け、順番にペアを組んだ相手の紹介をする。
「実は○○です」自己紹介
プレイ人数:4~10人(聴講のみなら何人でもOK)
プレイ時間:約20~40分
自己紹介の最初に「実は……」で始まる内容を入れてもらうアイスブレイク。「実は」をつけることでその人の意外な趣味や性格を知ることができるため、自己紹介が面白く印象的になり、聞いた人はその人の秘密を知ったような気分になれます。そのため、研修が終わったあとも「ヒマラヤに登ったことがある島田さん」というように、相手のことをしっかりと覚えることができます。
また、報連相やコミュニケーションが大事な社内において、自分から情報を開示する練習にもなります。
遊び方
(1):順番に「実は…」で始まる自己紹介をする。(話題は1つでOK)
(2):自己紹介が終わったら、時間がある限り2巡目、3巡目と繰り返す。
1分時計
プレイ人数:人数を問わない
プレイ時間:約1~2分
参加者に時計を見ずに心の中で1分を計ってもらい、1分たったと思ったら手を挙げてもらうゲーム。1分でも人によって時間の感覚はバラバラなので、時間の概念の大切さを学び、仕事中でも1分1秒をムダにすることがないように意識することができます。
特に自己紹介などのプレゼン前に取り入れると役立ちます。
遊び方
(1):参加者に目を閉じてもらう。
(2):進行役の「よ~い、スタート!」の合図で、参加者は心の中で1分をカウントする。
(3):参加者は1分がたったと思ったところで手を挙げる。
(4):進行役は1分たったところでそれを伝え、全員に目を開けてもらう。
また、これらのビジネスゲームと一緒にフレームワーク「SDGsマッピング」を実施することで、より学びを深めることができます。
SDGsマッピングは、自社の取り組みとSDGsを結びつけるワークショップです。 SDGsの目標を構造化して示した「ウェディングケーキモデル」に自社の取り組みを分類し、自社とSDGsのつながりを見つけます。 IKUSAのSDGsマッピングは、SDGsボードゲーム「ワールドリーダーズ」もしくはオンラインSDGs謎解き「ある惑星からのSOS」とセットで実施します。ゲームとワークショップをセットで行うことで、ゲームでの体験をより深い学びに落とし込むことができます。また、ワークに入る前に、SDGsの基礎的な内容について解説を行うため、SDGsの知識があまりない方でも気軽に取り組めます。 SDGsマッピングを行い自社とSDGsのつながりを感じることで、SDGsを身近なものとしてとらえ、自分ごと化することができます。
自分の意見を活発に発表するこのアクティビティは、内定者研修にもおすすめです。
<体を動かす系ゲーム>

バースデイライン
プレイ人数:8~15人
プレイ時間:5~15分
制限時間内に、誕生日の早い順から順番に一列に並ぶゲーム。ただし、終始無言で行い、言葉を使ってはいけません(筆談もNG)。
言葉で伝えられるコミュニケーションの大切さと、言葉が通じなくても相手の気持ちを推測するノンバーバルコミュニケーションの重要性を同時に学ぶことができます。
遊び方
(1):誕生日の早い順(先頭が1月1日生まれ、最後尾が12月31日生まれ)に一列に並ぶ。しゃべることや筆談はNG。
(2):制限時間がきたら、先頭から順番に自分の誕生日を言う。
(3):メンバーの誕生日の順番を間違えずに並んだチームが優勝。
謎解き脱出ゲーム

プレイ人数:5~8人
プレイ時間:20~60分
ネットで生まれた「謎解き脱出ゲーム」を現実の世界で行うゲーム。数人でチームを組み、部屋に隠されたヒントを探しながら謎を解き、部屋から脱出するのが目標です。
思考の柔軟性や発想力が問われるほか、謎を解くために情報共有やリーダーなどの役割分担を行うことで、コミュニケーションやチームビルディングとしても活用できます。
遊び方
(1):与えられた資料やヒントをもとに、チームで謎を解いていく。
(2):制限時間内に脱出できたら成功、できなければ失敗。
(3):全チーム終了後、進行役が謎の答え合わせを行う。
チャンバラ合戦

プレイ人数:30~300人
プレイ時間:60~90分
スポンジでできた刀で、相手が肩につけた「命」の代わりのボールを落とす「チャンバラ合戦」は、頭も体もフルに活用して楽しめるアクティビティゲーム。
ただ単純に叩きあうだけでなく、昔の合戦のようにきちんと戦略をたてて相手に攻め込むため、短時間でPDCAを回すことやチームワーク生成の練習に繋がります。
遊び方
(1):チームに分かれ、他チームをどのように攻めるか作戦会議をおこなう。
(2):「戦、開始!」の合図でチャンバラ合戦を行う。相手チームのボールを狙いつつ、自分のボールが落とされないようにする。
(3):自分のボールが落としてしまったらフィールドから一旦出る。
(4):フィールド内に残ったチームが勝利。
(5):(1)~(4)を数回繰り返す。
<リアルでもオンラインでも楽しめる系ゲーム>
謎パ
プレイ人数:10〜600人
プレイ時間:1時間半〜2時間
「謎パ」は、リアルでもオンラインでも楽しめる謎解きとパズルを組み合わせた「全員協力必須」の謎解きパズルゲームです。
参加者全員でチームを組んで謎のかけらを集めて謎を解いてミッションのクリアを目指します。参加者全員で交流できて、社員の士気向上に繋がるゲームです。
リモートワークで希薄化した研修者とのコミュニケーションを改善したい企業様におすすめです。
遊び方
(1):問題が書かれたデータをもらう。
(2):他のメンバーと情報を共有して謎を解く。
(3):謎を解き明かしたら次のミッションに挑戦する。
(4):ミッションを全てクリアする。
(5):最終問題に挑戦する。
(6):最終問題を解けたらゴール。
ハイブリッドイベント
プレイ人数:10〜500人
プレイ時間:1時間半〜2時間
「ハイブリッドイベント」は、リアル会場にいる参加者とオンラインでイベントをしたい参加者が一緒に楽しめるハイブリッド型社内イベントです。
参加者は、リアル会場に出向くか、あるいはオンラインで参加するかの好きな方を選んで、イベントに参加できます。オンラインでイベントを行いたい参加者と会場にいる参加者が協力して同じイベントを楽しめます。オンラインでの参加者は会場にいる参加者と同じ空間、同じ時間で作業をしているような臨場感を味わえます。
参加者全員で協力してゲームを行うので、リアル×オンラインのハイブリッド型チームビルディングの促進に繋がります。
遊び方
(1):入場をする。
(2):オープニング、ルール説明を行う。
(3):謎を解読する。
(4):解説、表彰、エンディングを行う。
ゲームを取り入れて、たのしく学べる研修にしよう

内定者研修にゲームを取り入れるメリットはたくさんあります。実務に役立つ考え方を得られるほか、参加者に「楽しかった」と思わせられるような研修ができれば、企業にプラスのイメージを持ってもらうこともできます。
楽しく学びつつ、実際の仕事にもしっかり役立ててもらえる研修にしましょう。
この記事を書いたIKUSAは、内定者や若手向けの体験型研修プログラムをご提案しています。
検討時期が先でも、お気兼ねなくご相談ください。
⇒どんなことができるか資料を見てみる
⇒まず相談してみる






 IKUSA.jp編集部
IKUSA.jp編集部




