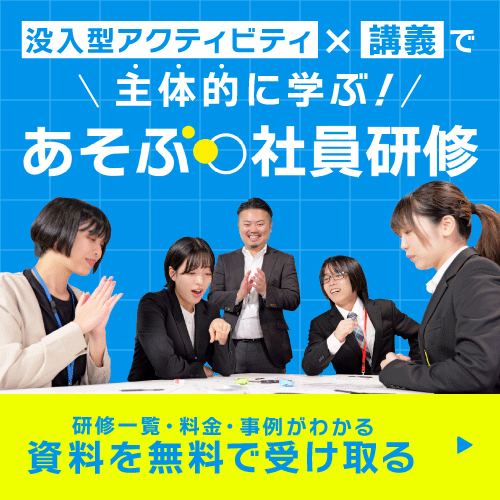updated: 2025
アクティブラーニングを活用した企業研修の効果・研修例を紹介

目次
「アクティブラーニング」と呼ばれる学習方法が注目を浴びています。学校だけでなく、企業でも社員の教育や研修の場で導入されるようになりました。企業研修にアクティブラーニングを活用することで、業務に必要な能力を効率的に修得でき、企業の成長に大きく貢献する人材育成が実現できます。
本記事では、アクティブラーニングを活用した企業研修の効果から具体的な手法まで詳しく解説していきます。
受講者が没入して取り組むアクティビティ・振り返り・専門講師が行う講義をブリッジし、研修の学びを最大化
⇒受講者のスキルアップとチームビルディングをはかる「あそぶ社員研修 総合資料」を無料で受け取る
メールアドレスのみで簡単10秒受取「研修の効果を高めるノウハウ集」
⇒無料で資料を受け取る
アクティブラーニングを活用した企業研修の効果とは

企業研修にアクティブラーニングを活用することで、おもに下記の3つの効果が期待できます。
- 主体性の向上
- 課題特定および解決に必要な能力の向上
- 自身の感情や行動を統制する能力の向上
それぞれの効果を詳しく解説していきます。
主体性の向上
アクティブラーニングには、社員の「主体性」を向上させる効果が期待されています。アクティブラーニングは指導者が一方的に講義を行うのではなく、受講者の同士で積極的に交流することで主体的に思考を深める「能動的」な教育方法だからです。
アクティブラーニングなら普段はなかなか自分の意見を主張できない社員でも、課題に対して自分で考え、論理的に表現する力が身につきます。また、仲間と協力して課題に取り組む必要があるため、主体性だけでなく協調性を養うことも可能です。
課題特定&解決に必要な能力の向上
アクティブラーニングには、課題の特定や解決に必要な能力を向上させる効果が期待されています。
アクティブラーニングの目的は正しい知識を身につけることではなく、答えのない課題に対して、仲間との議論によって課題解決までのさまざまな手法を修得することです。
変化が激しい現代社会では、従来の常識が通用しなくなってきました。そんな時代でも企業が生き残るためには、ただ知識をもっているだけでなく、状況に合わせて知識を柔軟に応用し、課題を解決する能力が欠かせません。
企業研修にアクティブラーニングを導入することで、課題に対して論理的に考え、成功に導く優秀な人材を育成できます。
自身の感情や行動を統制する能力の向上
アクティブラーニングでは、自身の感情や行動を統制する能力「メタ認知」を向上させる効果が期待されています。
組織のなかで仲間と協力しながら業務を遂行していく上で「メタ認知」は重要な能力です。メタ認知が高い人は、自分を客観的に捉えて柔軟にコントロールでき、業務においてもつねに冷静な判断や行動ができるからです。
アクティブラーニングにより「メタ認知」を向上できれば、社内で人間関係をうまく構築しながら、高い意欲で仕事に取り組める優秀な人材として活躍してくれるでしょう。
なおアクティブラーニングはオンライン研修にも有用です。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
オンライン研修にアクティブラーニングを導入するメリットや事例を解説 | IKUSA.JP
企業研修で活用できるアクティブラーニングの手法を紹介

ここからは、実際に企業研修で使えるアクティブラーニングの手法を紹介していきましょう。
具体的な手法としては、おもに下記の5つが挙げられます。
- Think-Pair-Share
- ジグゾー法
- ラウンド・ロビン
- ピア・レスポンス
- マイクロ・ディベート
それぞれの手法を詳しく解説していきます。
Think-Pair-Share
Think-Pair-Shareとは、決められたお題に対して自分の意見と他者の意見を比較しながら議論を深めていく手法です。1つの課題を全体で討論する際の土台として活用することもできます。
– Think-Pair-Shareのやり方–
- 指導者が全体に「お題」を提示する
- 数分間の間「お題」について個別で考える
- ペアになりお互いの考えを交換する(意見が異なる場合は、そのように考えた理由まで詳しく確認する)
- 可能であればペアで1つの意見にまとめて全体で発表する
Think-Pair-Shareのポイントは、自分の意見だけでなく他者の意見をしっかりと聞き、柔軟にまとめ上げられるかどうかです。自分の意見ばかりを主張しないように注意しましょう。
ジグゾー法
ジグゾー法とは、各グループのメンバーに異なる役割が与えられ、その役割のプロフェッショナルとして学習した後に、グループに戻りメンバー同士で教え合うという手法です。
–ジグゾー法のやり方–
- 4人程度のグループを作成し、人数分の学習テーマを提示する
- グループ内の各メンバーは自分が担当する学習テーマを決定し、学習内容別の専用グループに移動する
- 学習内容でわけられた専用グループ内で学習を深めると同時に、自分のグループにわかりやすく伝える方法を考える
- 自分のグループに戻り、担当した学習テーマについて教え合い理解を深める
ジグゾー法のポイントは、自分が学習テーマを理解するだけでなく、自分のメンバーにもわかりやすく伝える必要があるという点です。自分では理解できているつもりでも、他人に教えるためには内容の要点を押さえて論理的に伝えなければいけません。
ラウンド・ロビン
ラウンド・ロビンとは、決められた「お題」についてグループ内で順番にアイデアを発言していく手法です
–ラウンド・ロビンのやり方–
- 4人程度のグループを作成し、「お題」を提示する
- 発言の順番を決めてアイデアを出していく
ラウンド・ロビンのポイントは、発言の内容に対して評価やコメントはせず、とにかく新しいアイデアを出すことに注力することです。どんな些細なアイデアでも構わないので、気にせず自分の考えを発表していきましょう。
発言者とは別に記録係を用意しておくと、全体での議論に生かすこともできますね。また、時間制限を設けるなどのゲーム要素を加えてもおもしろいでしょう。
ピア・レスポンス
ピア・レスポンスとは、プレゼンテーションやレポートの準備段階においてアウトラインを共有することで、他者から感想や改善案を得る手法です。
–ピア・レスポンスのやり方–
- ペアまたはグループを作成し、発表者はアウトラインを共有する
- 聞き手はアウトラインの内容について感想や意見を述べてフィードバックを行う
- 発表者を交代し、メンバー全員が終わるまで繰り返す
- フィードバックを元に自分のプレゼンの改善を行う
ピア・レスポンスのポイントは、相手に伝わりやすいように端的に話すことが挙げられます。発表者と傍聴者のどちらも経験できるため、客観的な視点や多角的な表現力が身につきます。
マイクロ・ディベート
マイクロ・ディベートとは、3人1組のグループで「お題」に対して肯定・否定の立場から議論を行う手法です。
–マイクロ・ディベートのやり方–
- 「お題」について肯定・否定の立場から論拠を5つ以上考える
- 3人1組のグループを作り、肯定役・否定役・ジャッジ役の順に合計3回のディベートを行う
マイクロ・ディベートのポイントは、意見が対立する状況のなか、お互いが納得する結論を導き出せるかどうかです。ディベートを通じて課題解決力や論理的思考力を身につけ、業務で課題に直面した場合でも適切に対処できるようになることが、マイクロ・ディベートの狙いだといえるでしょう。
企業研修におけるアクティブラーニングの失敗例と対策

企業研修にアクティブラーニングを導入すれば、業務に必要な幅広い能力や社員同士の協調性を高めることが可能です。
一方で、企業研修におけるアクティブラーニングの代表的な失敗例として下記の2点が考えられます。
- 主体性の低い社員に対するフォローアップが弱い
- 研修の評価基準が曖昧になりやすい
アクティブラーニングは、受講者自身が主体的に取り組むことで成り立つ教育方法です。講義形式であればあまり問題ないのですが、能動的な参加が求められるアクティブラーニングでは、内向的な社員への配慮やフォローアップが必要です。
また、アクティブラーニングは社員の理解度や習得度を定量的に評価するのが難しい側面があります。事前に評価基準を設けておき、グループワークやプレゼンに対して適切な効果測定やフィードバックが行うようにしましょう。
アクティブラーニングを活用した企業研修

IKUSAでは、社員が積極的に参加できるような楽しい「体験型」の企業研修を提供しています。特徴は「学び」と「楽しさ」を両立できること。メンバー間の情報共有やコミュニケーションも自然に生まれるので、チームワーク向上効果が期待できます。
ここからは、IKUSAの企業研修の中から、社内のチームワーク向上や業務に必要な能力の修得に効果的なプランを紹介します。
リアル探偵チームビルディング
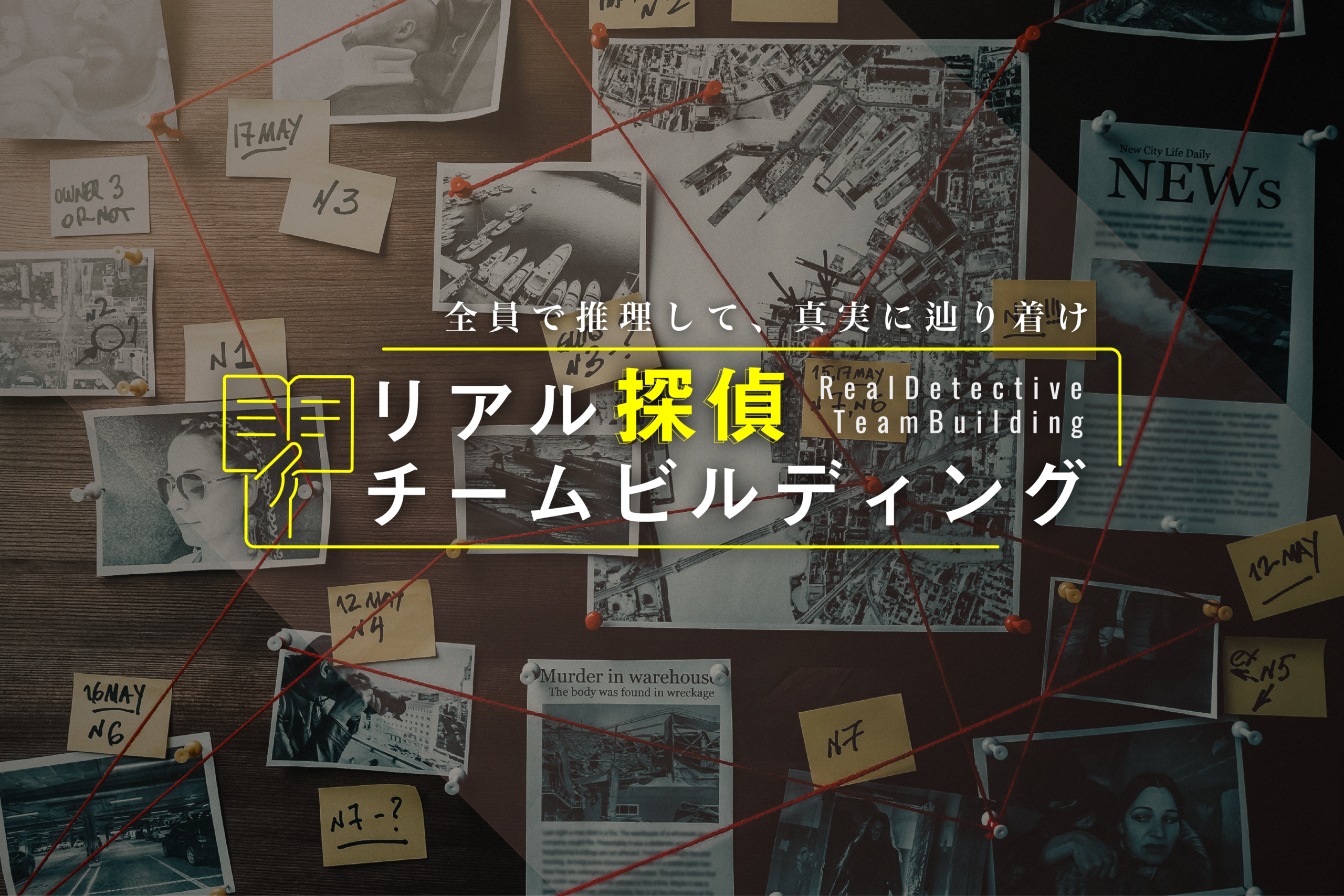 リアル探偵チームビルディングは、ジグソーメソッドを活用した推理ゲームです。仲間と協力をしながら推理を進めるなかで、コミュニケーション力や情報整理能力、論理的思考力を身につけることができます。
リアル探偵チームビルディングは、ジグソーメソッドを活用した推理ゲームです。仲間と協力をしながら推理を進めるなかで、コミュニケーション力や情報整理能力、論理的思考力を身につけることができます。
参加者は、はじめに4〜6名の「小グループ」内で、与えられた情報を確認・整理します。小グループはいくつかあり、それぞれのグループに別々の情報が与えられています。
小グループ内で情報を整理できたら、次は「大グループ」へと移動。それぞれが持つ情報を共有し、推理を進めていきます。
その後再び小グループにて各々が入手した情報を共有し、さらに推理を深め、最終的に大グループとして一つの答えを導き出します。
ゲームクリアのために最も重要なのは、協力すること。その名前の通り、高いチームビルディング効果が期待できる研修です。
また、リアル探偵チームビルディングのオンライン版として、「リモ探」もございます。リモートワークでのオンライン研修をお探しの方におすすめです。
リモ探
リモ探とは、ご紹介した通りリモートでもチームビルディングができる大人数参加型の推理ゲームです。
「リモ探」はこんな場面におすすめです
- 社内研修
- チームビルディングイベント
- 新入社員研修
リモ探は、アクティブラーニングの手法「ジグソー法」を活用したゲーム型研修です。参加者は少人数の「小グループ」と、いくつかの小グループから構成された「大グループ」を行き来しながら情報を整理・共有し、ミッションに取り組みます。
大人数でのコミュニケーションを取りたい、情報を整理する力や正しく伝える力を身につけたいといった場面におすすめの体験型研修です。
サバ研

サバ研とは、勝つためのフレームワークとして近年注目を浴びる「OODA LOOP」と「サバゲー」を組み合わせた日本初の体感型研修です。
︎「サバ研」はこんな場面におすすめです
- リーダーシップ研修
- チームビルディング研修
- 幹部・役員研修
サバ研では、「迅速な意思決定・臨機応変な対応・リーダー像」といった組織の成長に必要な能力を楽しく学べます。また、先行きが不透明な状況下でチームをまとめ上げ、道筋を生み出す思考回路を育むことが可能です。
普段の業務では体験できない状況をあえて作ることで、目的達成に向けて常に考え、チーム全員で動き続けるスキルを身につける。これがサバ研の醍醐味です。
OODAチャンバラ合戦
IKUSAが提供するOODAチャンバラ合戦は、勝つためのフレームワークであるOODA LOOPと、IKUSAの人気アクティビティであるチャンバラ合戦を融合した体験型研修です。
合戦は、敵チームの小判をより多く獲得したチームの勝利です。チームのメンバーにはそれぞれ役割が与えられ、勝利には役割を最大限活用できる戦略立案とチームワークが欠かせません。特に戦略立案をするうえで重要な考え方が、OODA LOOPです。
OODA LOOPとは、Observe(見る)、Orient(わかる)、Decide(決める)、Act(動く)という意思決定の4つのプロセスを高速で回す(LOOP)ことです。これにより、判断・意思決定を素早く行えるようになります。
OODA LOOPを講義から学んだら、このフレームワークを合戦内で活かすことで、学んだことがとても身につきやすい研修です。
楽しく実践的な研修を行いたい方におすすめのアクティブラーニング研修です。
合意形成研修 コンセンサスゲーム ONLINE
コンセンサスゲームとは、ある状況における物事の優先順位をつけていくゲーム。まずは個人個人で優先順位を考えたあと、チームで話し合いながら優先順位を決めていきます。
優先順位を決める内容としては、例えば「荷物の中で持っていく優先順位付け」が挙げられます。思考力が鍛えられれるうえに、比較的考えやすい低い設問であるため参加ハードルは低いといえるのではないでしょうか。
自分で選んだあとにチームで決めていく際には、「なぜ、それをその順番にしたのか」をチームメイトに説明する必要があります。思考力に加えて、論理力も鍛えられるでしょう。
他にもコミュニケーション能力やリーダーシップ、多様な価値観を知ることで得られる視野の広さも実施のメリットです。
所要時間は30分~1.5時間程度と、比較的カジュアルに導入できます。リモートワークが続いている会社のコミュニケーション機会作りとしてもおすすめです。
オンライン、リアル、どちらでも開催可能です。
⇒合意形成研修コンセンサスゲーム ONLINEの資料を無料で受け取る
リーダーシップ研修「グレートチーム」

「グレートチーム」は、IKUSA のリーダーシップ研修の中で行うビジネスゲームです。
チームに分かれて、「プロジェクト」をメンバーに「アサイン」したり、リーダーとしてさまざまな状況に決断を下す「リーダーズチョイス」を行ったりして、多くの報酬を稼ぐことを目指します。
ゲームの中でメンバーのリソース管理や育成、リーダーとしての決断を繰り返すことで、リーダーシップやマネジメントについて学び、いろいろなリーダーシップの型について知ることができます。
また、アクティビティの前後にはリーダーシップに関する講義も受けていただきます。そのため、座学だけ、アクティブラーニングだけの研修に比べて、より深い学びを得ることができるのも特徴です。
企業研修にアクティブラーニングを活用したいとお考えのあなたへ

本記事では、企業研修に最適なアクティブラーニングの手法を5つご紹介しました。どの手法も優秀な人材育成が期待できるので、ぜひ導入してみてはいかがでしょうか。
株式会社IKUSAでは、企業研修に関する相談や支援を承っております。体験型の企業研修イベントを通じて、社員間のチームワークを高め、より主体的に成長できるでしょう。
「あそぶ社員研修」は、受講者全員が没入して取り組むアクティビティ・振り返り・講義をブリッジすることで学びを最大化させ、翌日から業務で活かせる知識・スキルが身につく講義・アクティビティ一体型の研修プログラムです。
アクティビティが受講者の主体性を高めてコミュニケーションを促進させ、スキルアップやチームビルディングをはかれます。
メールアドレスのみで簡単10秒受取「研修の効果を高めるノウハウ集」
⇒無料で資料を受け取る

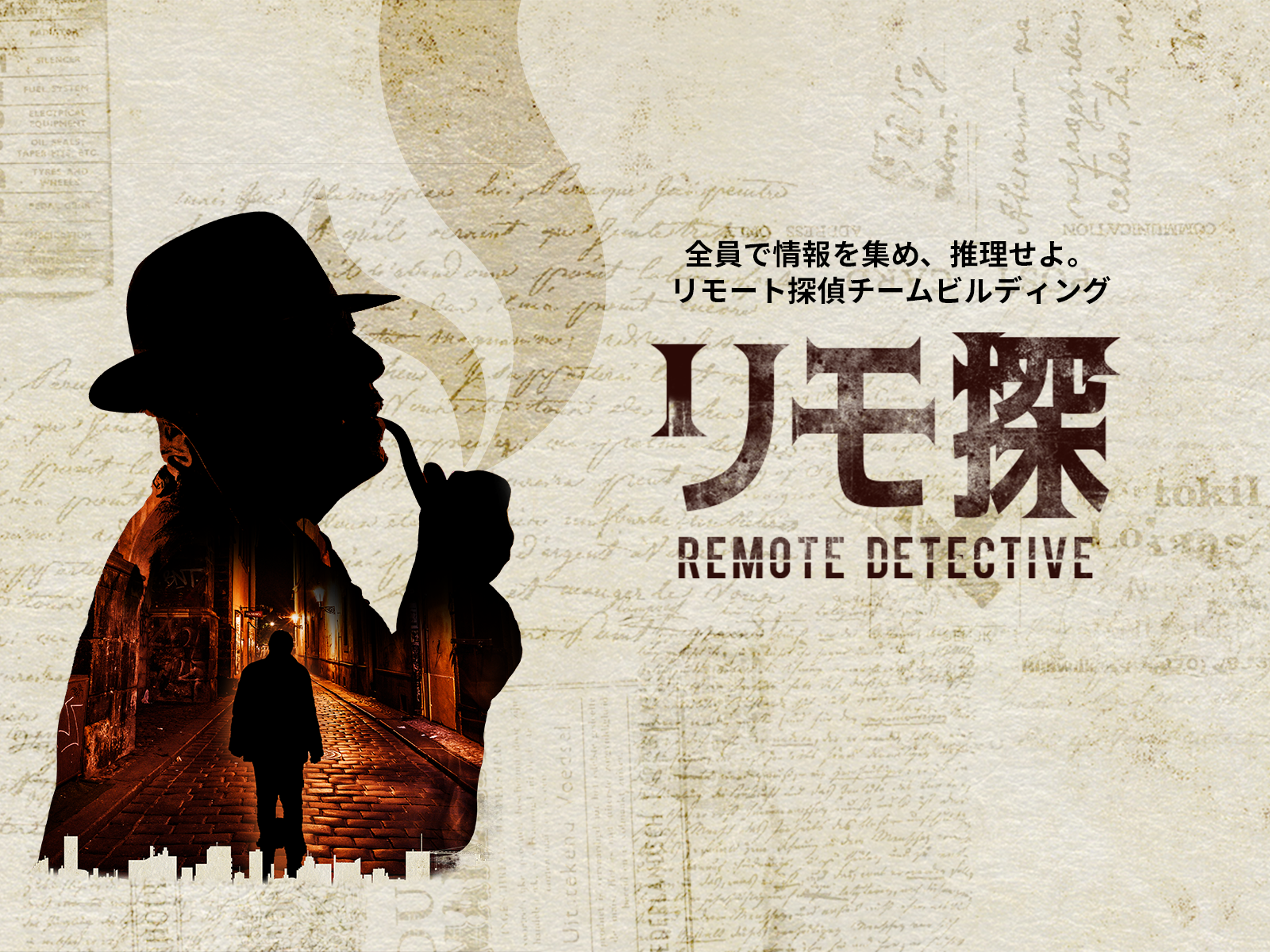



 赤坂大樹
赤坂大樹
 犬千代
犬千代
 ともしど
ともしど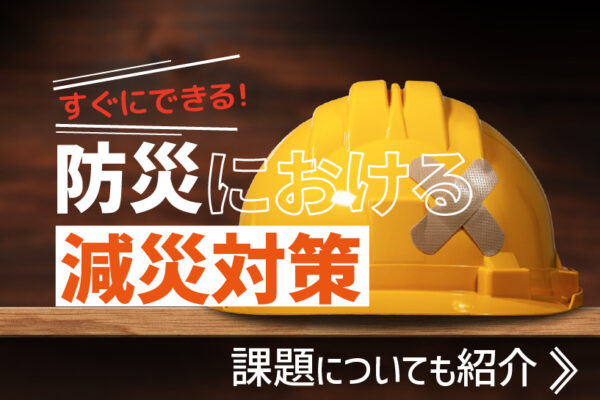
 IKUSA.jp編集部
IKUSA.jp編集部