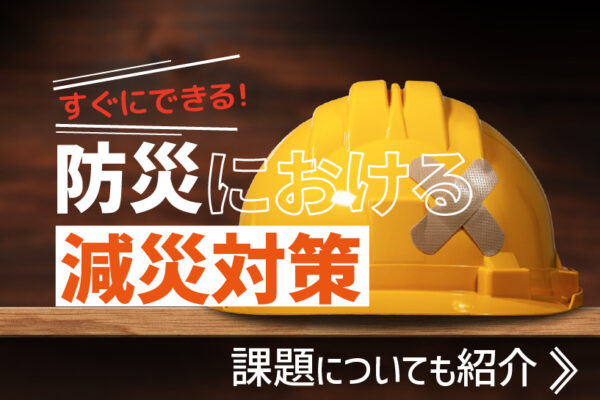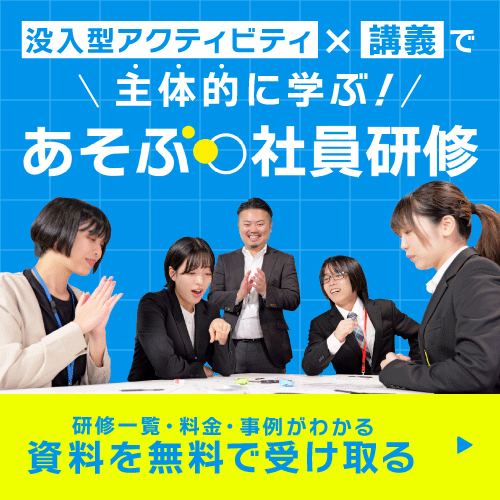updated: 2024
企業がアクティブラーニングを導入する際の課題と解決方法を解説

受講者が能動的に参加する学習方法、「アクティブラーニング」。教育現場だけではなく、企業でも社内研修に取り入れるところが増えてきています。
今回は、企業がアクティブラーニングにより得られるメリット、導入時に気をつけたい注意点について紹介します。
年間1000件以上のイベント・研修を支援。IKUSAのサービス総合カタログ【デジタル版】を無料配布中
⇒無料で資料を受け取る
社内レク、懇親会、運動会、研修などでチームビルディング!圧倒的に盛り上がる社内イベント・研修の事例集を無料配布中
⇒無料で資料を受け取る
アクティブラーニングとは

「アクティブラーニング」とは、受講者が能動的に参加する学習形態です。従来の授業は、先生が黒板前に立って板書をしながら説明し、時に生徒に発言させる形は、受け手となる生徒たちは説明を聞く、ノートに書くといったことに終始します。
一方アクティブラーニングは、一方向の授業だけではなく、少人数でのディスカッションやディベート、グループワークなどを取り入れ、受講者に自ら考え発言、行動することを促します。
社内研修やセミナーも、これまでは講師が登壇し、受講者である社員はその話を聞くといった一方向のスタイルが中心でした。しかし、社員に自分で考え動ける力を養うため、企業でもアクティブラーニングを社内研修に取り入れるところが増えてきているのです。
参考:アクティブラーニングとは?具体例や企業研修に導入するメリット・注意点を解説|あそぶ社員研修
企業でアクティブラーニングを導入するメリット

企業がアクティブラーニングを導入するメリットには、以下のものが挙げられます。
- 問題解決力向上
- 主体性向上
- 発想力・創造力向上
- コミュニケーション能力向上
- 人材育成(早期戦力化)
- 知識の定着率向上
- リーダーシップ育成
それぞれの詳しいメリットについて説明します。
問題解決力向上
正しい答えを教わる一方向のセミナーとは異なり、アクティブラーニングは課題の答えを自分たちで考え、導き出さなければなりません。論理的に考えて仮説を立て、検証するといった流れの中で、社員の問題解決力を磨きます。
主体性向上
従来型の受け身で聞いていればいい研修・セミナーとは異なり、アクティブラーニングでは受講者が主体性を持って研修に取り組まなければなりません。考えて意見を出し、話し合う経験は、社員の主体性を向上させるでしょう。
発想力・創造力向上
アクティブラーニングでは答えを出すことを求められます。しかし、答えには正解がない場合も多い点が特徴です。自分とは異なる価値観や考え方に触れる機会は、発想力や創造力を向上させる機会になるはずです。
人材育成(早期戦力化)
一般的な座学と比べ、アクティブラーニングは学習の効果をより高められます。新入社員研修にアクティブラーニングを取り入れることで、より早期の人材戦力化が可能となります。
知識の定着率向上
ただ話を聞いているだけでは、なかなか知識が頭に入っていかないものです。議論をしたり、自分の考えを発言したりする能動的な行動は、自分の脳を働かせる分、理解が深まりやすいとされています。座学と比べ、知識の定着率を上げられるでしょう。
リーダーシップ育成
グループで課題を解決するには、一人ひとりが自分の役割、今何をすべきかを考える必要があります。他人任せにしたままでは一向に議論が進まないため、おのずとリーダーシップが育まれるでしょう。
企業がアクティブラーニングを導入する際の課題・注意点と解決法

単純にアクティブラーニングを導入すれば、自動的に上記で紹介したメリットが得られるわけではありません。企業がアクティブラーニングによるメリットを得るためには、いくつかの注意点があります。ここでは、注意点と解決方法について紹介します。
目的が曖昧になっていないか
研修内容がいいものであっても、何のために実施するのか目的が明確化されていない状態では、アクティブラーニングの良さを発揮できません。受講してもらう社員に、アクティブラーニングに参加してもらい何を得てほしいのか、何のためにアクティブラーニングを導入するのかを、あらかじめ整理しておきましょう。
また、導入当初は目的が明確化されていたはずが、回を重ねるうちに「アクティブラーニングを実施すること」が目的化してしまうケースも見られます。同じアクティブラーニングをただ繰り返すのではなく、本来の目的が果たされているのかどうかを定期的に見直すことが必要です。
受講者全員にとって「アクティブ」な学習になっているか
アクティブラーニングにおける「アクティブ」とは、体だけではなく脳を動かすことを指します。そのため、そのアクティブラーニングにおいて、受講者全員が自ら考え、発言や行動に起こせていることが重要です。
数人でグループワークを行うと、役割分担が自然と行われ、結果的に「指示を聞いて動いているだけ」の受講者が出てきてしまうことがあります。グループワークを行う際は、一人ひとりに役割や責任を持たせ、個々が役目を果たすために自ら思考を働かせられるプログラムを組みましょう。
評価ができるようになっているか
アクティブラーニングは、営業成績のように単純に数字で評価を表しにくい特徴があります。とはいっても、受けてもらって終わりでは、アクティブラーニングを受けた意味があったのかどうかが受講生にも伝わりません。アクティブラーニングを導入する際は、前もって効果の測定基準や測定方法、フィードバック方法を整えておくといいでしょう。
教育現場でアクティブラーニングを導入する際は、よく「ルーブリック評価」が取り入れられています。ルーブリック評価とは、受講者(生徒・学生)の学習到達状況を評価するために用いられる評価基準です。いくつかの評価項目を設け、項目ごとにどこまで達成できているのかを可視化します。
こうした評価制度を取り入れることで、受講生にアクティブラーニングを受けたことで成長した度合いや、今後さらに伸ばしていったほうがいい部分について伝えられるでしょう。
講師のスキル面に問題はないか
最後の注意点は、講師のスキル面です。アクティブラーニングの講師には、自分の専門分野の知識だけではなく、コーチングスキルやファシリテーションスキルが求められます。
社内でアクティブラーニングを行う際、自社社員が講師を務めるパターンと外部に依頼するパターンとの2つが挙げられます。自社社員が講師を務める場合は、コーチングやファシリテーションについて別途トレーニングを行う機会を設け、意義のあるアクティブラーニングにできるように準備をしておくといいでしょう。外部に講師を依頼する場合も、専門知識だけではなく、アクティブラーニングコーチとして必要なスキルを有しているかどうかを判断して依頼することが大切です。
おすすめの研修サービス
サービスを提供している会社に外注すれば、アクティブラーニング研修を簡単に実施できます。ここでは、株式会社IKUSAの提供するサービスを3つご紹介します。
OODAチャンバラ合戦
IKUSAが提供するOODAチャンバラ合戦は、勝つためのフレームワークであるOODA LOOPと、チャンバラ合戦を融合した体験型研修です。
OODA LOOPとは、Observe(見る)、Orient(わかる)、Decide(決める)、Act(動く)という意思決定の4つのプロセスを高速で回す(LOOP)ことです。これにより、判断・意思決定を素早く行えるようになります。
OODA LOOPを講義で学び、それを作戦の立案に活用、チャンバラ合戦で体を動かしながらOODA LOOPを繰り返し実践し、振り返りを行うことで定着させます。
楽しく実践的に研修を行いたい方におすすめのアクティブラーニング研修です。
合意形成研修 コンセンサスゲーム ONLINE
コンセンサスゲームとは、参加者同士でコンセンサスを得る(合意形成)ことで、与えられたテーマ課題の解答を導き出すゲームです。コンセンサスゲームでは、ジャングルや宇宙などを舞台としたストーリーの中で、グループで所有しているアイテムに優先順位をつけ、グループ全員からのコンセンサスを得ることで、危機的状況から脱出することを目的としています。
コンセンサスを得ることはとても重要なことですが、簡単では決してありません。ゲーム内で合意形成達成を経験することで、その後もスムーズに合意に至ることができるようになるでしょう。
IKUSAが提供する合意形成研修 コンセンサスゲームは、対面とオンラインのどちらでも実施可能です。
⇒合意形成研修コンセンサスゲーム ONLINEの資料を無料で受け取る
リアル探偵チームビルディング
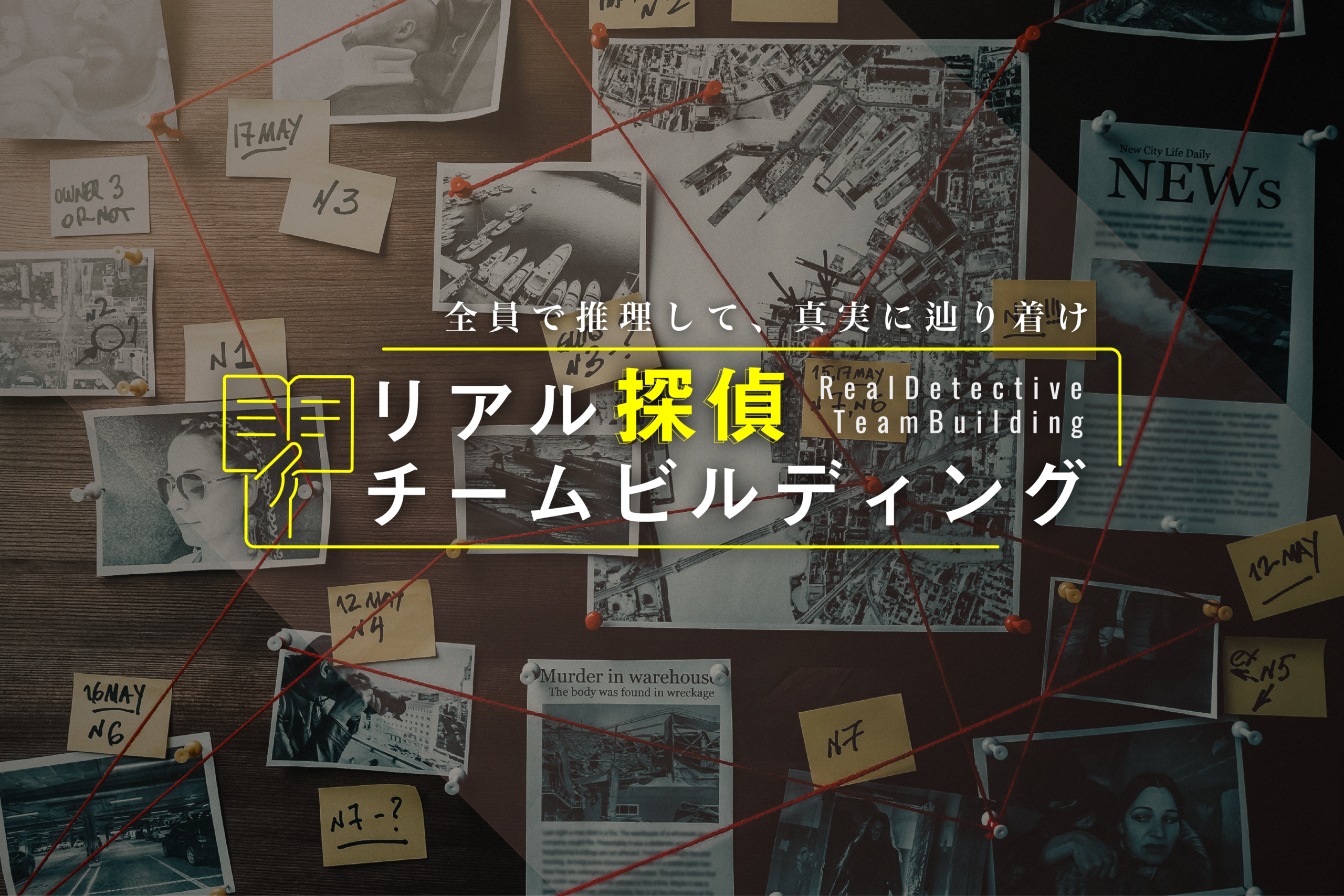 リアル探偵チームビルディングは、ジグソーメソッドを活用した推理ゲームです。仲間と協力をしながら推理を進めるなかで、コミュニケーション力や情報整理能力、論理的思考力を身につけることができます。
リアル探偵チームビルディングは、ジグソーメソッドを活用した推理ゲームです。仲間と協力をしながら推理を進めるなかで、コミュニケーション力や情報整理能力、論理的思考力を身につけることができます。
参加者は、はじめに4〜6名の「小グループ」内で、与えられた情報を確認・整理します。小グループはいくつかあり、それぞれのグループに別々の情報が与えられています。次は「小グループ」がいくつか集まった「大グループ」へと移動。それぞれが持つ情報を共有し、推理します。この過程を繰り返し、ゲームクリアを目指します。
ゲームをクリアするには参加者同士の協力が必要不可欠。アクティブラーニング研修をお探しの方に、ぜひおすすめしたい内容となっています。
また、リアル探偵チームビルディングのオンライン版として、「リモ探」もございます。リモートワークでのオンライン研修をお探しの方におすすめです。
まとめ

AIの誕生に伴い、人間が働く上でより重要なのは、自ら考え、答えのない問いに自分なりの答えを見出して動けることであるといえます。社員がそういったスキルを身につけるためにも、アクティブラーニングは有効です。
しかし、今回ご紹介してきたように、ただやみくもにアクティブラーニングを導入しておけばいいわけではありません。どういった目的があり、目的を達成するためにはどのようなプログラムを組んだらいいのかを考え、意味のあるアクティブラーニング導入を目指しましょう。
IKUSAでは、年間1000件以上のユニークなイベントや研修を支援しています。90種類以上のイベント・研修サービスからお客様のニーズに合わせてご提案させていただき、ご要望に応じたカスタマイズも可能です。サービスの詳細や具体的な事例は下記の資料でご確認ください。
⇒無料でサービス総合カタログ【デジタル版】を受け取る
アクティブラーニングを活用した研修としておすすめなのがオンラインでできるゲーム型研修「リモ探」です。
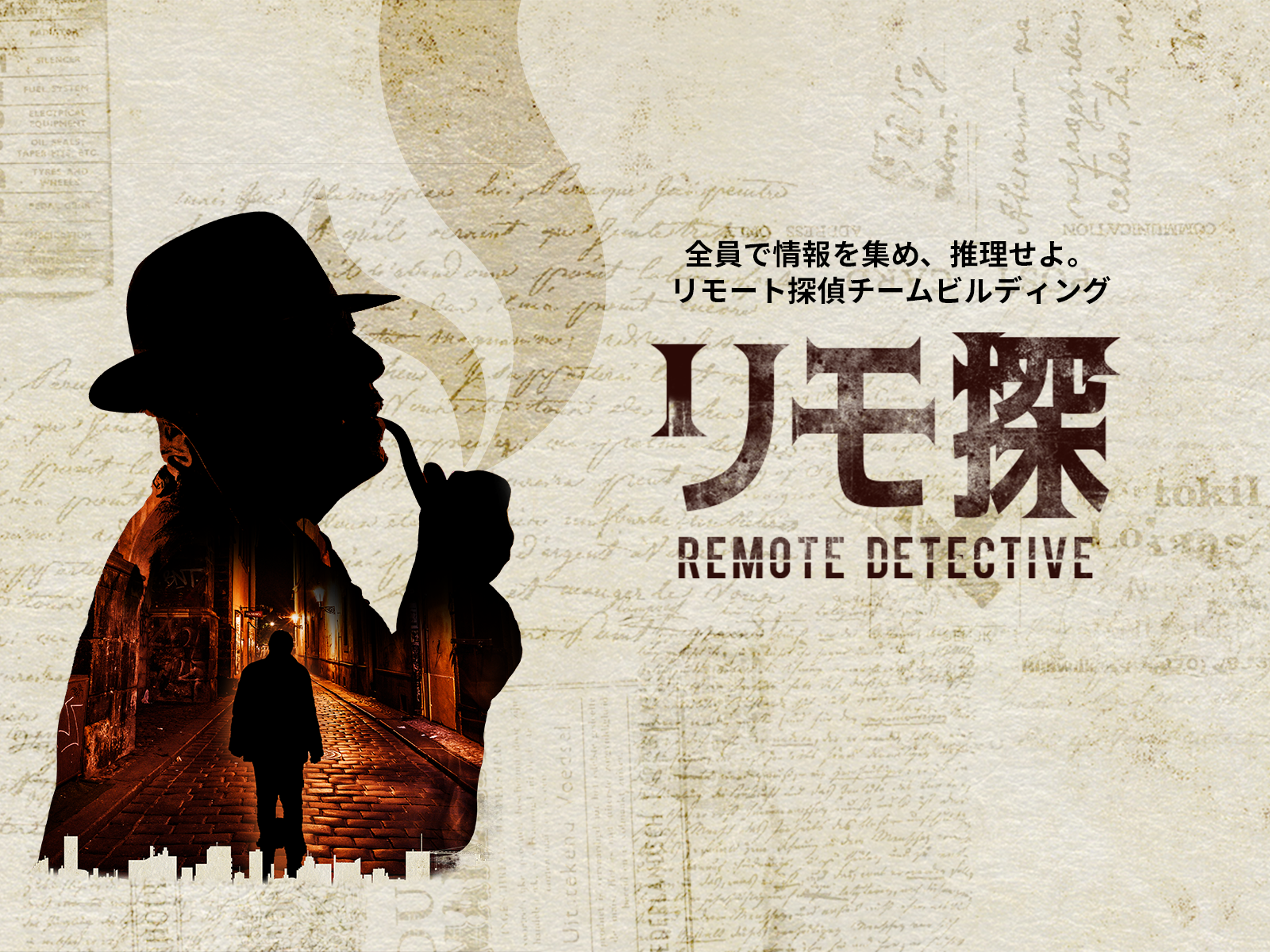
リモ探は、他者と情報を共有し合うことで答えを導き出すアクティブラーニングの手法「ジグソー法」を活用した研修です。
参加者は情報を整理・共有しながら、全員の力で真実に辿り着くために推理を行います。
ゲームは制限時間内に解決すべき「あるミッション」が発生するところからスタート。
参加者は大グループの中でさらに小グループに分かれ、各小グループはそれぞれ異なる情報が与えられます。小グループの中で情報を分析し、大グループに共有することを繰り返ししながら、全員でミッションクリアを目指します。
それぞれが持つ情報を積極的に共有し、情報をうまく整理していく必要があるので、参加者の主体性やコミュニケーション能力が問われるゲーム型研修といえます。
参考サイト:




 IKUSA.jp編集部
IKUSA.jp編集部
 ともしど
ともしど
 正木友実子
正木友実子