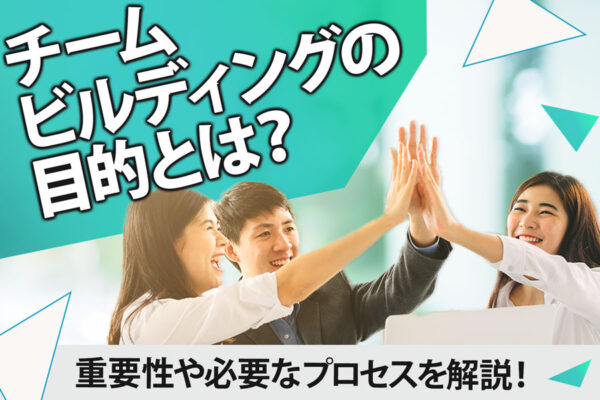updated: 2026
研修で使えるビジネスゲーム23選!メリット・やり方も紹介

組織の連帯感や生産性をあげるために研修を実施しているものの、効果が見えない…と感じる企業は多数あり、研修は企業の人材育成における課題の一つです。研修を行っても同じようなテーマで参加率が上がらない、参加者のモチベーションが上がらない、伝えたいことが定着しない、そんな悩みはないでしょうか。
ありきたりな研修ではなく、短時間でも効果が上がる新しい研修として「ビジネスゲーム」が注目されています。ゲームの形式で実際にいろいろな場面を体験することで、組織で求められる考え方や役割を学ぶことができます。
本記事では、ビジネスゲームのメリットの解説とともに、短時間でもできるおすすめのビジネスゲーム23選を紹介します。ビジネスゲームの種類は、屋内外問わずできるものや、身体を動かして学ぶもの、頭を働かせるものなどさまざまです。
オンラインでも、一体感はつくれます。
コロナ禍で年間1000件以上のノウハウと実績が保証。満足度にこだわったオンラインイベントを豊富な実績からご提案!
⇒企業向けオンライン謎解きの決定版!「リモ謎」の資料を見る
⇒ ハイブリッド開催もOK!まずは相談してみる
ビジネスゲームとは
 ビジネスゲームとは、ビジネス上も求められる考え方やスキルなどを直接的・間接的に疑似体験で学べるシミュレーションゲームです。ゲーム形式で行うため座学で知識として得るより感覚的に身に付けることができ、多くのメリットがあります。ビジネスゲームを用いた研修はビジネスゲーム研修と呼ばれ、近年多くの企業でも取り入れられるようになりました。
ビジネスゲームとは、ビジネス上も求められる考え方やスキルなどを直接的・間接的に疑似体験で学べるシミュレーションゲームです。ゲーム形式で行うため座学で知識として得るより感覚的に身に付けることができ、多くのメリットがあります。ビジネスゲームを用いた研修はビジネスゲーム研修と呼ばれ、近年多くの企業でも取り入れられるようになりました。
失敗しないオンラインイベント・ハイブリッドイベントのアイデアが見つかる!
⇒【無料ダウンロード】企業向けイベント事例集を見てみる
ビジネスゲームを研修で取り組む8つのメリット
組織が求めるスキルを伝えられる
一致団結して事業を進めることができるようにするためには、企業の経営理念や求める役割や考え方、スキルなどを社員に浸透させる必要があります。ゲーム形式とはいえ、社員に何を学んでもらいたいのか、これからの社員に何が必要なのかを吟味して、必要性・合理性のあるビジネスゲームを選ぶことで、企業の意図を浸透させることができます。
主体的思考が身につく
座学だけでは自分で主体的に考える必要がなく、受け身になることが考えられますが、ゲーム形式であれば、勝つためにはどんな行動に出るべきか主体的に考えることが必要になります。ビジネスパーソンとしては、組織にどんな貢献ができるか主体的に考え、行動ができる人材を育成することに繋がります。
課題発見能力が養える
ゲームに勝つという目的に対し、障壁になるものを見つけるという課題発見能力は、ビジネスにおいても必要なスキルです。座学で聞くだけでは知識として得るだけに留まる一方、シミュレーションで学ぶからこそ課題発見のスキルが身に付きます。
リーダーシップが身につく
数人のチームでゲームに挑む場合、意見を出し合うことはもちろん大事ですが、意見を取りまとめ、議論を活性化させ、結論を出して行動に移す、という各フェーズでリーダーが必要になります。誰もがその立場に立てばリーダーが務められるよう、状況把握能力や判断力といったスキルを養う必要があります。
判断力が向上する
ビジネスゲームではロールプレイング型でシチュエーションを疑似体験することができ、チームが成功を収めるためには差し迫った判断が必要なシーンもあります。組織全体のためには何を優先すべきか、といったビジネスパーソンとして必要な総合的な判断力を養うことができます。
コミュニケーションが活性化する
座学での研修に比べ、ビジネスゲームではチームで行うものが多いため、メンバー同士の交流は自然と促進されるでしょう。普段は交流のない部署や役職のメンバーが混ざっていると、始めは堅い雰囲気だとしてもコミュニケーションを取り協力せざるを得ないため、自然と会話をすることになります。座学より楽しい雰囲気であることからも、コミュニケーションが活発になるでしょう。
楽しみながら学べる
座学の講義で学ぶことも必要ですが、ビジネスゲームのメリットは、楽しみながらビジネスに必要なスキルを学べるということです。楽しい時間を共有することで仲が深まり、社員全体でのスキルアップが期待できます。
失敗からも学べる
現実のビジネスでは、失敗から学ぶこともたくさんあります。ビジネスゲームは疑似体験からビジネススキルを学び、ゲームが終わるたびに即時フィードバックを行うので、短い時間でゲームを繰り返しながら反復学習ができます。ゲームだからこそ、安心して失敗することができ、失敗から学びを得られることがビジネスゲームの良さだと言えるでしょう。
研修で使えるビジネスゲーム23選
チャンバラ合戦

チャンバラ合戦は、スポンジの刀で相手の腕についたボールを切り落とすというシンプルなルールで楽しむアクティビティです。しかしただ戦うのではなく、相手チームに勝つための「戦略」を練ることが大切なので、ビジネスゲームとしてもおすすめです。
勝つために作戦会議である「軍議」を行ない、合戦を通して実践し、また軍議で振り返り、作戦を立て直すという流れになっています。まさに合戦を通してPDCAサイクルが学べるのです。身体を動かすことで参加意欲を高め、軍議を通してチームディルディングも学ぶことができるのがチャンバラ合戦の特徴です。
合戦内容はチームを全滅させる「全滅戦」、チーム内に大将をつくり大将を討ち取る「大将戦」、会社内一の剣豪を決める個人戦の「バトルロイヤル戦」とさまざまです。PDCAサイクルを即効で体感できるチャンバラ合戦には、より研修に特化した「体験型合戦研修IKUSA」プランも提供しています。体験型合戦研修IKUSAの開催事例はこちらをご覧ください。
【開催事例】「城攻め」某アパレル企業様
パズル
パズルは、バラバラのピースを合わせていき、一つの絵に仕上げるあそびです。あそびといっても、みんなで協力して仕上げる中で、さまざまな学びが得られます。どの部分から組み立てていけばいいのか、みんなで取り組むにはどうやって取り組めば効率的かなどを考えなくてはいけません。
その計画性は仕事をする上でも必要なスキルです。効率を考え、計画性のある行動をとることは、稼働率や生産性に影響を与えます。パズルはそういった部分でのスキルアップが期待されます。パズルのピース数は、参加人数に合わせたり難易度を上げてみたり、参加者に応じて考慮するようにしましょう。
-パズルのやり方-
- パズルを用意する
- チームで協力してパズルを完成させる
アゲアゲ・ブレインストーミング
 ブレインストーミングとは、他人同士の頭脳(Brain)を嵐(Storm)のようにかき混ぜるという意味のアイデア発想法のことです。
ブレインストーミングとは、他人同士の頭脳(Brain)を嵐(Storm)のようにかき混ぜるという意味のアイデア発想法のことです。
アゲアゲ・ブレインストーミングは、まずチームでプレインストーミングのテーマを決めます。そして1人がアイデアを出すのですが、他の参加者は決して出された意見を否定してはいけません。「いいね!それなら…」と続く形で自分のアイデアを語ります。否定せずにアゲ続けることで途方もないアイデアへとさせ発展させていくことができます。主体性や創造力、傾聴力などが身につくビジネスゲームです。
-アゲアゲ・ブレインストーミングのやり方-
- チームでブレインストーミングのテーマを決める
- 1人がアイデアを出し、他の参加者は否定せずにさらに自分のアイデアを出していく
ビズストーム
ビズストームとは、ビジネスに必要な要素を疑似体験することができ、実践につなげられるボードゲーム型のビジネスゲームです。ゲーム参加者一人ひとりがそれぞれ会社を経営し、魅力ある商品をつくって広告営業などをしながら商品販売を行います。経営者となって経営における疑似体験をすることで、ビジネスの全体像を学べるゲームです。視座を高めることができるビジネスゲームとして、多方面の研修で活用されています。
参照:BIZSTORM~経営センスを鍛えるビジネスゲーム研修、ビズストーム~
謎解き脱出ゲーム

謎解き脱出ゲームとは、参加者自身が物語の主人公になり、決められた時間や空間の中で与えられた謎を解いて物語のクリアを目指すあそびです。
今人気の謎解き脱出ゲームは、緊張感のある空間からチームで力を合わせて脱出を図るシチュエーションが特徴です。屋内型で広いスペースと体力が必要ないチームビルディングとして活用いただけます。今流行の謎解き脱出を試してみてはいかがでしょうか?
健康チェックカードー心技体ー
健康チェックカードー心技体ーは、50枚からなるカード化された設問に答えることで、参加者一人ひとりの健康状態を数字にして測定し、改善していくカードゲームです。最近は新型コロナウイルス感染症の影響で、体調面や精神面に不安を抱えていた方も少なくないでしょう。
また、知らず知らずのうちに、不安とストレスばかりが募り、疲れに鈍感になってしまっている方はいませんか? ビジネスゲーム健康チェックカード−心技体−は、自身の心身の健康状態を数値で見える化にしたことで、無意識に溜まっていた疲れやストレスに気づくことができます。見える化したことで自分の身体の状態を知り、自身の生活を見直すきっかけになるでしょう。
参照:健康チェックカード−心技体− – 健康経営のSUDACHI
ビブリオバトル
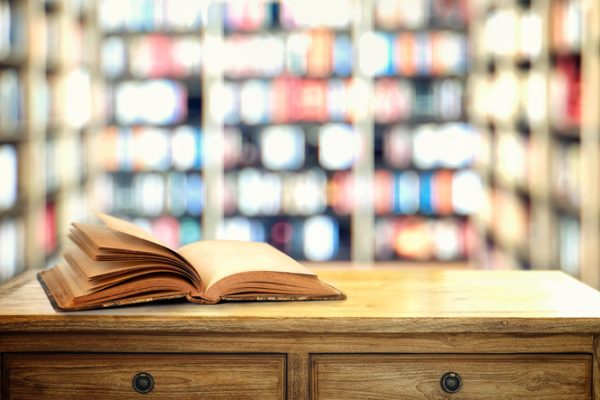 ビブリオバトルとは、簡単にいうと本を中心とした勉強会です。「ビブリオ」は古代ギリシア語で本のことを示しています。
ビブリオバトルとは、簡単にいうと本を中心とした勉強会です。「ビブリオ」は古代ギリシア語で本のことを示しています。
参加者が読んで面白いと思った本を持って集まり、順番に1人5分間で本をプレゼンします。それぞれの発表の後に参加者全員でその発表に関するディスカッションを行います。すべての発表が終了した後に1番読みたくなった本に投票し、最多票を集めたものが『チャンプ本』です。
発表する際のプレゼン力は今後のコミュニケーション力や、営業のトークスキルにもつながります。
-ビブリオバトルのやり方-
- 参加者が読んで面白いと思った本を持って集まる
- 順番に1人5分間で本をプレゼンする
- それぞれの発表の後に参加者全員でその発表に関するディスカッションを行う
- すべての発表が終了した後に1番読みたくなった本に投票し、最多票を集めたものが『チャンプ本』になる
防災運動会

「防災運動会」は、体を動かしながら楽しく防災知識や災害時の知恵を学べる運動会です。災害を5つのフェーズに分割し、「事前/災害発生/発災直後/避難生活/生活再建」とそれぞれのフェーズに応じた競技を体験することができます。
災害時は社員の安全ももちろん大事ですが、自分が助かること=自助とともに重要になるのが周りの人同士で助け合うこと=「共助」の考え方。社員にもその考えを浸透させたいと考える場合は、このアクティビティがおすすめです。
人狼ゲーム
人狼ゲームは、それぞれの役割を決めて、会話しながら相手の心理を読み取るゲームです。
人狼とは、村人になりすました狼のことで、人狼は村人を一晩ごとに一人襲撃します。村人は力をあわせて人狼を追放しなくてはいけません。村人役は誰が人狼かを推理し、人狼役は自分が人狼だと気づかれないよう振る舞う必要があります。すべての人狼を追放すれば勝利です。一方、人狼チームは自分の正体を見破られないようにしながら、すべての村人を襲撃することができれば勝利となります。
このゲームは会話が何より大切です。コミュニケーション力や観察力も身につくだけでなく、交渉術や戦略などを考える練習にもなるでしょう。
-人狼ゲームのやり方-
- それぞれ村人チームと人狼チームの役割のカードを渡される
- 人狼は一晩ごとに村人を一人襲撃する
- 村人チームは人狼チーム全員を追放すれば勝利
- 人狼チームは自分の正体を見破られないまま村人をすべて襲撃すれば勝利
サバ研

サバ研とは、サバイバルゲームでOODA LOOP(ウーダループ)を学べる研修です。サバイバルゲームとはエアーソフトBBガンを利用して行う日本発祥のスポーツです。通常は2チームに分かれて行うことが多く、主なゲームは殲滅戦やフラッグ戦などがあります。この研修を体感していただくことで新規事業の立ち上げを確度と高めたり、事業速度加速させたりするだけではなく、未曽有の事態が発生した際や先行きが不透明ななか、あらゆる局面で意思決定して進めていくことが可能です。
「OODA LOOP」とは米空軍出身のジョンボイド大佐が自身の戦闘を元に、五輪の書などから学びを加え提唱した勝つためのフレームワーク。迅速かつ柔軟な意思決定の流れをみる(Observe)、わかる(Orient)、きめる(Decide)、うごく(Act)という4つのプロセスごとに分けています。
また、4つのプロセスは瞬間的に完結するものなので、これらを何度も何度も高速で回転(LOOP)させることにより、時間をかけずに最適な判断を下すことが可能となっています。現在では全世界のスタートアップや軍隊、スポーツなどあらゆる場面でOODA LOOPが取り入れられ、活用されています。より早く問題を突破していくことが可能なOODA LOOPを学ぶだけではなく、体感していただくことができる研修です。
OODAチャンバラ合戦

勝つためのフレームワークとして近年注目を浴びる「OODA LOOP」とチャンバラ合戦を組み合わせた、OODAチャンバラ合戦もビジネスゲームに最適です。迅速な状況把握から柔軟に次の行動をとる、状況が変わればその変化に対応して行動する、というものです。
OODAチャンバラ合戦では軍のメンバーそれぞれに役割を振り当て、個々が主体的に迅速に動くことが原則。役割の重要性や指示の在り方などを身に付けることができます。
流れ星ゲーム
 流れ星ゲームとは、チーム内の参加者に「流れ星の絵を1分間で描いてみてください」とお題を出し、参加者はそれぞれに指定した絵を自身のイメージで描いてもらうゲームです。
流れ星ゲームとは、チーム内の参加者に「流れ星の絵を1分間で描いてみてください」とお題を出し、参加者はそれぞれに指定した絵を自身のイメージで描いてもらうゲームです。
できるだけメンバー全員の絵が同じような絵になるのが目標となるので、自分の表現だけでなく、他者に合わせようと考えることも必要となります。太陽や犬、花など、さまざまなお題で行いましょう。単純なゲームですがお互いのイメージを揃えるために相手に合わせようとする協調性や思考力が養われます。
-流れ星ゲームのやり方-
- チーム内の参加者に「流れ星の絵を1分間で描いてみてください」とお題を出す
- 参加者はそれぞれに指定した絵を自身のイメージで描く
- 最後にチームで描いた絵を見せ合う
情報伝達ゲーム
情報伝達ゲームは、リーダーだけがある絵を見て、その絵をチーム内の参加者に口頭で伝えて絵を描いてもらうゲームです。表情から読み取られないように、伝える時には目を瞑って伝えなくてはいけません。チーム内の参加者はリーダーに質問することができるので、ここでのヒアリング力が重要になります。
全員がリーダー役を体験するなかで、自分の目で見た情報を言語化する難しさを感じることでしょう。ゲーム内では、コミュニケーションを取ることが必要不可欠になるので、自然とコミュニケーションを図れます。また、伝える力や聞きだす力を身につけられるゲームです。
-情報伝達ゲームのやり方-
- チーム内でリーダーを決める
- リーダーだけがある絵を見る
- 絵をチーム内の参加者に口頭で伝えて絵を描いてもらう
戦国宝探し
戦国宝探しは、宝の地図を読み解き、実際に隠された宝箱を探す、チームビルディング要素の強い周遊型のゲームです。またオリジナルのシナリオも作成可能なので、会社の歴史と組み合わせることで、貴社ならではのオリジナリティ溢れる企画も実施することができます。
宝の地図を手に入れ、地図に描かれている謎を解き、推理した場所へと実際に向かいます。謎が難しければヒント店を回ったり、案内看板を見たり、施設マップを手に入れたりして謎を解いて、宝箱を見つけ出して合言葉を探し出さなくてはいけません。チーム内で推理することで話し合いが必要なので、チームビルディングやコミュニケーションの活性化、協調性や論理的思考などを学ぶことができます。
部課長ゲーム
部課長ゲームは、チームで協力して制限時間内にクリア条件を満たすゲームです。チームメンバーには部長・課長・平社員のいずれかの役割が与えられており、クリア条件は部長役のみが知っています。部長は課長や平社員もクリア条件を知っていると勘違いしたまま指示を出します。
しかし、クリア条件を知らない他の課長や平社員は何をすれば良いのか、なぜそのような指示を出されるのかよくわからないままプレイします。ゲームを通して、仕事の目的を共有すること、目的を理解して仕事に取り組むことの目的共有の重要性を学べるゲームとなっています。
-部長課長ゲームのやり方-
- チームメンバーには部長・課長・平社員のいずれかの役割が与えられる
- クリア条件は部長役のみが知っている
- 制限時間内に全員でクリア条件を満たす
ペア探しゲーム
ペア探しゲームは、他者との会話や質問を通して、ペアを探し出すゲームです。
たとえば自分に割り当てられた言葉が「イヤフォン」ならば、「ものですか?」「何をするために使うものですか?」などと質問をして絞り込んでいきます。質問を繰り返していくなかで、自身と同じ言葉の人を探し出せたらペア発見となります。質問の仕方でペア発見が遅くなることもあり、質問の仕方を工夫するスキルが身につくことでしょう。
-ペア探しゲームのやり方-
- 参加者はそれぞれ単語が割り当てられる
- 相手に「ものですか?」「何をするために使うものですか?」などと質問をして絞り込んでいく
- 同じ言葉の人を探し出せたら成功
ストロータワー
 ストロータワーはその名の通り、ストローを使ってタワーを作るゲームです。ストローハサミを使って、制限時間内にストローで1番高いタワーを建てられたチームが勝ちとなります。
ストロータワーはその名の通り、ストローを使ってタワーを作るゲームです。ストローハサミを使って、制限時間内にストローで1番高いタワーを建てられたチームが勝ちとなります。
考えなく作っていくのではなく、始まる前には作戦タイムの時間が設けられています。そのため、チーム内でコミュニケーションを図りながら、役割分担や戦略を練ることが可能です。シンプルながらも、集中力が身につき、協調性が学べるゲームです。
-ストロータワーのやり方-
- チームごとにストローが配布される
- 作戦タイムで戦略を練る
- 制限時間内にもっとも高いタワーを作ったチームが勝ち
リーダーシップ研修「グレートチーム」
 「グレートチーム」は、IKUSAがリーダーシップ研修のために作成したビジネスゲームです。参加者は、リーダーとしての立場を擬似体験し、「プロジェクト」のアサインや「リーダーズチョイス」を行って高い売上を目指します。
「グレートチーム」は、IKUSAがリーダーシップ研修のために作成したビジネスゲームです。参加者は、リーダーとしての立場を擬似体験し、「プロジェクト」のアサインや「リーダーズチョイス」を行って高い売上を目指します。
ゲームの中でメンバーのリソース管理や育成、リーダーとしての決断を繰り返すことで、楽しみながらリーダーシップやマネジメント能力を身につけ、また、いろいろなリーダーシップの型を知ることができます。
アクティビティの前後にはリーダーシップに関する講義もあるため、座学だけ、あるいはアクティビティだけの研修に比べて、より深い学びを得ることができるのも特徴です。
SDGsビジネスゲーム「ワールドリーダーズ」
 ワールドリーダーズは、企業経営の擬似体験をチームで行うビジネスゲームです。一チーム、一企業として企業の利益をどれだけ上げられるかを競います。
ワールドリーダーズは、企業経営の擬似体験をチームで行うビジネスゲームです。一チーム、一企業として企業の利益をどれだけ上げられるかを競います。
利益は、労働力と資本を使って上げることが可能です。ただし、このゲームは、ただ利益を上げるだけでは勝利できず、勝利のためには環境や社会など、様々なことを考慮して企業の価値を高める必要があります。本ゲームでは、SDGsにおける企業の役割だけでなく、戦略を立てる方法や、駆け引き、チームビルディングについても学ぶことができます。
オンラインSDGs謎解き「ある惑星からのSOS」
「ある惑星からのSOS」はオンラインで楽しめる、SDGsと謎解きを掛け合わせたイベントです。 参加者の皆さんは「ある惑星」の課題を解決するというミッションを与えられます。 謎を解いて情報を情報を整理することで、惑星の課題を解決する方法を導き出すことができます。 チームでゲームを進めるなかで、知らず知らずのうちに、今世界で起きている問題や、SDGsの必要性を学ぶことができます。
また、これらのビジネスゲームと一緒にフレームワーク「SDGsマッピング」を実施することで、より学びを深めることができます。
SDGsマッピングは、自社の取り組みとSDGsを結びつけるワークショップです。 SDGsの目標を構造化して示した「ウェディングケーキモデル」に自社の取り組みを分類し、自社とSDGsのつながりを見つけます。 IKUSAのSDGsマッピングは、SDGsボードゲーム「ワールドリーダーズ」もしくはオンラインSDGs謎解き「ある惑星からのSOS」とセットで実施します。ゲームとワークショップをセットで行うことで、ゲームでの体験をより深い学びに落とし込むことができます。
また、ワークに入る前に、SDGsの基礎的な内容について解説を行うため、SDGsの知識があまりない方でも気軽に取り組めます。 SDGsマッピングを行い自社とSDGsのつながりを感じることで、SDGsを身近なものとしてとらえ、自分ごと化することができます。
SDGsマッピング|SDGsの社内浸透を推進するワークショップ | IKUSA.JP
リモ謎

リモ謎は、リモートで実施できる謎解き脱出ゲームです。株式会社IKUSAが提供しているオンラインアクティビティで、チームビルディングにおすすめのゲームでもあります。対面形式での実施も可能です。
リモ謎の特徴は、チームでの協力が必要不可欠な点。「電脳世界」という異世界空間を舞台にした謎解きゲームを通して、必然的にコミュニケーションの活性化につながるのが魅力です。非言語コミュニケーション(表情やジェスチャーなど)も取り入れる必要があり、あらゆるコミュニケーションの基礎を身につけられるでしょう。
リモ謎は、コミュニケーションの講義・ワークとセットで研修として実施することもできます(対面形式・オンライン形式)。
リモ探
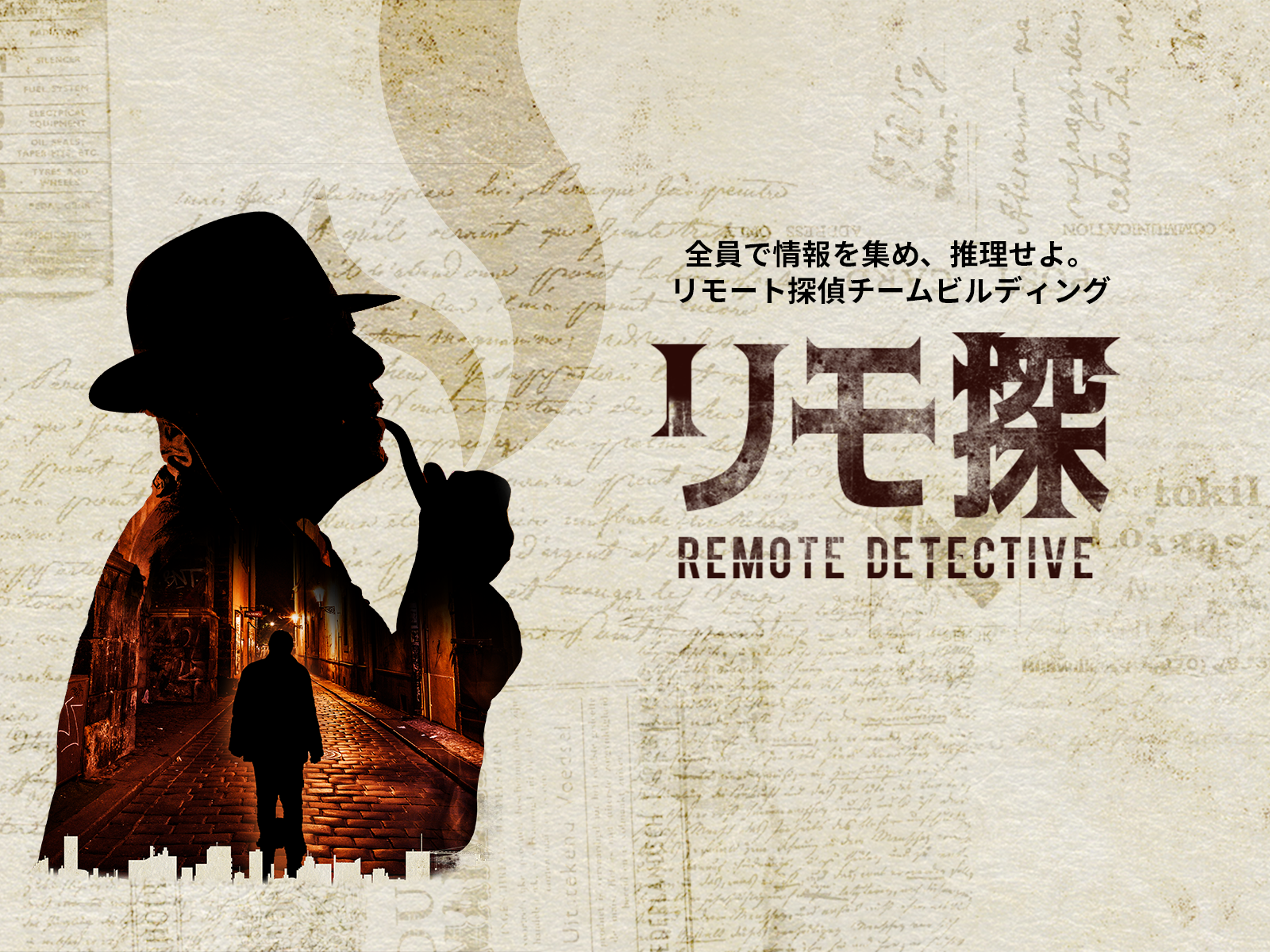
「リモ探」は与えられた情報を整理・共有して、全員の力で真実に辿り着くことを目的としたグループワークです。
アメリカの社会心理学者が提唱した「ジグソー法」を元に開発されました。ジグゾー法は参加者同士の協力や教え合いを促進し、学びを得ることができるとされる方法で、問題発見能力などを培うのに良いとされるアクティブラーニングを体験できます。
リモ探は、ロジカルシンキングの講義・ワークとセットで研修として実施することもできます(対面形式・オンライン形式)。
コンセンサスゲーム
コンセンサスゲームは、物語を通してチーム内で合意を形成について学べるプログラムです。危機的な状況において、自分の考えや他人との価値観の違いを認め合い、組織の目的のために最適な考えを議論しながら一つの結論を出す、というプロセスを実際に体験することができます。
実際のビジネスにおいても必要な、相手の意見を聞く力、自分の意見を言語化する力、論理的思考やチームワークを養うことができ、ビジネスゲームや研修前のアイスブレイクとしても効果的でしょう。
⇒合意形成研修コンセンサスゲーム ONLINEの資料を無料で受け取る
コンセンサスゲームは、合意形成・アサーティブコミュニケーションの講義・ワークとセットで研修として実施することもできます(対面形式・オンライン形式)。
⇒合意形成・アサーティブコミュニケーション研修の資料を無料で受け取る
まとめ
 研修を社員のスキルアップに繋げるためには、積極的にビジネスゲームを取り入れることがおすすめです。座学のみの研修と比べ楽しくモチベーションを維持しながら、主体的に考える社員を育成することに役立ちます。ビジネスゲームにはいろいろなものがあるので、社内の課題に合わせたものを検討してください。
研修を社員のスキルアップに繋げるためには、積極的にビジネスゲームを取り入れることがおすすめです。座学のみの研修と比べ楽しくモチベーションを維持しながら、主体的に考える社員を育成することに役立ちます。ビジネスゲームにはいろいろなものがあるので、社内の課題に合わせたものを検討してください。
このまま企画を進める前に、他社の成功パターンも見てみませんか?
年間1400件の体験型イベント実績をもとに、目的に合う企画と進め方をまとめました。
⇒「IKUSAサービス説明資料」を無料で見てみる
⇒ 企画段階でもOK!まずは相談してみる







 IKUSA.jp編集部
IKUSA.jp編集部