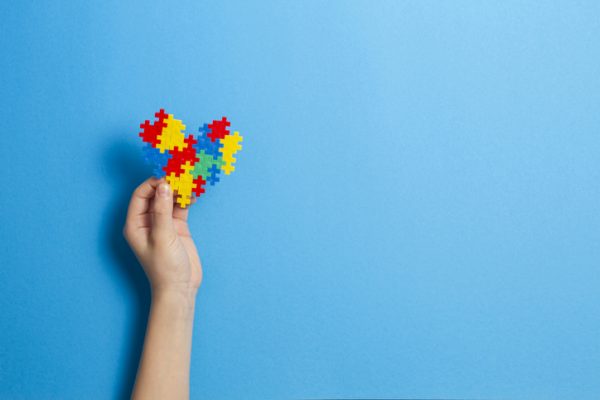updated: 2025
高齢者向けの音楽レクリエーション20選

目次
音楽系のレクリエーションを実施することで、参加者のストレス発散や関係性の構築などにつながります。
本記事では、高齢者向けの音楽レクリエーション20選を紹介します。
歌に関する高齢者向け音楽レクリエーション5選

歌は腹筋や口の周りの筋力を使えるほか、歌詞を覚えてリズム通りに歌うことにより、脳の活性化も期待できます。好きな曲を楽しんで歌えば、ストレス発散の手段としても有効です。
以下では、歌に関する音楽レクリエーション5選を紹介します。
1.カラオケ
「カラオケ」は、カラオケ機器が福祉施設や公民館などにあれば手軽に実施できます。高齢者は高音を出しにくくなりやすいため、簡単なボタン操作のみで音程を調整できるのもメリットです。幹事やファシリテーターが気を配り、参加者全員が満遍なく歌えるようにしましょう。
2.合唱
「合唱」は、複数人が「ソプラノ」「アルト」などのパートに分かれて歌うことを指します。合唱は、ほかのパートにつられないようにする難しさがある一方で、音程がぴったりハマったときには美しいハーモニーが感じられ、達成感や一体感が醸成されることが期待できます。
3.歌リレー
1曲を決められた文字数分だけ歌い、次の人にバトンタッチする音楽ゲームです。1人あたりの文字数を指定したり、1フレーズずつ歌ったりする方法があります。
<準備物>
- 人数分の歌詞カード
<ゲームの流れ>
- 参加者が輪になるように椅子を並べて座ってもらう
- 指定された文字数・フレーズを歌ったら次の人に繋ぐ。5文字に指定する場合は、「夕焼け小焼け」を歌う場合は「ゆうやけこ」まで歌って、次の人が「やけでひが」まで歌う
- 順番に最後までミスなく歌えれば成功
音楽レクリエーション全般に言えることですが、目的は完璧にやり遂げることではなく、皆で楽しむことです。途中で躓いたり、間違えたりしても笑いに変えて楽しんでもらいましょう。
4.輪唱
「輪唱」は、参加者を2つのグループにわけ、片方のグループが歌い始めてからワンフレーズ遅れてもう片方のグループが歌い始める「追いかけっこ」のような歌唱法です。
例えば「紅葉」の場合、以下のような流れで行います。
- 片方のグループが歌い始める
- 「あーきのゆーうー」まで歌ったところで、もう一方のグループが歌い始める
自分とは異なるグループにつられないように一致団結して取り組む必要があり、参加者同士の関係性の構築につながります。
5.パタカラ体操
「パタカラ体操」は、加齢とともに衰えてくる舌や口の周りの筋肉を歌いながら使うことで、誤嚥やムセの予防を図る体操です。介護施設で食事前に行われる「パタカラ体操」を、童謡のメロディに乗せて行います。「ももたろう」の歌で行う場合の手順を以下に紹介します。
- 1番の歌詞を通常通り歌って、皆でメロディを覚える。
- 適当なフレーズごとに区切って、歌詞を「パ・タ・カ・ラ」に置き換えて歌う。
「もーもたろさん、ももたろさん」→「パーッパパパパ、パパパパパ」
「おこしにつけた、きびだんご」→「タッタタタタタタ、タタタタタ」
「ひとつわたしに、くださいな」→「カッカカーカカカカ、ラララララ」
童謡は多くの高齢者が知っており歌いやすいため、「うさぎとかめ」「うらしまたろう」などがおすすめです。
脳トレ・頭の体操に関する高齢者向け音楽レクリエーション6選
音楽と脳トレを組み合わせることで、脳の活性化や交流促進などが期待できます。ゲームの勝敗にこだわりすぎず、参加者が自由な発想を楽しむことが大切です。
以下では、脳トレ・頭の体操に関する音楽レクリエーション6選を紹介します。
6.童謡カルタ
「童謡カルタ」は、童謡を連想するイラストが描かれた札で行うカルタです。
<準備物>
- 歌を連想するイラストを描いた取り札10枚程度
- 提供者が持つ歌い札
高齢者が見やすく取りやすいよう、手札は厚紙や画用紙を使って大きめに作りましょう。歌い札ごとに「1番の出だし、2番の出だし」など歌う部分を変えると、適度な緊張感と集中力を維持できます。
7.イントロクイズ
「イントロクイズ」は、参加者になじみのある童謡や歌謡曲のイントロを流して、曲名を当ててもらうゲームです。CDやYouTubeなどで音源を準備すれば簡単に行えることが特徴です。
8.曲名当てクイズ
「曲名当てクイズ」は、答えとなる曲を連想させるキーワードを3つ挙げて、曲名を当ててもらうゲームです。例えば「坂本九・ひとりぼっち・歩く」であれば答えは「上を向いて歩こう」、「二人・山のこだま・青空」であれば「二人は若い」となります。
9.音楽神経衰弱
「音楽神経衰弱」は、歌詞を書いたカードと、曲名を書いたカードを合わせるゲームです。
<準備物>
- 歌詞カード、曲名カード(各5~10枚ずつ)
<遊び方>
- 歌詞カードと曲名カードを裏返して、参加者全員が取りやすい位置に並べる
- 通常の神経衰弱と同様に、参加者に順番に2枚ずつ札を引いてもらう
- 正しいペアを引いたら、引いた人に曲を歌ってもらう。引いた人が知らない場合は、皆で歌う
10.音楽連想ゲーム
「音楽連想ゲーム」は、特定のテーマに沿って集めた複数の曲を参加者に聴いてもらい、連想する言葉を発表してもらうゲームです。
- 秋桜(コスモス)
- 紅葉
- まつぼっくり
- まっかな秋
上記の例であれば、「秋の歌」「秋の植物の歌」など、正しく連想される解答ができれば正解となります。正解は複数あるため、参加者の自由な発想で楽しることが特徴です。
11.字抜き歌遊び
「字抜き歌遊び」は、曲のなかの特定の言葉だけ歌わず、代わりに手を叩くゲームです。「むすんでひらいて」を例にすると、以下のようになります。
むすんで ひらい(て) (て)をうっ(て) むすんで
またひらい(て) (て)をうっ(て) その(て)を うえに
むすんで ひらい(て) (て)をうっ(て) むすんで
※(て)の部分は歌わずに手を叩く
ほかにも「あんたがたどこさ」の「さ」の部分で歌わずに手を叩くなど、歌詞に同じ言葉が繰り返し出てくる曲で行うのがおすすめです。
体を動かす運動に関する高齢者向け音楽レクリエーション7選
音楽を聴くとリズムに乗ることができるため、なじみの曲に合わせて体操すると、テンポよく身体を動かせます。
以下では、体を動かす運動に関する音楽レクリエーション7選を紹介します。
12.音楽手遊び
「音楽手遊び」は、童謡を歌いながら簡単な手遊びをするレクリエーションです。例えば、「うさぎとかめ」を歌いながら以下の順番で肩を叩いていくと、曲の終わりと手を叩タイミングが一致します。
- 右肩を8回、左肩を8回(もしもしかめよかめさんよ せかいのうちにおまえほど)
- 右肩を4回、左肩を4回(あゆみののろい ものはない)
- 右肩を2回、左肩を2回(どうして そんなに)
- 右肩を1回、左肩を1回(のろいの)
- 最後、歌が終わると同時に両手を「パン」と1回叩く(か)
このほか、童謡の歌詞に簡単な手話をあてて歌うなど、色々な遊び方があります。実施する際は、最初に提供者がやってみて見本を見せると、参加者もやりやすくなるでしょう。
13.絵描き歌
「絵描き歌」は、参加者に曲を聴いてもらい、思い浮かんだ情景を絵に描くレクリエーションです。画用紙とクレヨンや色鉛筆などがあれば実施できます。
曲目は参加者が好きなものや、「故郷」「お正月」などの昔を思い出しやすい童謡にすると、イメージが膨らみやすいです。描き終わったら、一人ずつ描いたものを発表する時間を設けると、コミュニケーションの円滑化にも繋がります。
14.リズム体操
「リズム体操」は、曲のリズムに合わせて身体を動かし、身体機能と集中力の維持向上を図るレクリエーションです。「幸せなら手を叩こう」「365歩のマーチ」「アブラハムの子」などは、歌詞に合わせて歌いながら身体を動かすだけでいい運動になります。
高齢者は足腰の筋力が弱っている場合があるため、ひじ掛け付きの椅子に座った状態で行うのがおすすめです。例えば「幸せなら足ならそう」という歌詞なら、座ったままで足踏みするよう声かけするとよいでしょう。
15.音楽ストレッチ
「音楽ストレッチ」は、歌って呼吸をしながら身体をほぐすストレッチ手法です。童謡「富士山」でのストレッチ例を以下に紹介します。
富士山の歌詞 | 身体の動き |
|
|
参加者の好きな歌を歌いながら、椅子に座ってつま先を上げ下げしてもらうだけでも十分なストレッチとなります。また、足首を柔らかくすることで、歩行時のつまずき予防も期待できるでしょう。ストレッチも安全を考慮して、椅子に座ったまま行うのがおすすめです。
16.音楽ボール渡しリレー
「音楽ボール渡しリレー」は、参加者に輪になって椅子に座ってもらい、歌を歌いながら隣の人にボールを渡していくゲームです。歌は「ずいずいずっころばし」「茶摘み」など、参加者が歌いやすいものであれば何でも構いません。参加者の身体機能に応じて、歌のテンポを早めたり、タイムを計測したりしてゲーム性を高めるのもよいでしょう。
使用するボールは、柔らかくて持ちやすいビニールボールでもいいですし、少し難しくしたいなら参加者がひとつずつ紙コップを持ち、ピンポン玉を入れてリレーしても楽しめます。
17.楽器演奏
参加者全員で楽器を演奏することで、一体感を得られて軽い運動にもなります。高齢者の音楽レクリエーションでよく使われるのは、タンバリンや鈴、ハンドベルなどです。
タンバリンや鈴は、曲に合わせて自由に叩いたり鳴らしたりするだけでも楽しめますし、皆で叩く場所やリズムを決めるのもおすすめです。握力の弱い高齢者の方がいる場合は「リストベル」という手首や足首に巻くタイプの鈴を使うと、無理なく演奏に参加できます。ハンドベルは、色分けされたものを使用して模造紙で色楽譜を作れば、「チューリップ」などの簡単な童謡をグループで演奏することもできます。
18.手作り楽器
身近にあるもので楽器を作ることで、手指の運動になり、材料ごとの音色の違いも楽しめます。今回は、ペットボトルやカプセルトイの容器を使ったマラカスの作り方をご紹介します。
<材料>
- ペットボトル、カプセルトイの容器、ビニールテープ
- ビーズ、あずき、どんぐり(きれいに洗って、冷凍庫で一度冷やしたもの)など
<作り方>
- 利用者に好みの容器を選んでもらう
- ①のなかに、ビーズやあずきなどを適量入れてもらう
- ②の蓋をしめ、外れないようにビニールテープでとめる
ペットボトルは500ml以下のサイズを用意すると、高齢者が演奏するときに持ちやすいです。
コミュニケーションに関する高齢者向けレクリエーション2選
音楽は記憶や感情と結びつきやすい性質があります。音楽を通じて昔の思い出を語り合ったり今の自分の感情を表現したりすることで、情緒の安定や他者との交流を促します。
以下では、コミュニケーションに関する音楽レクリエーション2選を紹介します。
19.回想法
1960年代にアメリカの精神科医ロバート・バトラー氏が提唱した心理療法です。参加者の思い出の品や写真などを見て、当時の楽しさや苦労を語り合い、これまでの人生を再評価し、自己肯定感を高める狙いがあります。
回想法は、童謡や歌謡曲など、参加者の思い出の曲を聴くことでも行えます。「この曲が流行っていた頃はどんな時代だった?」「どんな毎日を過ごしていた?」などと、提供者が適宜質問することで、参加者も話しやすくなるでしょう。
20.打楽器自己表現
「打楽器自己表現」は、タンバリンやハンドドラムなどの打楽器を使って、参加者に今日の機嫌を表現してもらう遊びです。明るく語りかけながら楽器を渡すと、参加者も叩きやすくなるでしょう。
力いっぱい叩く人もいれば、優しく穏やかに叩く人など、参加者の性格や個性が見えてくるのでアイスブレイクとして使うのも効果的です。
まとめ
音楽に関するレクリエーションは楽しく取り組みやすく、福祉施設や公民館などで高齢者向けに実施する際におすすめです。目的や参加者層などに応じて、適切なレクリエーションを活用しましょう。


 IKUSA.jp編集部
IKUSA.jp編集部