updated: 2025
イベントの効果測定で設定するKPIは?測定手法やアンケート作成のコツも

目次
イベントの運営に携わる担当者の中には、「イベントは成功だった」と自信を持って報告したいものの、その根拠をどのように示せばよいか悩んでいる方もいるかもしれません。投じたコストや労力に対してどのような成果が得られたかを可視化し、次につなげるためにも、ここで効果測定の方法を理解しておきましょう。
本記事では、イベントの効果測定で設定すべきKPIの具体例から、ROI分析やアンケートといった測定手法、そして上司も納得するレポート作成のコツまで、わかりやすく解説します。
イベント開催後に効果測定が重要な理由

イベントが無事に終了すると安心してしまいがちですが、本当に大切なのはその後の振り返りです。イベントの効果測定は、投じたコストや労力に対してどのような成果が得られたかを、客観的なデータで明らかにし、次のイベントにつなげるために欠かせない取り組みです。
「やりっぱなし」で終わらせず、得られたデータを分析することで、次回以降のイベントを改善するための貴重な学びが得られます。さらに、具体的な数値に基づいた報告は、上司や経営層への説得力を高め、今後のイベントへの予算獲得や、より大きなプロジェクトを任されるきっかけにもなるでしょう。
【目的別】イベントの効果測定で設定するKPIの例

効果測定を始めるにあたり、最初にすべきことは「何を測るか」を明確にすることです。その指標となるのがKPI(重要業績評価指標)で、イベントの目的によって設定すべき指標が大きく異なります。
ここでは、代表的な4つの目的別に、設定すべきKPIの具体例を紹介します。
見込み客獲得・商談創出のためのKPI
BtoBの展示会やセミナーでは、将来の顧客となる見込み客をどれだけ獲得し、商談につなげられたかが重視されます。単に名刺の枚数を数えるのではなく、その「質」を見極めることが大切です。
見込み客の質を把握できれば、営業部門のアプローチ効率が上がり、受注率の向上にも直結します。リード獲得を目的としたイベントでは、以下のようなKPIを設定して効果を測定することがおすすめです。
【指標の例】
指標 | 概要 |
CPL(Cost Per Lead) | 見込み客1件あたりの獲得コストを指します。イベントにかかった総費用を獲得した見込み客の数で割って算出し、1件あたりの費用を明確にすることで、他の施策との費用対効果を比較できます。 |
有効リード率 | 獲得した見込み客(リード)のうち、ターゲットとしていた業種や役職に該当する割合を示します。MA(マーケティングオートメーション)ツールなどを活用し、属性でセグメント分けして分析します。 |
商談化率 | 獲得した見込み客のなかで営業部門がアプローチし、具体的な商談に進んだ割合を指します。この数値が高いほど、質の高い見込み客を獲得できたと判断できます。 |
ブランディング・認知度向上のためのKPI
新商品のローンチパーティーや会社の周年記念イベントなどは、売上以外にも、ブランドの価値や認知度を高めることも大きな目的です。それらの目に見えにくい成果も、指標を立てれば可視化することが可能です。
ブランディング効果を把握するために活用できるKPIの例を以下にまとめました。
【指標の例】
指標 | 概要 |
メディア掲載数・広告換算価値 | イベントがテレビやWebメディアなどでどの程度取り上げられたのかを確認します。さらに、その掲載枠を広告として購入した場合の費用に換算することで、広報活動の成果を金額で示すことができます。 |
SNSエンゲージメント数・言及数 | イベントのハッシュタグが付いた投稿の数や、「いいね」「シェア」の総数を測定します。参加者によるポジティブな投稿が増えれば、ブランドイメージが向上していると考えられるでしょう。 |
指名検索数 | イベントの前後で、会社名や商品・サービス名での検索数がどれだけ検索されたのかを分析します。Google Search Consoleなどのツールで確認でき、世の中の関心度を把握します。 |
顧客満足度を向上させるためのKPI
既存顧客を対象としたユーザー会や感謝祭では、顧客満足度を高めて、顧客との関係性をより深めることが目的となります。顧客の「この会社のファンで居続けたい」と感じてもらえたのかを測定しましょう。
以下のようなKPIを設定して、顧客との関係性を数値で可視化することが有効です。
【指標の例】
指標 | 概要 |
NPS®(ネット・プロモーター・スコア) | 「この会社(商品)を友人や同僚にどの程度勧めたいですか?」を尋ね、顧客の愛着や信頼を数値化する指標です。 |
リピート参加率 | 過去のイベントにも参加してくれた顧客の割合を示す指標です。この数値が高いほど、顧客との間に良好な関係が築けていることがわかります。 |
コミュニティ参加率 | イベント後に案内した、顧客向けのオンラインコミュニティやSNSグループへの参加率を示す指標です。イベントを一過性のものとせず、継続的な関係構築につながったのかを確認できます。 |
優秀な人材を採用するためのKPI
採用説明会やミートアップといった採用イベントでは、将来の仲間となりうる人材に「この会社で働きたい」と思ってもらうことが目的です。採用市場が競争激化するなかで、イベントを通じてターゲット層に好印象を与えられるかどうかは非常に重要です。
その成果を客観的に確認するためには、以下のKPIを設定して測定するとよいでしょう。
【指標の例】
指標 | 概要 |
ターゲット層応募率 | イベント参加者のうち、会社が求めるスキルや経験を持つ人材からの応募がどれだけあったかを示す指標です。 |
選考移行率 | イベント参加後に、実際にエントリーしてくれたり、次の選考ステップに進んでくれたりした人の割合です。イベントが参加者の入社意欲を効果的に高められたのかを判断できます。 |
内定承諾率 | イベントに参加した候補者に出した内定が、どれだけ承諾されたかを示す指標です。他の経路で採用した候補者の承諾率と比較することで、イベントの効果を把握できます。 |
イベントの効果を測定する手法

KPIを設定したあとは、そのKPIを具体的にどうやって測定していくのかを考える必要があります。ここでは、多くのイベントに共通して活用できる5つの基本的な手法を紹介します。
ROI(投資対効果)を算出し、費用対効果を可視化する
ROI(Return On Investment)は、イベントに投じた費用に対して、どれだけ利益を生み出せたかを示す指標です。ROIを算出することで、イベントという投資がビジネス全体にどの程度貢献したのかを客観的に判断できます。
計算式は以下のとおりです。
ROI(%) = (イベントによる利益 ÷ イベントの総投資額) × 100 |
たとえば、100万円を投資したイベントから生まれた商談によって、150万円の利益が出た場合、ROIは50%です。この数値は、他の施策と比較する際の有力な判断材料となるでしょう。
アンケート調査を実施し、参加者の満足度や意識を測る
アンケートは、参加者の満足度や意見といった、数値だけでは捉えにくい「生の声」を直接収集できる手法です。イベント内容の評価や、ブランドイメージの変化、次回への要望などを把握できます。Webアンケートツールを活用すれば、集計や分析も効率的に進められます。
どのような質問を設計すべきかについては、「効果測定の精度を高めるアンケート作成のコツ」の章で詳しく解説するので、興味がある方はぜひ参考にしてください。
営業データを追跡し、売上への貢献度を分析する
見込み客獲得を目的としたイベントでは、その後の営業活動の成果を追跡することが欠かせません。CRM(顧客関係管理)やSFA(営業支援)といったツールを活用し、イベントで獲得した見込み客がどれくらいの期間で、何件商談化し、最終的にいくらの受注につながったのかを分析します。
そうした数値を明らかにすることで、イベントが売上にどの程度貢献したのかを金額で示すことができます。
メディアやSNSでの反響を分析し、認知度を測定する
ブランディングや認知度の向上を目的とイベントでは、メディアやSNSでの反響を分析します。Webメディアの記事やテレビでの報道などを収集し、その広告換算価値を算出する方法が一般的です。また、SNS分析ツールを使い、イベントに関する投稿数や閲覧数、そして内容のポジティブ・ネガティブ傾向を調べることで、社会的な反響を定量化できます。
参加者の行動や反応から、関心の高さや熱量を測る
アンケート結果だけでは見えない参加者の真の関心は、その行動に表れます。たとえば、セミナーの各セッションへの参加率や、ウェビナーでの途中離脱率、質疑応答での質問の数や内容、展示ブースでの滞在時間などを記録・分析することが有効です。
それらの客観的な行動データを読み解くことで、参加者が本当に興味を持ったコンテンツを把握できて、次回以降のイベントに活かせます。
効果測定の精度を高めるアンケート作成のコツ

アンケートは、設計の仕方によって得られる情報の質が大きく変わります。ここでは、イベントの効果測定の精度を高め、具体的な改善につなげるためのアンケート作成のコツを4つ説明します。
- イベントの目的から逆算して質問を設計する
- 定量質問と定性質問をバランスよく配置する
- 回答しやすい設問数とボリュームに調整する
- 具体的な改善につながる「深掘り質問」を入れる
イベントの目的から逆算して質問を設計する
アンケートを作成する際、つい「満足度」や「感想」ばかりを尋ねてしまいがちですが、本当に重要なのは「イベントの目的が達成できたか」を確認できる質問を入れることです。たとえば、製品の理解度向上を目的としたセミナーであれば、「本日のセミナーで、〇〇(製品名)の最も魅力に感じた機能はどれですか?」といった、理解度を尋ねる質問がおすすめです。
常にイベントの目的に立ち返り、その達成度を検証するための質問は何かを考えましょう。
定量質問と定性質問をバランスよく配置する
質の高い分析を行うためには、定量質問と定性質問をバランスよく組み合わせることが大切です。
- 定量質問: 「満足度を5段階で評価してください」のように、選択式で回答でき、全体の傾向を数値で把握しやすい質問
- 定性質問: 「最も良かった点を具体的に教えてください」のように、自由記述で回答してもらう質問。改善のための具体的なヒントや、思わぬ発見につながることがある。
先に定量質問で全体像を把握し、その後に定性質問で理由を深掘りする流れにすると、回答者も答えやすくなります。
回答しやすい設問数とボリュームに調整する
どれほど優れた質問を用意しても、回答してもらえなければ質問の意味がありません。アンケートの設問数が多すぎたり、回答に時間がかかりすぎたりすると、回答者の負担が大きくなり、途中離脱につながります。
回答時間は5分以内、設問数は10問程度に収まるようにするのが理想的です。どうしても聞きたいことが多い場合は、「必須回答」と「任意回答」の項目を分けるなど、負担を軽減する工夫を取り入れましょう。
具体的な改善につながる「深掘り質問」を入れる
「満足しましたか?」という質問に「はい」と答えてもらうだけでは、改善のヒントは得られません。「具体的にどのセッションが、どのような理由で役に立ちましたか?」あるいは「もし改善できるとしたら、どの点を、どのように変更すると、より満足度が上がりますか?」といった「深掘り質問」を入れることがおすすめです。それにより、成功要因や改善点を具体的に特定できて、次に活かせる有益な情報が手に入るでしょう。
上司も納得!イベントの効果測定レポートの項目

効果測定でデータが得られたら、次のアクションにつなげるためのレポートにまとめましょう。レポートを整理して提出することで、上司や関係者がイベントの成果を正確に理解でき、次の意思決定もしやすくなります。
ここでは、レポートの基本的な項目を解説します。
項目 | 概要 |
イベントの基本情報 | イベントの概要を簡潔に記載し、誰が見ても内容が把握できるようにする。 (例)イベント名、開催日時、場所、目的、ターゲット層、予算総額など |
主要な成果 | 事前に設定したKPIに対して、実際の成果を数値で示すレポートの中心部分。 (例)来場者数、新規見込み客の獲得数、商談化率、SNSでの反響、参加者アンケート満足度スコアなど |
費用対効果の分析 | 投じたコストと得られたリターンを明確に示し、経営層に訴求する。 (例)費用の内訳・合計金額、ROI算出方法と数値 |
会場の様子と参加者の声 | 数値だけでは伝わらない臨場感を補足し、説得力を持たせる。 (例)会場写真、アンケート自由記述のコメント、SNS投稿の抜粋など。 |
メディア掲載実績 | 第三者からの報道・掲載を示し、成功の裏付けとする。 (例)掲載メディア名、掲載日、記事タイトル、Web記事リンク。 |
総括 | イベントの成功要因と改善点を箇条書きでまとめる。 |
今後の提案 | 結果を踏まえ、次に取り組むべき具体的アクションを提示する。 |
イベントの基本情報
まず、このレポートが「何のイベントに関する報告書か」という前提情報を簡潔にまとめます。誰が読んでもすぐに概要を把握できるように記載しましょう。
【記載内容の例】
- イベント名
- 開催日時
- 場所
- 目的
- ターゲット層
- 予算総額など
主要な成果
次に、事前に設定したKPIに対して、実際にどのような成果が得られたのかを数値で示します。レポートの中心となる重要な部分です。
【記載内容の例】
- 来場者数
- 新規見込み客の獲得数
- 商談化率
- SNSでの反響
- 参加者アンケートの満足度スコア
これらの数値は目標や結果、達成率として表やグラフに整理すると、視覚的にわかりやすくなります。
費用対効果の分析
イベントにかかったコストと、それによって得られた成果を明確に示します。特に経営層が重視する項目であり、予算獲得の根拠にもなります。
【記載内容の例】
- かかった費用の内訳
- かかった費用の合計金額
- ROI(投資対効果)の算出方法
- ROIの最終的な数値
会場の様子と参加者の声
数字だけでは伝わらない、イベントの熱量や雰囲気を伝える項目です。定量データに加え、会場の雰囲気や参加者の感情を示すことで、レポートに説得力を持たせられます。
【記載内容の例】
- 会場の盛り上がりが伝わる写真
- アンケートの自由記述から抜粋した象徴的なコメント
- SNSでの好意的な投稿など
メディア掲載実績
テレビやWebメディアなど、第三者による報道や掲載は、イベントの成功を裏付ける強力な材料となります。
【記載内容の例】
- 掲載されたメディア名
- 掲載日
- 記事タイトル
- 記事へのリンク(Webメディアの場合)
総括
今回のイベントから得られた学びや課題をまとめる部分です。次回に向けた改善を考えるうえで欠かせません。成功の要因と次回に向けて改善すべき点を、データに基づいて具体的に箇条書きで整理します。
今後の提案
レポートの締めくくりとして、今回の結果を踏まえた具体的な次のアクションを提示します。報告で終わらせず、未来への提案を加えることで、担当者としての評価も高まる可能性があります。「今回の成果を踏まえ、次回は予算を拡大し、オンラインでも同時開催することを提案します」といった、データに基づいた建設的な提案を行いましょう。
【イベントの種類別】効果測定のポイント
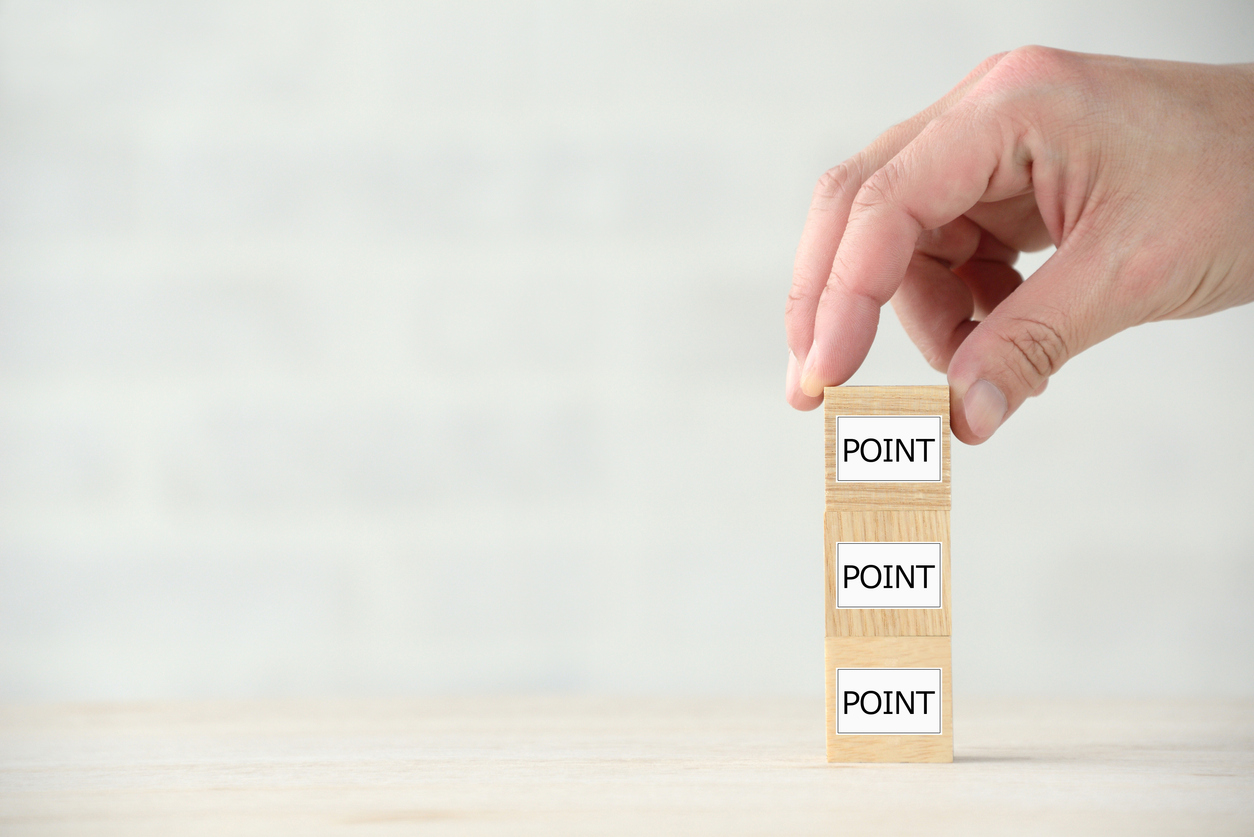
一口にイベントといっても、その種類によって目的や重視すべき指標は異なります。ここでは、代表的な3つのイベントごとに、効果測定のポイントとKPIの設定例を紹介します。
展示会における効果測定のポイント
多くの会社が出展する展示会では、多くの来場者の中からいかにして自社の見込み客を見つけ出し、関係を構築することが求められます。そのため、見込み客の量だけでなく、質に着目して評価することが重要です。
【重視すべきKPIの例】
- ターゲット属性の見込み客獲得数:獲得した見込み客のうち、本当に狙っていた顧客層(役職、業種など)の割合
- ブース滞在時間:ブース前を通り過ぎただけでなく、興味を持って長く滞在してくれた人の数や平均時間
- Aランク商談化率:イベント後に創出された商談のうち、受注確度の高い「Aランク」と評価された商談の割合
セミナー・ウェビナーにおける効果測定のポイント
セミナーやウェビナー目的は、参加者に専門的な知識やノウハウを提供し、自社製品やサービスへの理解を深めてもらうことです。参加者の満足度と理解度は、その後の問い合わせや資料請求といったアクションに直結するため、特に重視すべきポイントとなります。
【重視すべきKPIの例】
- アンケート満足度・理解度:「内容が役に立ったか」「理解が深まったか」を5段階評価などで測定したもの
- セッション毎の離脱率(ウェビナーの場合):参加者の関心がどこで離れてしまったのかを分析するための割合
- CTA(行動喚起)クリック率:セミナーの最後に案内した、個別相談会や資料ダウンロードへの申し込みページがクリックされた割合
社内イベントにおける効果測定のポイント
全社会議や周年記念パーティーといった社内イベントの目的は、社員の会社への愛着や貢献意欲を高め、会社としての一体感を醸成することです。成果が数値化しにくい分、アンケートなどを通じて可視化することがポイントとなります。
【重視すべきKPIの例】
- 任意参加イベントの参加率:社員の関心の高さを示す指標
- eNPS(従業員推奨度):イベント前後で「この会社で働くことを友人に勧めたいか」というスコアがどう変化したか示す指標
- 社内SNSの活性化度:イベントに関する投稿やコメントがどれだけ増え、部門を超えた交流が生まれたかを測定するための指標
イベントの効果測定に関するよくある質問

ここでは、イベントの効果測定に関するよくある質問とその回答をまとめました。
効果測定に役立つツールはありますか?
はい、目的に合わせてツールを使い分けることで、効果測定を効率的に行えます。Google Analyticsでは申込数や流入経路を把握できて、CRMやSFAなどでは見込み客の商談化や受注額まで追跡可能です。アンケートツールで満足度を収集し、SNS分析で認知拡大を確認すれば、成果を多角的に示せます。
もし測定結果が悪かった場合、どのように報告すればよいですか?
結果が思わしくなかった場合でも、データを隠さず正直に報告することが信頼につながります。ただし、単に「失敗でした」と報告するのではなく、「その結果になったのかという要因の分析」と「その学びを次にどう活かすかという改善策」をセットで提案することが大切です。「次はこうすれば成功の確率が上がります」と建設的な姿勢で報告することで、失敗を価値ある学びへと変えられます。
数値化しにくい「ブランディング効果」などは、どう伝えれば納得してもらえますか?
ブランディングのように、直接的に売上へ直結しない効果は、将来の成果につながる「先行投資」として説明するのがおすすめです。たとえば、アンケートでの「会社のイメージの変化」に関するスコアや、メディアの掲載実績、SNSでのポジティブな投稿といった客観的なデータを示しながら、「今回のイベントでブランド好意度がこれだけ向上したため、中長期的には指名検索数の増加や受注率の向上が期待できます」というように、未来の成果への貢献度を示すと説得力が高まります。
まとめ

本記事では、イベントの効果測定の重要性から、具体的なKPIの設定例、測定手法、アンケートやレポート作成のコツまで、幅広く解説しました。
イベントの効果測定は、成果を評価するためだけに行うものではありません。得られたデータは、チームの取り組みを客観的に証明し、次回のイベントをさらに成功に導くための指針となります。そして、データに基づいた改善を繰り返すことで、会社の成長に大きく貢献するでしょう。
今回ご紹介したKPIの設計例やアンケート作成のコツなどを参考にして、イベントの価値を可視化し、次の成功へとつなげてください。
“普通の企画”では物足りない、そんなイベントに。
IKUSAでは、チャンバラ合戦や謎解き、ワークショップ型アクティビティなど、企画映え・体験価値の高いコンテンツを100種類以上ご用意。コンセプトや会場に合わせて柔軟にカスタマイズ可能です。
「体験要素を入れたい」「参加者の記憶に残る演出がほしい」といったご相談も歓迎です。


 IKUSA.jp編集部
IKUSA.jp編集部




