updated: 2026
福利厚生で助成金を活用するメリット・注意点を紹介
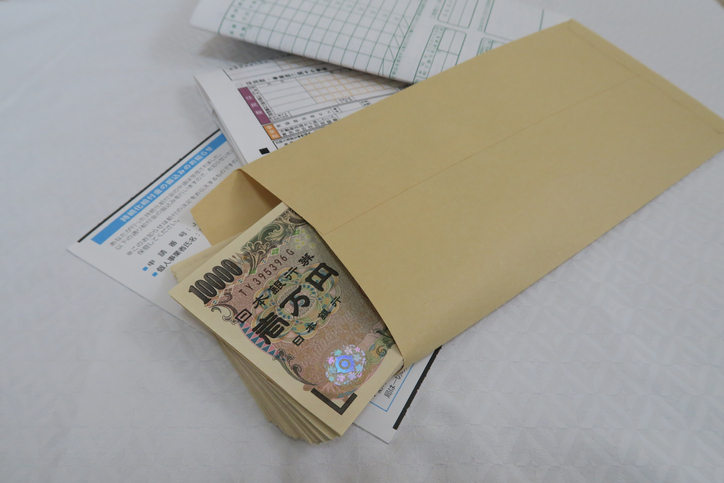
本記事では、福利厚生で助成金を活用するメリット、注意点、助成金5選を紹介します。
失敗できない社内イベント、準備は万全ですか?
年間1400イベントのプロに丸投げで安心のチームビルディングイベント
⇒企画案や実績、実施までの流れを見てみる
⇒企画段階でもOK!今すぐ相談してみる
福利厚生が必要な理由
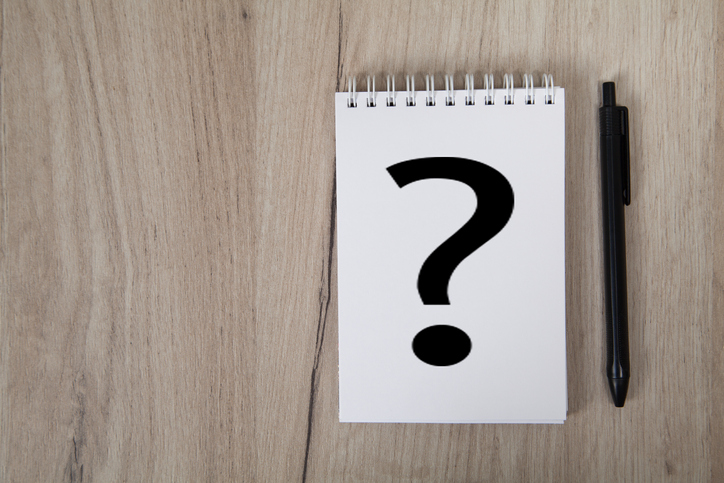
以下では、企業において福利厚生が必要な理由を紹介します。
理由1.法律で義務づけられているため
福利厚生は法律で義務づけられています。福利厚生は法定福利厚生と法定外福利厚生に分けられます。法定福利厚生は、法律に義務づけられている健康保険や介護保険、厚生年金保険などが含まれます。また、法定外福利厚生は、家賃補助や交通費の支給、特別休暇などがあります。
理由2.人材確保のため
就活生が福利厚生を重視して入社先を決めるケースもあります。福利厚生が充実しているほど就活生や求職者に興味を持たれやすくなり、人材確保につながります。
理由3.従業員を定着させるため
福利厚生は従業員の働きやすさに大きな影響を与えます。福利厚生を充実させ、従業員が働きやすい職場にすることができれば、快適に業務を進められるため離職率の低下につなげられます。
理由4.業績・成果を上げるため
福利厚生は従業員をサポートする制度であり、生産性の向上につながる場合があります。また、スキルアップやキャリア支援を行うことで、従業員の成長を促すこともできます。
福利厚生で助成金を活用するメリット

以下では、福利厚生の助成金を活用するメリットを紹介します。
返済の必要がない
助成金は、原則として返済する必要がありません。そのため、借金ではなく、雑収入として処理できます。あくまで助成は売上ではないため、その点に気をつけながら処理するようにしましょう。
費用を補填できる
予算が少ないと思うようにできませんが、助成金を申請することで、福利厚生を充実させられる可能性があります。中小企業やベンチャー企業の福利厚生を充実させる際の支援になるでしょう。
助成金を活用する際の注意点

以下では、福利厚生の助成金を利用する際の注意点を紹介します。
事前に計画を立てて申請する
助成金は要件を満たし申請すれば受け取ることができますが、申請作業の手間がかかります。余裕を持って準備するようにしましょう。
受給するための要件がある
申請する前に、助成金を受け取るための要件を確認していくことが重要です。具体的な要件内容は助成金によって異なります。
福利厚生に関する助成金5選

福利厚生に関連する助成金を5選紹介します。
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者や短時間労働者といった非正規雇用の労働者における企業内でのキャリアアップを目指すための助成金です。コースは7つ設けられています。
- 正社員化コース
- 障害者正社員化コース
- 賃金規定等改定コース
- 賃金規定等共通化コース
- 諸手当制度等共通化コース
- 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
- 短時間労働者労働時間延長コース
助成金の詳細:キャリアアップ助成金|厚生労働省
トライアル雇用助成金
トライアル雇用助成金とは、職業経験や技能などの問題から安定的な就職が難しい方に対して、ハローワークや職業紹介事業所などの紹介によって一定期間試行雇用した場合に助成される制度です。
助成金の詳細:トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)|厚生労働省
特定求職者雇用開発助成金
特定求職者雇用開発助成金は、高年齢者や障害者といった就職困難者を雇う際に助成される制度です。
- 特定就職困難者コース
- 生涯現役コース
- 被災者雇用開発コース
- 発達障碍者・難治性疾患患者雇用開発コース
- 三年以内既卒者等採用定着コース
- 障害者初回雇用コース
- 安定雇用実現コース
- 生活保護受給者等再開発コース
助成金の詳細:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) |厚生労働省
人材確保等支援助成金
人材確保等支援助成金は、従業員の離職率低下や労働環境の向上などを目指す企業に対して助成される制度です。
- 雇用管理制度助成コース
- 雇用管理制度助成コース(建設分野)
- 人事評価改善等助成コース
- 介護福祉機器助成コース
- 中小企業団体助成コース
- 外国人労働者就労環境整備助成コース
- テレワークコース
- 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)
- 作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)
助成金の詳細:人材確保等支援助成金|厚生労働省
両立支援等助成金
最後に紹介する両立支援等助成金は、育児や介護をしている従業員が働いている企業におすすめの制度です。こちらの場合、以下のコースに分かれています。
- ・出生時両立支援コース
- ・介護離職防止支援コース
- ・再雇用者評価処遇コース
- ・育児休業等支援コース
- ・女性活躍加速化コース
助成金の詳細:両立支援等助成金|厚生労働省
まとめ

今回は、福利厚生に関する助成金を紹介しました。
このまま企画を進める前に、他社の成功パターンも見てみませんか?
年間1400件の体験型イベント実績をもとに、目的に合う企画と進め方をまとめました。
⇒「IKUSAサービス説明資料」を無料で見てみる
⇒ 企画段階でもOK!まずは相談してみる


 IKUSA.jp編集部
IKUSA.jp編集部




