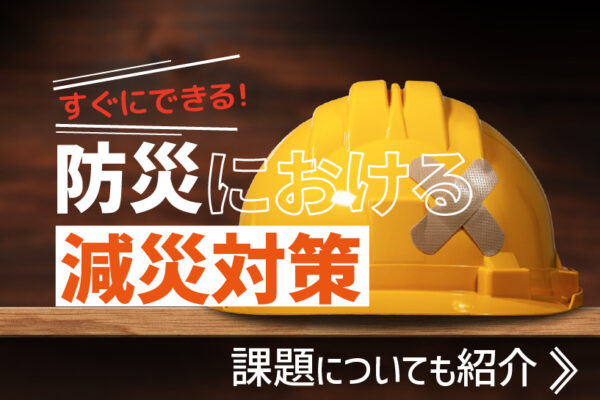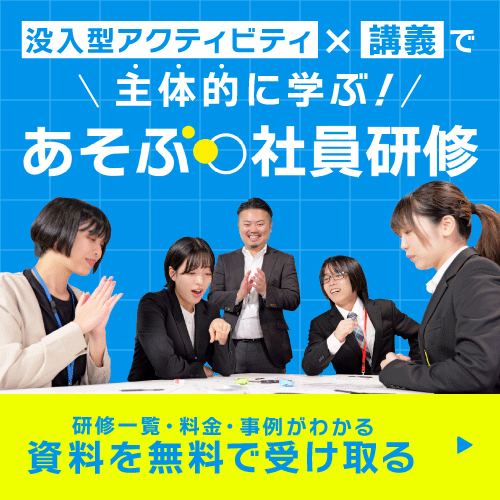updated: 2024
防災イベントの企画方法・内容、面白い企画例20選

防災イベントを企画するときに大切なポイントとは何でしょうか?
「マンネリ化している」「面白くない」「人が集まらない」といった悩みを解消するには面白い要素を企画に盛り込むことが重要です。
本記事では、子どもから大人まで楽しめる防災イベントの企画方法・内容、面白い取り組み20選、防災関連アクティビティを紹介します。
防災研修・防災イベントの実績200件以上。あそびの力で防災意識を高める「あそび防災プロジェクト」とは?
⇒無料で資料を受け取る
企業防災でおさえるべきポイントを網羅した防災マニュアル「担当者必見 企業向け防災完全ガイド」とは?
⇒無料で資料を受け取る
防災イベントの必要性

防災イベントと聞くと少し堅い印象を持つ方も多いのではないでしょうか。開催にあたってどのように興味を持ってもらうかは、開催者側の頭を悩ませる問題です。そんなときは、「防災イベントはなぜ必要か?」を分かりやすく伝えられるようにするとよいでしょう。ここでは、防災イベントが必要である理由について確認してみましょう。
日本は災害大国でも防災意識が高い人は少ない
防災大国である日本では、毎年のように地震や台風、大雨など自然災害が発生して広範囲の地域が被害にあっています。そして、災害発生時に自分や家族の身を守ってくれるのが、それまでに習得していた防災知識です。いざという時に防災知識がないと、とっさの避難が遅れたり、十分な備えができておらず被災生活で危機に直面する可能性があります。
災害はいつどこで起きるかわかりません。防災知識は災害が起きた後に学ぶのでは遅く、普段から身に着けておくことが最も大切です。
防災イベントなら、楽しく防災知識を学べる
防災知識を得るためには学習が必要ですが、前述の通りに「防災」と聞くとやや堅い印象を受け、参加者側としても興味が湧きにくく、後回しにしがちです。
しかし、ゲーム性のある参加型のイベントであれば親子や仲間たちと「楽しめる時間」の一環と認識してもらえ、防災知識を学ぶきっかけとできるでしょう。そんな防災イベントでさまざまな体験をすることで防災の基礎知識を気軽に習得でき、日ごろの防災対策を見直すことができます。
防災イベントの企画方法・コツ

防災は老若男女全ての人が身につけておくべき知識です。そのため防災イベントでは、より広い層から関心を持ってもらえるような内容にしたいところです。
防災イベントを成功させるために押さえておきたい、企画のコツをいくつか紹介します。
大人も参加できる内容にする
イベントといえば子どもが集まるイメージを抱きますが、防災イベントは決して子どもだけのためのものではありません。災害時は年齢問わず全ての人が適切な行動を取る必要があります。そのため、子どもだけでなく大人も楽しく参加できるゲーム内容にすることが大切です。
ファミリー向けであれば保護者も子どもと一緒に参加できる体験イベントを取り入れる、職場であれば帰宅困難時の対策や防犯ベル・消火器の使い方講習など、幅広い年代が参加できる内容にしましょう。
興味を引きつける、楽しい内容を取り入れる
防災イベントは楽しむだけのイベントではなく、命を守る行動など災害時に必要な知識を学ぶものです。ただし、真面目なだけの内容だと興味を持ってもらいにくいため、ゲーム性のある楽しい内容とすることで、参加のハードルが下がるでしょう。
たとえば小さい子ども向けに、本物の消防車を用意すれば興味を持ってもらえる工夫になります。また、消防はしごに乗って地上数メートルの高さまで上がる、地震と同じ震度で揺れるトラックに乗る、消火器を使うなど、実際に体験できるものがあると周囲の注目を引き付けます。参加者に防災グッズをプレゼントするなどのアイデアもおすすめです。
防災知識を普段の生活に結びつけられる内容にする
参加者がイベントを通して防災知識を学び、普段の生活でも防災意識を高められるのが望ましいです。
たとえばペットボトルを使った簡易ランタンや新聞紙で作る防災スリッパなど、生活に身近なものでできる防災対策のワークショップを開催すると、興味を持ってもらえるでしょう。そのほか実際に被災した方の体験談を聞く、防災マップを作るなど、参加者に合わせた企画で、その後の生活に結びつく内容にできると参加者の満足度も上がるでしょう。
わかりやすい内容にする
防災イベントの理想は、小さい子どもから大人まで参加できるものがベストです。そのため、防災に必要な知識はわかりやすく、いざという時に活用できるものを紹介する必要があります。
たとえば小・中学校の防災教育として、避難訓練の「押さない・走らない(かけない)・しゃべらない・もどらない」という『おはしも(おかしも)の約束』などは子どもでも覚えやすく、非常時でも思い出しやすい内容です。災害時に必要な防災知識は多岐に渡りますが、防災イベントではできるだけ老若男女問わず理解しやすい内容を取り入れるといいでしょう。
継続して実施する
防災イベントは他の一般的なイベントとは異なり、ただ楽しむだけのものではありません。災害はいつ起きるかわからないため、一度やって終わりではなく、継続しておこなうことが大切です。防災の日に合わせる、学校や地域のスケジュールに組み込むなどで定期的に開催できる日程を確保し、参加者の防災意識を高めることが重要です。
また、防災グッズや避難方法などの情報は日々進化しています。防災イベントで最新の情報を開示することで、参加者により安全で効果的な防災知識を提供できるよう意識しましょう。
地域の防災情報を盛り込む
災害時は自宅や学校、職場周辺の避難経路や避難所の情報が重要です。海沿いや地震が多い、台風が多いなど、地域によって必要な災害時の避難方法や防災対策は異なります。
防災イベントでは開催する地域の防災情報をわかりやすく開示することで、参加者がいざという時の行動をとりやすくなります。
防災イベントに適した内容

防災イベントで学べる知識は多岐にわたります。開催中にすべてを盛り込むことは難しいため、開催場所や参加者の年齢層によって取り入れるべき内容を選びましょう。
1. 災害発生時の命を守る行動
たとえば地震が起きたときに室内ならテーブルの下にもぐる、屋外なら公園などの広い場所に逃げる、海辺の近くなら津波の恐れがあるので少しでも高い場所に避難するなど、災害発生時の数秒・数分の行動は命を分ける可能性がある重要なもの。年齢を問わず身に着けておきたい内容なので、イベントに組み込みたい内容です。
2. ハザードマップの確認
自宅や学校、職場のハザードマップを確認しておくことで、その地域ではどんな災害が起こりやすいのか、また、災害が起きてしまった場合にどれくらいの被害が想定されるのか把握することができます。また、避難所がどこにあるのか、避難所までの最短ルートなどもあらかじめ知っておけば、被災時もあわてず冷静に行動することができます。
3. 防災グッズや非常食のリスト紹介
必要性を感じつつも、「避難するときに必要な防災グッズをしっかりと準備している」という家庭は実際に多くありません。非常時に持ち出すリュックの中身や、自宅避難することになった場合に必要な人数分の非常食はどれくらいかなどをきちんと把握し、普段から用意しておくことで被災時、被災後に命を守る行動に繋がります。
4. 非常食や炊き出しの試食会
存在は知っていても、なかなか実際に食べる機会がない非常食。特に乳幼児が食べられるものがない、電気やガスがない状態でどのように調理するか分からないなど、いざという時に困らないように非常食や炊き出しの体験をするのも効果的です。実際にどんな味がするのか、電気がない場合はレトルト食品を温めるのにどれくらいの時間がかかるかなどを実際に体感できると、日頃の備えに目を向けるきっかけになります。
5. 消火器の使い方
災害時は火災が起こりやすくなるため、消火器の使い方は学校の避難訓練などでもよく取り入れられる項目です。火災発生時、近くに消火器があれば被害を最小限におさえることができますが、使い方を知らなければ火災が拡大してしまう恐れがあります。正しい使い方や使用期限のほか、住んでいる建物や学校・職場のどこに消火器があるのか、場所を把握することも大切です。
6. 室内からの脱出方法
自宅など屋内にいるときに災害が起こり、その場所から逃げる必要がある場合もあります。室内でもガラスの破片を避けるため靴を履く、ベランダの蹴破り戸を蹴る、頭を守り姿勢を低くするなど、避難方法を知っておくことで二次災害を防ぐことにつながります。
7. 災害を「自分ごと」とする意識づけ
防災イベント参加している人の中でも、防災を心から自分ごととして意識している人はそう多くないかもしれません。災害が起こっていても、身近に被害がない限りはつい他人事としてとらえてしまいがちです。
そのため、防災イベントでは「災害を自分ごと」とする、参加者の意識づけをおこなうことが必要です。被災者の講演会をおこなうなどで、「災害が起きたときに自分や家族はどうなってしまうのか、家がなくなってしまったらどうするのか」と想像してもらえる内容にしましょう。
防災イベントの面白い取り組み20選
「面白くてかつ勉強になる防災イベント」を実施するために、実際に開催されたイベントをヒントに企画を進めてみましょう。ここでは全国で開催された、ユニークな防災イベント事例を紹介します。
1. 防災お茶会
家が近い人が集まり、お茶を飲みながら地域の防災情報を学ぶイベント。自分の住む地域の消火器や消火栓の位置、防災倉庫の備品などを把握しておくことでいざというときの行動がスムーズになります。また、お茶会を通じてご近所さんと顔を合わせておくことで、被災時の助け合いにつながります。
参考:もっと和歌山「大切な家族を守るための「防災お茶会」を開催」
2. 防災食の屋台村
非常食と言っても、一般的なレトルト食品とは違って非常食は5年や10年など長期保存が可能なことや、昔と比べて格段に味がよくなり進化した非常食のおいしさ、温めなくても食べられるものなど知られていないことは数多くあります。屋台でレトルト食品などの非常食を無料で提供することで、参加者は気軽にお祭り感覚で参加できるほか、食べなれていない非常食を味わい、災害について学ぶきっかけになります。
また、イベントを公園などの災害時避難場所で開催することにより、地域の人の防災意識をさらに高める効果があります。
参考:NPO法人ハマのトウダイ「Park Caravan@保土ヶ谷駅前公園 〜防災食の屋台村〜」
3. マンション備蓄品見学ツアー
災害時に自分の住むマンションにはどのような非常用設備があるのか気になるもの。このマンション備蓄品見学ツアーでは、実際に住民が普段見ることのない設備を探検・見学するツアーです。
マンションの備蓄倉庫を見学し、どのようなものが備えられているか確認します。合わせて簡易担架と非常用簡易トイレの使い方の説明や避難場所の再確認も実施。住民の安心感と防災意識を高める機会になります。また、同じ参加者どうしの交流のきっかけにもつながります。
参考:一般社団法人マンション管理業協会「マンション居住者が一体となって、楽しみながら学べる防災イベントを開催」
4. LINEでデジタル避難訓練
場所を選ばず避難訓練をLINE上で開催するできる、デジタル避難訓練。福岡市で開催され、参加者には6日間のうち予告なく通知が届き、実際に災害が起きたことを想定して行動します。
また、LINEで位置情報を送ることで付近の避難場所がアップされ、現在地からのルートも検索できます。そのまま家族や友達に避難場所をLINEで連絡できるなど、なかなか参加するきっかけがつかめない人でもスマホ上で気軽にできる避難訓練です。
参考:LINE FUKUOKA「とつぜんはじまる避難訓練」
5.防災スマホ教室
情報収集になくてはならない存在になったスマートホン。災害時にもいかにスマホを駆使して情報を受け取れるかが、生死の分かれ目になる可能性も考えられます。
しかし特に高齢者世代では、スマホを普段使っておらず使い方に慣れていないという方も多い状態です。そこで東京都板橋区では、スマホを使って気象情報や避難情報を自分で取得できるようにするための教室を開催しました。内容は初めて触る方でも分かるように、電源の入れ方やタップ・スライドといった基本的な操作方法から学べる内容に。世代に特徴に合わせて、防災の観点から必要な支援を提供できる教室を作り上げています。
参考:板橋区「防災スマホ教室」
6.高尾山・サタデーナイトミュージアム
東京都八王子市にある高尾599ミュージアムで開催された「サタデーナイトミュージアム」。「夜を楽しみ、動物の生態や防災を学ぼう」をコンセプトに、夕方の美術館にてイルミネーション作りや防災学習、炊き出し体験を楽しめるイベントです。イベントは防災に特化するのではなく、普段体験できない“夜のミュージアム”を軸に企画されているので、幅広い関心層をイベントに呼び込みました。
地域資源を生かしてコラボ的に開催するのも一つの集客手段です。
参考:高尾599ミュージアム「イベント」
7.ショッピングモールでの防災イベント
東京都町田市にあるショッピングモール「南町田グランベリーパーク」は、帰宅困難者受入施設、風水が維持避難場所、一時退避場所といった、地域の防災拠点としての機能を有しています。ショッピングモールに入っている店舗をあげて開催したイベントでは、災害を自分ごと化して考えるための「AR・VR体験」や、ペットのための防災ブース「首輪作り体験」、災害時に役立つ知識が得られる本を紹介する「読む防災」など、施設に入る店舗それぞれの特徴を生かしたイベントが集まりました。
普段使っている施設がいざという時の防災拠点にもなると周辺住民に知ってもらえることも、イベント開催の価値ある効果です。
参考:Mitakaみんなの防災「南町田グランベリーパーク みんなで学ぼう!まちの防災2023」
8.100均防災展示
北海道札幌市白石で開催された「白石おやこ防災フェスタ」。防災フェスタでは楽しく気軽に学ぶことができるさまざまなイベントを用意しました。中でも「100均防災展示」では100円ショップで手に入る商品の中で、防災に使えるものを展示・紹介。普段から利用する人も多く、安価で実践しやすい商品に着目した好アイデアです。
そのほかにも緩衝材を使った防災アイテムのワークショップなど、身近なところから始められる防災のアイデアが満載のイベントとなりました。
参考:札幌市白石区「「令和5年度白石おやこ防災フェスタ」を開催しました!」
9.ぼうさい探検隊
一般社団法人日本損害保険協会が提供する「ぼうさい探検隊」。子どもたちが楽しみながら、まちの防災や防犯に関する施設・設備を周りマップにまとめるプログラムです。実際に自分たちの住むまちを歩いてめぐることで、ルートや施設が頭に入り、いざという時のとっさの行動に繋げられます。
足を動かして確認したまちの危険箇所とハザードマップとを見比べることで、情報をよりリアリティを持って受け取るきっかけにもなるでしょう。
参考:一般社団法人日本損害保険協会が提供する「実践的な安全教育プログラム「ぼうさい探検隊」の実施」
10.海外在住者も参加した防災ゲーム「帰宅困難サバイバル」
株式会社IKUSAが提供している防災コンセンサスゲーム「帰宅困難サバイバル」。チーム内の合意形成(コンセンサス)をオンラインゲームとして実施できるこちらのサービスですが、進行の補助を英語で行いながら、海外在住者に向けて実施。日本ならではの災害に馴染みの薄い参加者にも、災害に対する危機意識を伝えることができました。日本の外国人居住者にとっても非常に重要な防災。英語を用いての開催ができるイベントであれば、言葉の壁を超えて防災の啓発を進められるでしょう。
当日の詳しい様子が知りたい方は、以下の記事もぜひご覧ください。
参考:あそび防災プロジェクト「【英語で実施!】防災コンセンサスゲーム 帰宅困難サバイバルを南米諸国の皆様に体験いただきました!」
11.防災ゲームに参加したポイントをゲット!「イザ!カエルキャラバン!」
美術家の藤浩志さんとNPO法人プラス・アーツが共同開発したこちらのイベント。参加者はいらなくなったおもちゃを持ち込みます。集められたおもちゃは状態のよさなどで査定を受け、ポイントがついた状態でショップに並びます。イベント参加者は、防災ゲームをクリアすることでポイントをもらえ、そのポイントをおもちゃと引き換えることができるのです。
このイベントは主に子どもを対象としていて、景品を目指してゲームに繰り返し挑戦し、自然と防災意識を高められます。入口は広く、着実に防災を浸透させる工夫の凝らされたイベントです。
参考:内閣府「特集 心をつかんで広げよう」
12.防災ピクニック
東京都東久留米市で開催された防災イベントの中の企画の一つ、防災ピクニック。参加者は市役所から提供された廃棄予定の段ボールを使って、実際の避難時にも役に立つ段ボールハウスや自分用のプライベートスペース作り、非常用トイレ作りを体験できました。さらに作成で出た段ボールの端切れを利用して「自由にお絵描き&工作」時間も設け、被災後の子どもたちの遊び道具作りも意識した内容となりました。
一般社団法人防災教育普及協会「都立六仙公園で防災キャラバン、500名を超える親子連れや住民が参加」
13.防災料理教室
兵庫県神戸市では、大学の栄養学部生が中心となって、ローリングストックで災害ごはんを考える料理教室を開催しました。ローリングストックとは、普段から少し多めに食材や加工品をストックしておき、日常生活からその備蓄品を使い買い足しながら災害に備える方法です。
教室では食材キットとおうちの食材を使って作るオリジナル災害レシピを考えたほか、地域の防災への取り組みや災害時の食の考え方などのレクチャーも企画。親子を対象とし、地域防災力を高める目的で実施します。
参考:神戸市役所「親子防災料理教室の開催」
14.避難訓練コンサート
神奈川県にある横浜みなとみらいホールでは、2007年から「公演中に災害が起きたら」という想定の元、避難訓練込みのコンサートを実施してきました。避難訓練コンサートでは、コンサートをそれを中断しての避難訓練が実施されます。災害に対する講義が行われることもあり、地域の吹奏楽部や警察・消防と協力して開催されています。
公演中は足元が見えにくいことによる危険や大勢を避難誘導する必要が想定され、机上のマニュアルを実践することで見えてくる改善点を検証し、来るべき時に備える目的で開催されています。
参考:公益社団法人全国公立文化施設協会「避難訓練コンサートとはどのようなものか。」
15.防災情報チラシ
社会情勢やさまざまな理由で、「集まって実施することが難しい」という状況の中でも途切れることなく防災普及に取り組んだ工夫が「防災情報チラシ」です。兵庫県丹波篠山市東部の日置地区では、集まっての防災訓練が難しいと判断した年に「チラシで学ぶ防災訓練」として、チラシを地区全戸配布及び店舗に設置しました。
チラシの内容は同地区の防災士と消防団で内容を検討し、「子育て世代や高齢者向けの避難ポイント」や「避難行動のスケジュール表」などを掲載。イベント自体の実施は難しくても、切れ目なく防災普及に取り組む工夫を凝らした事例です。
参考:丹波新聞「コロナ禍でも訓練を 防災情報チラシに 全戸配布へ」
16.映画上映鑑賞付き防災訓練
福島県いわき市にある劇場「いわきアリオス」では、公演中に災害が起きたことを想定した避難訓練です。こちらの訓練は職員の防災意識を高めることを目的として実施され、対応スタッフは訓練内容の詳細は事前に知らない「ブラインド訓練」。参加する観客を募る形での実施となりました。
参加費は無料で長編作品と防災訓練を体験できるイベントとなっていて、参加者にとってもスタッフにとっても防災意識を高めながらユニークな体験ができる試みとなりました。
参考:いわき芸術文化交流館「いわきアリオス令和元年度下期防災訓練(映画鑑賞会付き)」
17.防災ウォークラリー
神奈川県横浜市では、防災にまつわる展示を各ポイントとするウォークラリー形式で防災イベントを実施しました。防災用品や段ボールベッド、簡易トイレに触れながらスタンプラリーを進められる形式で、そのほかにも起震車や水消化器、煙体験ハウスやバケツリレーを体験できるブースも設置しました。
地域の自治体、町内会がイベントを企画・運営したこちらのウォークラリー。災害時は地域の繋がりが大切になってくるため、イベント企画の段階から共助の取り組みがなされているのも優れた事例と言えるでしょう。
参考:横浜市「にしく通信!(東久保町夢まちづくり協議会防災ウォークラリー)」
18.おとなリ場交流会
防災に限らず日常的な活動グループとしてのご近所付き合いを目指して作られた神奈川県横浜市内の自治会の「おとなり場」。普段からメンバー同士でお茶会や趣味を楽しむ場を設けていて、その中の要支援者には「お助けグッズ」を配布しています。懐中電灯やホイッスル、タオルなど、いざという時に役に立つグッズがひとまとめにされていて、普段からのお互いの見守りに加え、防災弱者への備えを普段から意識して実施しています。
大きなイベントではありませんが、普段からの継続的な近所の交流を生み出す取り組みとして注目されています。
参考:横浜市「安否確認ができる関係をつくろう」
19.防災クイズ大会
茨城県つくばみらい市の小学校にて開催された、株式会社IKUSAが提供する「防災クイズ大会」。児童が楽しみながら学べる防災イベントを目的に開催され、当日は二択問題を体を動かしながら回答していき、わいわいと友達と楽しみながら最新の防災知識を学ぶ時間となりました。
イベント実施後、児童の皆さんに当日得られた気づきをお手紙にしていただくなど、体験型ゲームを通じて自発的に防災を学ぶきっかけ作りのお手伝いさせていただきました。詳しい実施の様子が知りたい方は、以下の記事をぜひご覧ください。
参考:あそび防災プロジェクト「富士見ヶ丘小学校にて「防災クイズ大会」を実施しました!」
20.防災ヒーロー入団試験
熊本県で開催された防災イベント「防災パーク」では、株式会社IKUSAが提供する体験型ワークショップ「防災ヒーロー入団試験」を実施しました。こちらのイベントでは、全7つの試練のうち、3つ以上クリアすると、「防災パーク特製防災ヒーロー認定バッジ」を手に入れることができる仕組みに。試練も子どもがゲーム感覚で楽しめる「スモーキー迷路」や「防災リュック間違い探し」など、意欲的に参加できる工夫を凝らしながらも、防災について親子で改めて考える機会とすることができました。
詳しい当日の様子が知りたい方はぜひ以下の記事もご覧ください。
参考:あそび防災プロジェクト「「熊本地震の日」周知啓発事業「防災パーク」で「防災ヒーロー入団試験」を実施しました!実施内容と参加者様の感想をご紹介!」
体験型の防災アクティビティ3選

面白い防災イベントとしてオススメするのが、防災訓練部門にて2020年度グッドデザイン賞を受賞した、株式会社IKUSAが提供している体験型防災イベントの『あそび防災プロジェクト』です。子どもも大人も楽しめる内容で防災イベントの参加ハードルを下げ、自ら「やってみたい」と思える人気のアクティビティが注目を集めています。
1. 運動会に防災を取り入れた「防災運動会」

「防災運動会」とは、その名のとおり防災の知識を取り入れた新しい運動会。競争やチームプレイといった運動会の特徴を残しつつ、参加しながら防災に関する知識や知恵を学ぶことができる運動会です。身体を使って楽しく防災体験ができるため、防災に興味のない人でも参加したくなるメリットがあります。
防災運動会では防災を5つのフェーズに分け、事前準備や災害発生時、災害発生直後、災害発生後72時間、生活再建とそれぞれのフェーズに応じた競技を体験できます。種目は「防災障害物リレー」、「防災借り物競争」、「避難所ジェスチャーゲーム」、「非常食体験会」などさまざま。地震が多い地域や台風が多い地域、被災するのが会社や自宅にいる場合など、開催する地域や参加する世代によってカスタマイズが可能です。
企業の運動会・レクリエーションや、地域の防災啓発に取り入れられているおすすめの防災イベントです。
2. オンラインでチームや家族と防災を学ぶ「おうち防災運動会」

「おうち防災運動会」は、オンライン上で防災体験ができる防災アクティビティです。運動会のようにチームでの競争を楽しみつつ、自宅ならではの防災体験ができる新しい防災教育のひとつです。
おうち防災運動会でも災害を5段階のフェーズに分け、それに応じた競技を体験します。参加者は「防災間違い探し」や「防災謎解き 崩れゆく会議室からの脱出」、「おうち探検!非常食探索トライアル」など、さまざまなオンライン競技を楽しみながら防災知識や体験を得ることができます。また、オンラインならではのチームビルディング要素も多く、自分の身を守り、他人を助けることの大切さを学ぶことができます。
家族で一緒に体験できるほか、新型コロナウイルスで開催できない企業の研修などでも取り入れられている人気のイベントです。
3.防災知識を楽しく学べる「防災ヒーロー入団試験」

「防災ヒーロー入団試験」は、親子で参加できる体験型防災アクティビティです。頭と体を両方動かしながら、楽しく防災知識を学べます。
防災ヒーロー入団試験は「楽しい」にフォーカスしたイベントなので、防災を学び始める子どもにも最適です。
「防災スリッパ作り」や「水消火器射的」、「防災ウォークラリー」など、ユニークな試験をクリアして、防災ヒーローを目指しましょう!
防災ヒーロー入団試験の事例はこちら
【開催事例】「防災ヒーロー入団試験」アリオ上尾様
まとめ

災害はいつ何時起きるか分かりません。そのため継続的にイベントを開催して、誰でも気軽に参加できる防災イベントを確立していくことが重要です。企画のコツをしっかりおさえて、参加者のためになる充実した防災イベントを開催しましょう。
「やらないと」から「やってみたい」と思える防災へ。「あそび防災プロジェクト」は、謎解きやワークショップ、運動会などの体験型イベントを通して参加者が防災を学ぶきっかけをつくるプロジェクトです。サービスの詳細や具体的な事例は下記の資料でご確認ください。
⇒無料で「あそび防災プロジェクト」総合資料を受け取る
企業防災でおさえるべきポイントを網羅した防災マニュアル「担当者必見 企業向け防災完全ガイド」とは?
⇒無料で資料を受け取る


 IKUSA.jp編集部
IKUSA.jp編集部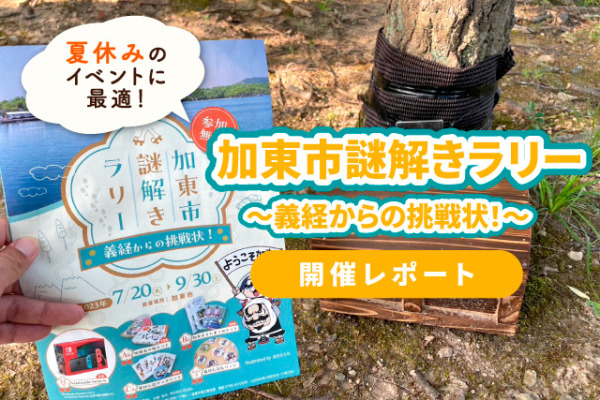

 チョビベリー
チョビベリー