updated: 2026
社内研修のスケジュールの立て方・手順、注意点を解説

社員研修では、事前にしっかりとスケジュールを立てているかどうかで研修自体で得られる成果が全く異なってきます。特に研修担当者の方は、このスケジュールを立てる工程で悩まれる場合も多いでしょう。
今回はそんな研修担当者の方のために、社員研修で役立つ有効なスケジュールの立て方についてご紹介いたします。
参加者が主体的に学び、定着する体験型研修「あそぶ社員研修」。
階層やお悩みに合わせてカスタマイズしたご提案が可能です。
⇒「何ができるの?」が一目でわかる資料を見てみる
⇒検討段階でOK!まず相談してみる
社員研修のスケジュールを立てる手順

一般的に、社員研修のスケジュールは以下のような手順を踏んで作っていきます。
研修カリキュラムの設定
研修カリキュラムを設定するにあたって、まずは経営者に人材育成方針を確認し、その内容を具体的なスキルや知識にブレイクダウンします。その後、社員にもヒアリングし、新入社員に身に付けさせたいスキル・知識の程度を把握しましょう。例えば前年度の新入社員には、「新入社員研修で役立ったこと」「新入社員研修で学んでおきたかったこと」「学べなかったために困ったこと」を尋ねます。また先輩社員には、「現場に配属される前に知っておいてほしいこと、身に付けてほしいこと」「前年度の新入社員を育てる中で感じた課題」を聞くとよいでしょう。
また研修の受講者に事前課題(アンケート)を行い、受講者の現状を把握します。ビジネスマナーなどは基礎から教える必要がありますが、PCスキルや語学力については、事前課題や入社試験の結果をもとに把握しておく必要があります。そのうえで、新入社員のレベルに合った研修を設計しましょう。
さらに研修の目的・目標は、目標行動と合格基準を設けて具体的に設定します。また各目標に対し、期限を設定することも重要です。「いつごろまでに、何を、どの程度までできるようになるか」という形で目標設定を行いましょう。例えば、「入社後3カ月までに、独りで顧客対応ができるようになる」という形です。
なお目標設定の際は、解釈が多様になる言葉を避け、明確な行動状態を設定しましょう。
カリキュラムの外注or内製を判断する
研修の外部委託と内製化には、それぞれメリット・デメリットがあります。カリキュラムの内容によって、外部委託するものと内製化するものを整理しましょう。
例えば、自社の状況や業界の課題などについての研修は、その内容に精通した内部講師が行うのが適切です。一方、ビジネスマナーやビジネスライティングなど、業種や職種に縛られない研修で、かつ社内では専門的に教えられないものは、外部委託したほうが質を担保できます。
各担当の予定を確認し、スケジュールを立てる
外部講師の予定、社外セミナーの開催予定、内部講師の予定、他の社内行事の日程、関係部署における業務の繁忙期・閑散期などを踏まえて、スケジュールを策定します。特に実地研修を行う場合は、現場との早めの予定調整が不可欠です。また、日程が合わず集団研修を行えない場合は、E-ラーニング(動画配信)や通信教育などの方法で補うことも考えましょう。
社員研修のスケジュールを立てる際の注意点

社員研修のスケジュールを立てる際には、以下のような点に注意しましょう。
まずは自社や業界についてのインプットを優先
自社や業界についての知識をあらかじめ身に付けたあと、実践的な内容に入ったほうが、仕事のイメージを持ちやすく、知識やスキルが身に付きやすくなります。また、就業規則や社内施設など、会社で働くうえで不可欠な内容の説明も、早いうちに行うのが適切です。ビジネスマナーやビジネスライティングなど実践的な内容は、後半以降に持ってきましょう。
フィードバックの時間を作る
社員の知識・スキルの定着や、今後のフォローアップのため、必ず振り返りの時間を設けましょう。アンケートも併せて行い、次年度以降の社員研修の改善に活用します。1日の終わりや研修期間中の毎週末など、定期的に行うことが重要です。また振り返りは、研修時間内の、受講者のモチベーションが高いうちに行いましょう。
外注のカリキュラムと内製のカリキュラムは日程を分ける
「1日目は内部講師が研修をする日」「2日目は外部セミナーに参加させる日」など、内製化する部分と外部委託する部分で日程を分けましょう。「午前中のうちに内部講師が社内で研修を行い、午後は社外セミナーに参加させる」といった予定の立て方では、研修の進行が慌ただしくなってしまいます。
こまめに休憩時間を設ける
受講者の集中力を保つため、こまめに休憩時間を取ることが必須です。時間の目安としては、1時間~1時間半ごとに20分前後を確保するとよいでしょう。
外注と内製のメリット・デメリット

研修カリキュラムを外注する場合と内製する場合には、それぞれメリットとデメリットがあります。
特徴を把握した上で状況によって決めていきましょう。
外注カリキュラムのメリット
確かな指導技術
講義をするのはプロなので、社内研修のように指導能力のバラつきが起こる可能性が少なく、参加者は安心して研修を受けることができます。
社内リソースを割かなくて済む
外部研修の場合は専門の施設でおこなわれるため、研修に必要な設備などが整っていることがほとんどです。便利なレンタルサービスや、必要に応じてお弁当やケータリングサービスが利用できる所もあり、ほとんど準備に手間がかかりません。
外注カリキュラムのデメリット
コストがかかる
外部研修だと、場所を借りる費用や交通費など、ほかにも適宜費用が発生します。手間がかからない分ある程度の費用が必要となるため、研修の内容や規模を加味してカリキュラムを組む必要があるでしょう。
実務との関連性は薄い可能性も
研修企業のマニュアルによっては、実務ですぐに役立つ内容ではないこともあるでしょう。自社に特化した研修でない場合は、自社業務について体系的に理解するのが難しい場合があります。
研修計画書・研修スケジュールの作成方法

企業全体の研修は研修計画書にまとめ、漏れが無いようにします。
研修名、対象者、実施予定時期、開催回数、一回当たりの開催日数、参加予定人員、年間参加延べ人数、研修の目的と内容などを一覧表にして作成します。
研修計画書や日程スケジュールでは、縦に研修項目を記載し、横に日程を記載したガントチャート方式のスケジュール表を作成し、項目に漏れが無いか、日程に重複がないかなど、緻密に計画し設定していく必要があります。
新人研修の場合
特に新人研修の場合は、研修内容が多岐にわたるので計画やスケジュールを綿密に作成する必要があります。
新入社員が数十人以上入社する企業においては、4月1日の入社式のあと、1か月から3か月程度の日数をかけて、新入社員教育を実施します。
ここでは社会人として最低必要な電話での応対の仕方、名刺の渡し方、受け取り方、言葉遣いなどのマナー研修に始まり、座学で業界の現状、会社の歴史、取り扱い製品の説明、社内各部門の業務の説明などを行います。
国内各地に工場や事業所がある場合には、それぞれの拠点を訪問し、時間をかけて工場での現場実習や営業部門での営業実習を行います。
自社の研修所がない場合
大企業のように自社で大きな研修所を持っていない場合、研修会場の確保、宿泊場所の設定、工場実習や営業実習をお願いする工場や支社への依頼、座学の講師の手配など、さまざまな内容にしたがって、日程調整や手配をしていかなければなりません。
研修におすすめのサービス
ワールドリーダーズ

ワールドリーダーズは、企業経営を擬似体験できるビジネスゲームです。一チームが一企業となり、企業の利益をどれだけ上げられるかを競い合います。
利益は、労働力や資本を使って上げることができます。
しかし、このゲームは闇雲に利益を追求するだけでは勝利できず、勝利のためには、社会や環境など、様々なことを考える必要があります。
本ゲームでは SDGsにおける企業の役割だけでなく、戦略の立て方や情報共有、駆け引き、チームビルディングなどについても学ぶことができます。社内研修にぴったりです。
カイジ×チームビルディング ~悪魔的社内研修を生き延びろ!~

⼈気漫画・アニメシリーズ『賭博黙⽰録カイジ』の世界に入り込み、カイジのゲームを通してチームビルディングができる、新体験型イベントです。
常に極限の状態に置かれる『カイジ』のスリリングな緊張感の中で、心理戦や戦略立ての過程でチーム内の活発なコミュニケーションや信頼関係の構築を促進します。『カイジ』が好きな方はもちろん、そのストーリーを知らない方も楽しめる内容となっています。
実施ゲームは以下の通りです。詳細はリンクよりご確認ください。
- 限定じゃんけん
- 地下労働
- 鉄骨渡り
- スリー・ポーカー
- Eカード
SDGs カードゲーム「2030SDGs」
カードゲーム「2030SDGs(ニーゼロサンゼロ エスディージーズ)」は、SDGs17の目標を達成するための“道のり”を体験できるカードゲームです。プレイ人数は最低5人から、最大で200人規模まで対応可能です。
このゲームは、SDGsの目的やゴールについて学ぶゲームではなく、「SDGsの本質」について体感的に学べる内容になっており、SDGsについての理解や興味がない人でも、プレイすることで「SDGsとはこういうものなんだ」と理解できます。
例えば、「交通インフラを整える」というプロジェクトを実行するには、お金と時間が必要になり、それと引き換えに新たなお金と時間がもらえます。そして、交通インフラを整えることで経済は良くなりますが、一方で環境は破壊されます。そのため、世界の状況メーターの「経済」はプラスになりますが、「環境」はマイナスになってしまうのです。
2030SDGsは、このように、お金や時間といった制約の下で自分の価値観を満たしつつ、世界の状況を整えるにはどうしたらいいかをプレイヤー自身が考えていくゲームとなります。
SDGsというと遠い世界の話と思っている方も多いかもしれませんが、ゲームを実施してSDGsを「自分事化」することで、SDGsへの理解を深めることができます。深い学びを得たいときには、特におすすめできるワークショップです。
ある惑星からのSOS
「ある惑星からのSOS」はオンラインで楽しめる、SDGsと謎解きを掛け合わせたイベントです。 参加者の皆さんは「ある惑星」の課題を解決するというミッションを与えられます。 謎を解いて情報を情報を整理することで、惑星の課題を解決する方法を導き出すことができます。 チームでゲームを進めるなかで、知らず知らずのうちに、今世界で起きている問題や、SDGsの必要性を学ぶことができます。
謎解きには協力が不可欠、チームビルディング効果のあるゲームです。SDGsという堅苦しいテーマを扱いますが、気負わずに楽しく研修に参加することができます。
SDGs マッピング
SDGsマッピングは、自社の取り組みとSDGsを結びつけるワークショップです。 SDGsの目標を構造化して示した「ウェディングケーキモデル」に自社の取り組みを分類し、自社とSDGsのつながりを見つけます。 IKUSAのSDGsマッピングは、SDGsボードゲーム「ワールドリーダーズ」もしくはオンラインSDGs謎解き「ある惑星からのSOS」とセットで実施します。
これらのゲームとワークショップをセットで行うことで、ゲームでの体験をより深い学びに落とし込むことができます。また、ワークに入る前に、SDGsの基礎的な内容について解説を行うため、SDGsの知識があまりない方でも気軽に取り組めます。 SDGsマッピングを行い自社とSDGsのつながりを感じることで、SDGsを身近なものとしてとらえ、自分ごと化することができます。
会社のことを改めて整理するので、普段の業務に役立つことでしょう。
リアル探偵チームビルディング
リアル探偵チームビルディングは、協力や教え合いを促進し、それを通して学びを得るジグソー法を基にした、アクティブラーニング型チームビルディング研修です。
ジグソー法とは、アメリカの社会心理学者が提唱した、人種間の壁を取り除くために開発された手法です。参加者は①大グループとその中の②小グループに所属し、②にはそれぞれ別の情報が与えられます。
参加者は②で個別に話し合った内容を①に適切に情報を提供し、お互いに教え合いながら、学習を進めいていくことで学習効果が高まります。
楽しい研修ですが、高い効果を見込めるおすすめのゲームです。
リーダーシップ研修「グレートチーム」

「グレートチーム」は、IKUSAのリーダーシップ研修の中で行うビジネスゲームです。
チームに分かれて、「プロジェクト」をメンバーに割り当てたり、さまざまな状況に対して提示された選択肢を選ぶ「リーダーズチョイス」を行ったりして、多くの報酬を稼ぐことを目指します。
メンバーのリソース管理や育成、リーダーとしての決断を繰り返すことで、いろいろなリーダーシップの型を知り、リーダーシップやマネジメントについて学ぶことができます。
また、リーダーシップに関する講義もセットになっているため、座学だけ、アクティビティだけの研修に比べて、より深い学びを得ることができるのも特徴です。
合意形成研修コンセンサスゲーム
合意形成研修コンセンサスゲームは、物語を通して複数人で合意形成をする過程と要点を実践しながら学べる研修です。
参加者同士で議論を行い、自分と他人の考え方や価値観の違いを知ることができます。また、結論を導くための論理的な思考、情報の整理力を向上させることも可能です。
オンラインツールを利用しての開催・リアルでの開催どちらにも対応しております。
協力することが大切な普段の業務内でも、話し合い「合意」獲得に至った経験は大きく役立つでしょう。
まとめ

社内研修は、参加者にとっても企業にとっても重要なイベントです。組織として成長するために、人材の成長は欠かせないため、あらかじめしっかりとスケジュールを立てた上で、限られた時間で無駄なく成果を求めることが大切でしょう。
研修の目的に応じて外注と内製を使い分けながら、有意義な研修スケジュールを立てましょう。
この記事を書いたIKUSAは、階層別にカスタマイズできる体験型研修プログラムをご提案しています。
検討時期が先でも、お気兼ねなくご相談ください。
⇒どんなことができるか資料を見てみる
⇒まず相談してみる




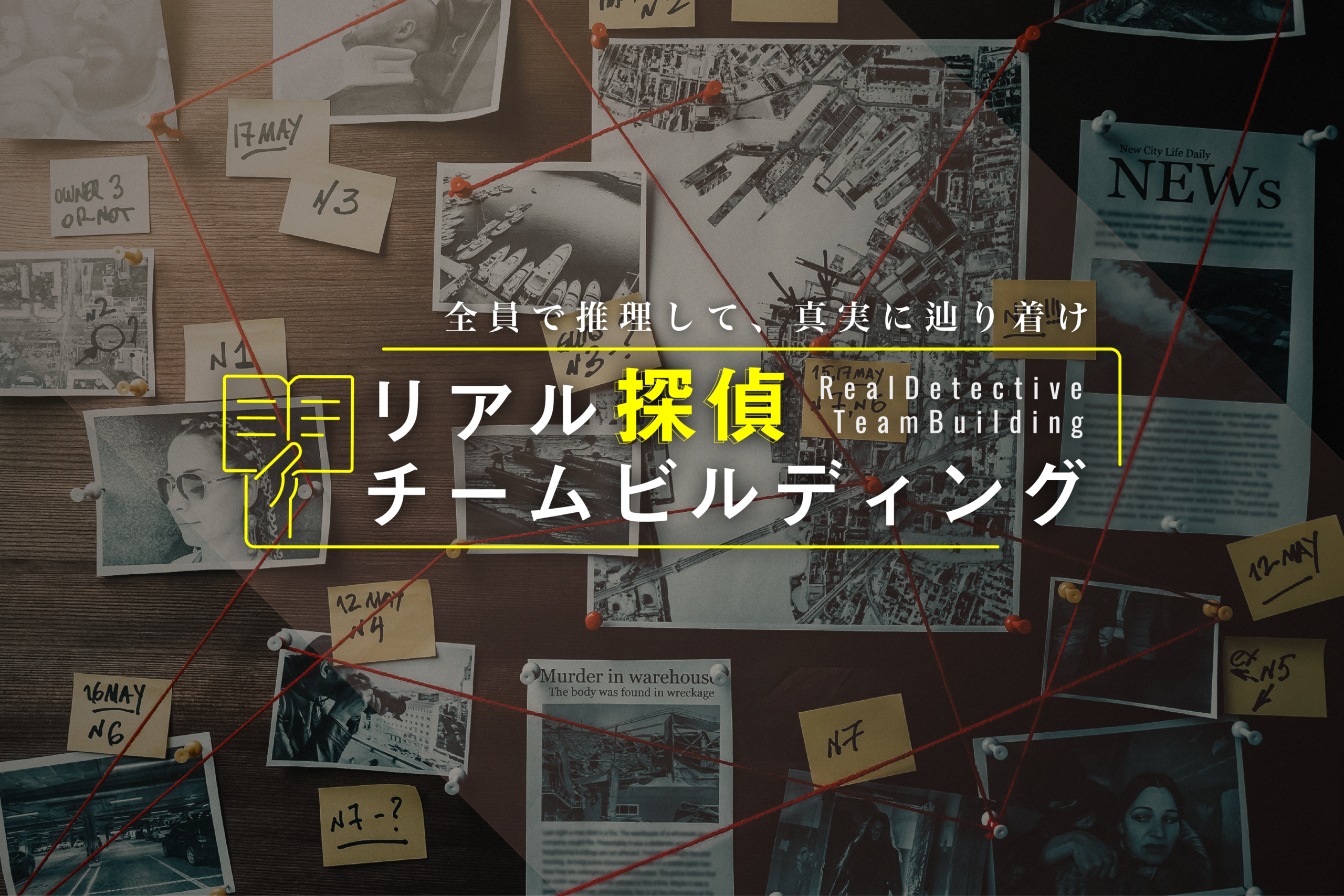


 IKUSA.jp編集部
IKUSA.jp編集部




