updated: 2026
福利厚生の利用率が低い原因・対処法を紹介

本記事では、福利厚生の利用率が低い原因・対処法を紹介します。
失敗できない社内イベント、準備は万全ですか?
年間1400イベントのプロに丸投げで安心のチームビルディングイベント
⇒企画案や実績、実施までの流れを見てみる
⇒企画段階でもOK!今すぐ相談してみる
福利厚生とは
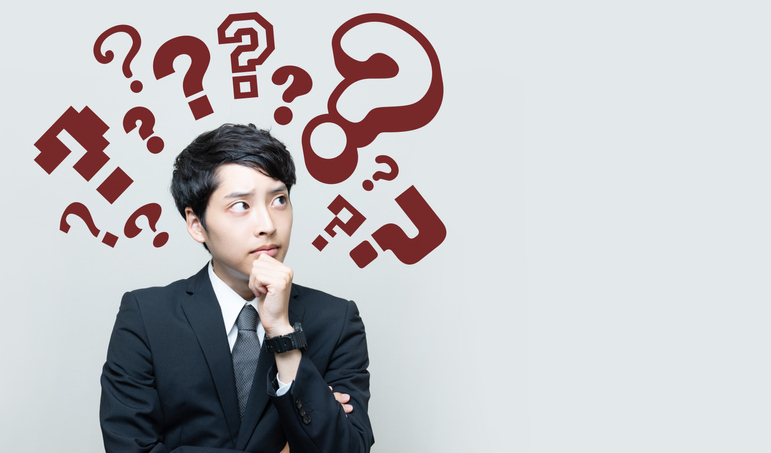
福利厚生とは、賃金・給与以外の手当など、企業が従業員に対して行う支援です。
法定福利厚生と法定外福利厚生の2種類があり、多岐に渡ります。
福利厚生の利用率が低い原因

以下で、福利厚生の利用率が低い原因を紹介します。
福利厚生の内容が魅力的ではない
制度内容が魅力的ではない可能性が考えられます。福利厚生の制度が従業員のニーズに応えるものでなければ、利用率が上がらない場合があります。
従業員に福利厚生制度が認知されていない
認知度が問題の場合もあります。福利厚生制度の内容を従業員に説明し、理解を深めることが大切です。
福利厚生の利用率が低い場合の対処法

以下では、福利厚生の利用率が低い場合の対処法を紹介します。
従業員の要望を汲み取った福利厚生制度を設ける
福利厚生を利用してもらうためには、従業員が何を求めているのか把握することが重要です。従業員に対してアンケートを取ったり面談でヒアリングを行ったりして要望を汲み取ることが重要です。
従業員に福利厚生の内容を伝える
認知度が低い場合は、従業員に福利厚生の内容を伝えたり、説明したりすることが大切です。メールで全体に周知させる方法や、社内セミナーを実施して福利厚生制度について説明する方法などがあります。
まとめ

福利厚生の利用率が低い背景には、内容や認知度などがあります。改めて自社の福利厚生を見直した上で利用率を上げるための対策を行いましょう。
このまま企画を進める前に、他社の成功パターンも見てみませんか?
年間1400件の体験型イベント実績をもとに、目的に合う企画と進め方をまとめました。
⇒「IKUSAサービス説明資料」を無料で見てみる
⇒ 企画段階でもOK!まずは相談してみる
RELATED ARTICLES関連する記事
RECOMMENDおすすめ記事


 IKUSA.jp編集部
IKUSA.jp編集部




